�r���s�ט_�@��T��
�S�̖̂ڎ��֖߂�
��T�� �ڎ�
- ��T���F���A���̏���
- (5.1)�F���[�S�[
- (5.2)�F�������j�T��
- (5.2.a)�@�@�@���F���Ă̏ꍇ
- (5.2.b)�@�@�@���F���{�̏ꍇ
- (5.3)�F�������̖{��
- (5.3.a)�@�@�@���F�������̋@�\
- (5.3.b)�@�@�@���F��������
- (5.3.c)�@�@�@���F���扺����
- (5.3.d)�@�@�@���F�l������
- (5.4)�F�g�ѕ֊�i���܂�j�̏�����
- (5.5)�F�������ӂ��ތ���
- (5.5.a)�@�@�@���F��C�E���E�H�ו�
- (5.5.b)�@�@�@���F�A���E�ہE�Í�
- (5.5.c)�@�@�@���F���������ƃG���g���s�[
- (5.5.d)�@�@�@���F�n����
- (5.5.e)�@�@�@���F�������ӂ��ތ���
- (5.2)�F�������j�T��
- ���Ƃ���
- ����
�S�̖̂ڎ��֖߂�
�i�T�j ���A���̏���
�i5.1�j�F���S�[
���B�N�g���E���S�[�w���E�~�[���u���x�̍Ōタ�����A��l���W�����E���@���W�������A�o���P�[�h�ŕ������C�������Ă���N�}�����X�������ŁA�p���s�X�̒n���̉������ɓ���A������ĐN�̑c���̊ق܂ő���͂���B�����āA���̒��ҏ����̑�c�~���߂Â��B
�p���s�X�n���̉��������čs���Ƃ����A���̒��҂̍Ō�̃N���C�}�b�N�X�̑O�ɁA���S�[�́u���b�̂͂�킽�v�Ƃ����͂��������B���̖`���͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B
�p���͔N�ɂQ��T�S���t�����Ƃ������𐅂ɓ�������ł���B����͂��Ƃ��b�ł͂Ȃ��B�ǂ�����āA�ǂ��������@�ŁH��������ł���B�ǂ������ړI�ŁH�ړI���Ȃ��ɁB�ǂ������l���ŁH�l�����Ȃ��ɁB�Ȃ�̂��߂ɁH�Ȃ�̂��߂ł��Ȃ��ɁB�ǂ������튯�������āH���̂͂�킽�ɂ���āB�͂�킽�Ƃ́H�������ł���B�i��㋆��Y��@�͏o���[�V��1989�@�͏o���E���w�S�W10�@p369�j���S�[�͂��́u���b�̂͂�킽�v�ŁA�ނ̉������_��W�J����̂ł���B�������̉��ǂ�_����Ƃ������A���̉������ɂ���Đ��ꗬ������Ă��镳�A�̉��l���̗g����A�Ƃ����_�̎����čs�����ł���B���̈Ӗ��ł́A���A�_�Ƃ�������B
�����ŁA���_�ł́A���S�[�́u���b�̂͂�킽�v�̕��A�_�Ɋ֘A���āA�����Ă�������������w�E���Ă��������B
���A���엿�Ƃ��ėD��Ă��邱�Ƃ́u�V�i�l�v�̕����悭�m��A�悭���p���Ă���ƃ��S�[�͂����B
�Ȋw�͒����������̍������������A����ɂ��ł́A�엿�̂Ȃ��ł�����y�n���₵�A�������ڂ�����̂͐l�삾�Ƃ������Ƃ��A�m��悤�ɂȂ�B�p���������b�����A�V�i�̐l�̂ق�������������ɂ��̂��Ƃ�m���Ă����B�G�b�P�x���N�̘b�ł́A�V�i�̕S���͒��ɏo��ƁA����ꂪ�����ƌĂԂ��̂��Q�̉��ɂȂ݂Ȃ݂Ɠ���A�|�Ƃ̗��[�ɂ����Ă͂���ł�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��������B�l��̂������ŁA�V�i�̓y�n�͂���ɂ����A�u���n������ƕς��Ȃ��Ⴂ�B�i���@p369�j���̂悤�ɉ��l�̂��镳�A���A�������ɂ���Đ�֎̂āA�C�֓f���o���B���̂��Ƃɂ���āu�y�n�͂₹�A���͉����B�Q�����c�삩��N����A�a�C���삩��N����v�B���S�[�͂��̂悤�ɘ_���āA�p���̉�������f�߂���B
�s�s�p�����s���Ă��邱�́u���ǂ낭�ׂ��C�̂����Ȃ��v�͌Ñネ�[�}�ȗ��̂��Ƃ��A�ƃ��S�[�͗��j�I�ȓW�]���s���B
�u���[�}�̉����́v�����[�r�b�q�͌����Ă���A�u���[�}�̔_���̕�������������݂̂������v���[�}�̓c�삪���[�}�̉������ɂ���čr��͂Ă��Ƃ��A���[�}�̓C�^���A�����Ƃ낦�������̂ł���A����ɁA�C�^���A�������ɗ����Ă��܂����ȏ�A�V�`���A���A�T���W�A���A���ɃA�t���J�������ɗ����������B���[�}�̉������͐��E���݂̂��B�i�����͈��p�ҁ@��p370�j�v����ɁA�p���͂��̌Ñネ�[�}�̉������ƕς��̂Ȃ��A�c����r�p�����߂鉺�����������Ă���ƁA�x����炵�Ă���̂ł���B�i�u��Q�� ���b�̂͂�킽�v�͂U�߂ɂ킩��Ă���B�����܂łɊȒP�ɏЉ���悤�ȕ��A�_�ƌÑネ�[�}�ȗ��̉������j�̂ق��ɂ́A�P�X���I�ɓ����Ă���́A�܂胆�S�[�ɂƂ��Ă̌���j�ł���p���̉������̒�����A�g���ɂ��ďq�ׂĂ���j
����Ń��S�[�����y���Ă����i�D���[�r�b�q�i1803�`73�j�́A�L�@���w�̗��_�I�o���_���悷��h�C�c�̗L���ȉ��w�҂ł���B�p���̃\���{���k��ŃQ�C�����T�b�N�Ɋw��ł���B���[�r�b�q�̓��S�[�i1802�`85�j�Ɗ��S�ȓ�����l�ł���A���S�[�̉������_�ɉe����^���Ă���B�u���[�S�[�́A�����֗��s���������[�r�b�q����A�����l�����A��y�ɕԂ��Ă���A�Ƃ����b���A�܂����[�r�b�q�́w�L�@���w�̔_�Ɨ��p�x��ǂ�ł����Ƃ����v�i�����w�ܑ��Ɖ������̕����xp100�j�B�w�L�@���w�̔_�Ɨ��p�x�i1840�j�́A����܂ŗ��_�I�Njy�Ő��ʂ��グ�����[�r�b�q���A���p���ʂɌ��������Ƃ��̒����ŁA�엿�̂R�v�f�A���f�E�����_�E�J�����咣���A�_�|���w�̊�{���������B�܂�A�A���̐�����h�{�ɂ��镪�͓I�Njy�̏o���_�ƂȂ�A�d�v�Ȓ���ł���B
����Ȃ��ƂɁA���́u�엿�̂R�v�f���v�����{�̑�w�ł́u�A���͖��@�엿�����ł����v�ƒZ���I�ɋ������Ă���A���̐l���엿�E�L�@�엿�ے�́u���w�엿���\�v�̍l�����ɔ��Ԃ������Ă����Ƃ����i���O�f��p100�j�B�܂�A�A���͓y���̉h�{�𒂑f�E�����_�E�J���̖��@�h�{�Ƃ��ċz������̂�����A���������w�엿�Ƃ��Ē��ڗ^����悢�A�Ƃ������_�I�Ȑ����ł���B�u���A���w�엿�̑��Y���\�ɂȂ�ƁA[���{]���{���L�@�엿�̕K�v��S���F�߂悤�Ƃ��Ȃ������v�i��p100�j�Ƃ����B�u�엿�̂R�v�f���v�����w�엿���\�̗��_�I�����Ƃ���Ă����̂ł���B���{�ł͂P�X�V�O�N������A�_�Ƃ̌��ꂩ�牻�w�엿�����𑱂����_�n���g����Łh���܂��Ă��錻�����˂������A�L�@�h�{�������Ղ�܂g�����Ă���y��h�̏d�v�����ĔF�������悤�ɂȂ�B
�A�����L�@���ڋz�����邱�Ƃ��������Ă��������łȂ��A�����̓y���������L�x�ɐ����Ă���y�뒆�ł����_�앨�����N�Ɉ���Ƃ��������Ă����B���N�Ȕ_�앨�����H���Ƃ��ėD��Ă����Ƃ������_�̍ĔF���ł���B�����āA���N�Ȕ_�앨�͌��N�ȓy��Ɉ�Ƃ������_�ł���B
������Ƙe���ɂ͂��邪�A�����ŁA�y��������Ɋ֘A����Ǐ����R���Љ��B
�f���B�b�h�E�v�E�E�H���t�w�n�������̋��فx�i�y��2003�j�͎��ɖʔ����{�ŁA�m�I�D��S���������Ă���B�����Ɋ֘A����P���Ⴞ���Љ��B�قƂ�ǂ̗���A���͓y���ɉ��낵�Ă��鍪�ɂ����āA�n���̐^�ۗށE�ۗނƋ������Ă���̂��Ƃ����B�}���ȐA���̒��f�Œ�ۂƂ̋����͂悭�m���Ă��邪�A����́i���ɏd�v�ȁj���ɂ����Ȃ��B���������^�ۗށE�ۗނ��u�ۍ��v�ނƂ����炵�����A�y���̐�����~�l��������A�����z���ł���`�ɂ��č��ɒ��Ă���B�A���̕��́A�n��Ō����������h�{��������Đ^�ۗނɗ^���Ă���B���̂悤�ɂ��āA�A���Ɛ^�ۗނ͋����W�Ō��т��Ă���B�n���[���L������߂��炳�ꂽ�ێ��Ԃɂ���āA�A�����m���Ȃ����Ă��邱�ƂȂǂ��m���߂��Ă���B����J�G�f����ׂ̃J�G�f�֗{�����ڂ邱�Ƃ����ː��̃J���V�E����ӂ�p���Ď�����Ă���B�}���Ȃ̐A���ɂ���ČŒ肳�ꂽ��C���̒��f���A�ۍ��ۂ̓����ɂ���ėׂ̃}���Ȃł͂Ȃ��A���Ɉڂ邱�Ƃ��������Ă���A�Ƃ����i�O�f��p141�j�B
����ꂪ�A����H���Ƃ��Ă��ׂ�Ƃ��A�����āA�n���̖��@�h�{�f�ƌ������̐��ʂ�H�ׂĂ���A�Ƃ����悤�ȊȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B����A���́A�y���ɍL��ɍL����g�n���������h�ɍ������낵�āA�����ƌ��т��āA�n��ł̉i���I�Ȑ����������Ƃ��Ă���̂ł���i�i���I�Ƃ����̂́A�l�ނ́g�������E�h�̎������S�`����N�ɔ�r���Ă̂��Ƃ����j�B�u���w�엿���\�v���\���Ǝv�����̂͂ق�̐��\�N�Ԃł����Ȃ������B�킽���������H����H�ׂ�Ƃ��A�R�T���N�̐����i���j�̑��̂�H�ׂĂ���A�ƍl����ׂ��ł���B�킽�������́u�H�ו��̂قƂ�ǂ͐������̂ł����v���A���������g�������i���j�̏�ɐ������Ă��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ����Ƃ��B
�����ׁw��n�̔��������E�x�i��g�V��1987�j��ǂ�ŋ��������Ƃ́A�y�뒆�̍ۂɂ��ẮA�قƂ�ǂ����m�ł���A�Ƃ������Ƃ��B�R�b�z�́u���@�v�i�y�g���M�̏�Ɋ��V��[���`���̔|�{���ɂ���A���̏�ɂ������ۂ�h�z����B�����`���T�ԂŃR���j�[���ł���j�ŃR���j�[�����y��ۂ͑S�̂̂P�����x�ɉ߂��Ȃ��̂��Ƃ����B �c���99���́A�|�{��̉h�{�ɔ����������B���Ȃ��̂ł���B�]���āA�����̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B���Ƃ��ΐ��c�̔������́u�n����̗��n�ɏZ�ޔ����������ŁA�����Ƃ��悭��������Ă����v�ip108�j�ł���̂��Ƃ����B�����ɂ́A�y�P�O���������萔�\���̍ۂ�����i����́A�������Œ��ڐ�����j�B�������A���܂��܂ɗp�ӂ���Ă���|�n�Ŋ������ăR���j�[�����̂́A���̂����킸��0.1���ȉ��ł���B
�܂茤���̑ΏۂƂȂ��������ۂ́A���c�ɏZ�ލۑS�̂̂Ȃ��́A�킸���O.�P���ȉ��ł���B����ł́A���̂X�X.�X���̍ۂ́A�������Ă���̂ł��낤���B�i��p108�j�u���R��������ᔻ�������̃p�X�g�D�[���̍l�����́A�������͉h�{�����^������A�K�����B���N����Ƃ������Ƃł������v�ip162�j�B�������A�u�y���͂��߂Ƃ��鎩�R�ɏZ�ޔ������̂Ȃ��ő��B���ł�����̂͂���߂ď��Ȃ��A�ނ����O�I�ł���Ƃ����悤�v�ip196�j�B�܂��A���B����ۂł��A�R���j�[������ē���Ɍ�����悤�ɂȂ�قǂ̑��ʂ̑��B�́u�ނ���܂�ł���v�B���Ď~�܂��Ă��܂��悤�ȃP�[�X�������̂��Ƃ����B
�������ɂ��Ă����Υ������������ꂽ�̂́A����ŃR���j�[���`��������̂̂����A���������ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�������R���j�[�����������́A�S�̂̂P�p�[�Z���g���x�ł���ƍl����ƁA�n����ɂ͂����ɖ��m���������������z������悤�B�i��p203�j
���؈��w�����w�Ɋ�Â����̊�b���_�x�i�C��1999�j���A�m�I�D��S���������Ă��邷�炵���{�ł���i���̖{�́A�Ɠc�ւ�ɂ͂��܂�u�G���g���s�[�w��v�̊��_�̌��݂̓��B�_�������Ă���B���̍��i�͎���5.5�u�������ӂ��ގЉ�v�ŏЉ��j�B���j�[�N�ȑ}�b�����������Ă��ċ������Ȃ��ł���A�ǂ�ǂ�ǂݐi�߂���B���̒�����A�����ƐA���̔�r�A�����̏����ǂƓy��̔�r�����Ă���Ƃ�����Љ��B
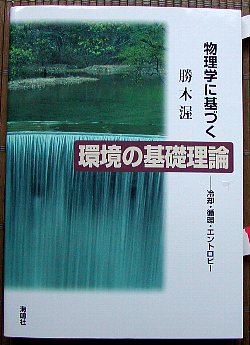
�A���́A����{�����n�̓y�납�獪�ɂ���ċz������B���̂��߂ɐA���A���ɍ��̂���A���́A���̂ƂȂ��Ă���͈ʒu�̈ړ������R�ɂ͂ł��Ȃ��B�i�Ȃ��A���̏��؈��̖{����Ɏ������A���Ёu�܂������v�ƁA�u���Ƃ����v�ȉ��̒����́u�ӎ��v��u��Q���ɂ������ẴR�����g�ƒlj��v�����ǂނׂ��ł���B�j
���������R�Ɉړ��ł���̂͂Ȃ����B����́A����̓��Ɏ�荞��ł��邩��ł���B���Ȃ킿�A�A�A���ɂƂ��Ă̓y��ɑ���������̂������ǂƂ��đ̓��Ɏ�荞�݁i���t����n�܂��āA�y�뒆�̔������ɑ������鐔�X�̏����y�f���A�����ǂ̒��ł͂��炢�Ă���j�A�����������̊C�ɑ���������̂����t�Ƃ��đ̓��Ɏ�荞��ł��邩��ł���B���ǂ��邢���O�т́A�A���̍����邢�͍��тɑ������Ă���B
�A���̗���ɗ��ƁA�y��͂����݂̈⒰�ɑ������Ă���B���A���w�엿�̗��p���ɂ���āA�y���a��ł���ƌ����邪�A�A������u�A����v�ɖ|��A�A�������͂����̈ݒ��a�ɑ�������a�������Ă���A�ƌ����悤�B���Ă��≺���ɔY�ނ悤�ȂƂ��A�����͕a�ޓy�ɐ�����A���̋�Y�ɂ��v�����������ׂ��ł���B�ip127�`8�j
�w���~�[���u���x�̎��M�͂P�W�S�T�N����S�W�N�ɂ����ď��e�A�����Ԓ��f���ꂽ�̂������͂P�W�U�Q�N�ł���B���̎����́A�p���ł���Ƌߑ�I�ȉ������H�����͂��܂��������ɂ������Ă���B�p���ł͂P�W�O�W�N���ɉ������i�J�����j���Q�Okm���炢��������Ă����B�p�������̑剺�����́A�����E�J���E���H��̃S�~�Ȃǂ�S������A�㐅���E�K�X�ǂȂǂ̋������݂����˂Ă���B���̌��݂́A��Q�鐭�i1852�`70�j�̎n�߂���I���܂ŁA�P�W�T�Q�N�ɑ������P�S�Okm�A�P�W�U�X�N�ɂ͂T�U�Okm�ƂȂ��Ă����B
���̍��̉����́A������s�s��������O���ֈڑ����A�����ŕ��o����@�\�������Ă��������ŁA���������Ƃ������z���Ȃ������B��������o�����Z�[�k�삪�]��ɂ������̂ŁA�����̏o�������ւ��āA�����Ɉڂ����̂����̍��ł���B�������Ƃ̓C�M���X�ł������Ă���A�����h���ł̓e�[���Y��̉��L���Ђǂ��č���c�����ŐR�c�ɂ����������قǂ������Ƃ���
�������̌��݂́A�����h���̕����A����s���Ă����悤�ł���B�P�X���I�O���ɉ������̐ݒu���i�ނɏ]���āA����܂ł͎s������n�Ԃś��A��_���։^�яo���Ă����̂��A�������������Ɏ̂ĉ������̓e���Y�͂ɕ��o���邱�ƂɂȂ����B���s��r�w�R�����̐��E�j�x�i������1994�j�ɂP�W�Q�V�N�̕����������Ă���̂ŁA��������p�����Ă��������B
���ɁA�����̈����B[�u�^�C���Y�v�̕ҏW�҂ł���] ���C�g�͂��̂悤�Ɍ����B�u���ꂾ�����������̐l�Ԃ����ꂾ��������ԂɏW�܂������Ƃ́A����܂ł̕����j�ɂȂ������Ǝv���B�v���́u���g���|���X�v�����f����e���Y�͂̐������������Ă���B�����͉����̃^�������ł���B�ȑO�̓e���Y�͂ɃS�~�𓊊����邱�Ƃ������̑ΏۂɂȂ����B�Ƃ��낪�A[�ȉ��A���p�́A���C�g�̂P�W�Q�V�N����]�����[�����Ƃ́A���̕����łP�X���I�O���܂ł̓����h���̎s���̛��A�����Ӕ_���֔엿�Ƃ��ĉ^�яo����U�z����Ă������Ƃ������邱�Ƃł���B�܂��A�������ɂ���ăe���Y�͂�����A����������𐅓��̌����Ƃ��Ďg���Ă��邽�߂ɁA�s���͔��܂������������ɂ��邱�ƂɂȂ��Ă���i���̓_�ɂ��ẮA�����i5.2.a�j���ň������j�B���[���b�p�ł̃R�����̍ŏ��̗��s�́A�O�f�����̒���̂P�W�R�O�`�R�Q�N���Ƃ����B�������N�̊ԂɁA���̓_�ɂ����s�̏�Ⴊ�܂����������̂��̂ɂȂ����B�R���I�O�ł���Έ�@�s�ׂƂ݂Ȃ���A�����̑ΏۂƂȂ����s�ׂ��A���܂ł͏Z���ɑ��ċ`���Ƃ��Ď��s����悤�ɏ��コ��Ă���̂ł���B���̖��̌��Ђł���T�[�E�M���o�[�g�E�u���[���ɂ��Υ������w����܂Ŋe�ƒ�̉����͂��ׂĉ������߂ɏW�߁A���|�l�ɥ��������ݎ���Ă�����Ă����B�Ƃ��낪�A���݂ł͉������Ǘ��ψ����������ׂĉ������ɗ������Ƃ��Z���ɋ��������肩�A���サ�Ă���̂��B�x�������ȑO�͖c��ȗʂ̉������n�Ԃɐςݍ��܂�A�엿�Ƃ��Ĕ_�n�ɎU�z����Ă������A���܂≺�������g���ăe���Y�͂Ƀ^���������Ƃ�F�߂�ꂽ�̂ł���B�������i���Ắj�r�����͔_���ɑ����Ă����B���ꂪ����A���̓`�F���V�[���瓌�̓����h�����܂łP�R�X��������������璋��������e���Y�͂ɕ��o����Ă���̂��B�e���Y�͂́u�ЂƂ̋���ȉ������v�Ɖ������B���̐��𐅓���Ђ͎s���ɋ������Ă���̂ł���B�ip153�@[�@]���͈��p�Ғ��j
���c�����Y�̓h�E�J���h���i1806�`93�j�́w�A�������w�x�������Ȃ���A���[���b�p�ł��l���A��엿�Ɏg�p���Ă������Ƃ��w�E���Ă���B
�Ƃ���Ő��E���ŁA�A�W�A�̐��c�k�얯�������A�l�Ԃ��܂̑召�ւ�엿�ɂ��Ă� ��Ƃ����̂́A�傢�ɂł���߂ł���B�h�E�J���h�����A�͂�����A���[���b�p�̔_���͑�̂���ƒ{�̕��A�����łȂ��A�l�Ԃ��܂̑召�ւ����A������ɔ엿�Ɏg���Ă����Əq�ׂĂ���B�i�w�l�Ԃ̗��j�x3-p88�j���W�F���A�����E�Q�����w�g�C���̕����j�x�i���^�J���X��@�}�����[1987�j�͗��_���Ƃ��Ă�����Ƃ��Ă���A���x���̍����Ǐ��ł���B��Ɉ��p�����w��ƂȂ��P�N�����̃g�C���x�̎�{�̂P�ɂȂ��Ă���悤���B���̒��ŁA�X�y�C���̃��[�A�l�������l���엿���悭�g�p�����Ƃ����L�q������B
���A���ɔ엿�Ƃ��Ă̌��ʂ�����Ƃ������Ƃ͒����ȗ��m���Ă���A���̎U�z�� ��ɃX�y�C���̃��[�A�l�ɂ���Ă悭���s����Ă����Z�p�Ȃ̂ł���B�ip137�j�܂�A���[���b�p�ł��l���A��엿�ɂ��邱�Ƃ͒m���Ă������A���{����Ă����B�����A���̕��@�͏\���ɕ��y���Ă����Ƃ͌������A�ߐ����{�ɂ�����悤�Ɏ���Ƃ���ɋ��ݎ�莮�֏�������_���������ēs�s�̕��A�����ݎ��ɂ���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�܂�A���[���b�p�ɂ����Ă͌ʂɁA�܂��͖����ɂ���Ă͐l���A��엿�Ƃ��Ă������A���ꂪ�s�s�̕֏��ƌ��т����L�ĂȃV�X�e���Ƃ��Ĉ�ʉ����Ă͂��Ȃ������B���̂��Ƃ́A���[���b�p�s�s�̕֏��i���p�֏��E���O�֏��j�̖����B�̌����ƂȂ�A�g�ѕ֊�i���܂�j�̕��y�𑣂����ƍl������B�i�����̂��Ƃɂ��ẮA�O�߂̖����u�֏��̕��y�v�ł��q�ׂĂ������j
�P�X���I�����ɂ̓��S�[�̂悤�Ȑl���엿�_�҂������̂ɑ��āA���̈���ł͐l���엿�̔ے�_�i�l���엿�͗L�Q�ł���Ƃ����_�j���������悤�ł���B�Ƃ������A�l���엿�ے�_�̂ق��������h�ŁA���S�[�́u���b�̂͂�킽�v�Łg�ւ��J���h�Ƃ����X�^���X���Ƃ��Ă����A�ƍl������B
�w�g�C���̕����j�x�́A�l���A���엿�ɓK���邩�ǂ����́u�����v���s��ꂽ���Ƃ��q�ׂĂ���B�P�W�U�X�N����p���s�̗\�Z���t���A�����_��ś��A����엿�Ɏg���A�q������āA����ŋ��������A���́u�����ƃo�^�[�͓y�؊w�Z�̎������ŕ��͂���A���ׂȂ��ƔF�肳�ꂽ�v�ip138�j�Ƃ������Ƃł���B����́A���{�ł����Ζ����Q�N�̂��Ƃł������B���[���b�p�ł͐l���A��엿�Ƃ���_�ƋZ�p���������Ă��炸�A���y���Ă͂��Ȃ��������Ƃ��A���́u�����v���{�ɂ���Ď�����Ă���Ƃ����Ă悢�Ǝv���B
�i5.2�j�F�������j�T��
�������́A�s�s�̑��݂�O��ɂ��Ă����Ƃ��Ă悢�ł��낤�B�s�s�Z���̕��A�̔r����肪�������Ɗ֘A���Ă���B�������A�������̖����́A���A�r�������ł͂Ȃ��̂ŁA�ȉ����炭�́i5.2�߁A5.3�߁j�A���A������⎋����L���Č��邱�ƂɂȂ�B
�ŏ��̓s�s�́A�@���������I�_�a�𒆐S�ɂ���ǂɂ����܂�Ă����Ƃ���A�����ւ�Â����瑶�݂��Ă����B
�s�s�̒a���͑O6��`�O1��N�I�ɃA�W�A�̐������ŕʁX�ɂ��������ƍl�����Ă���B�O5000�N�̃��\�|�^�~�A���������̃W�������ƁC�p���X�e�B�i�̃����_���쐼�݂̃C�F���R�C�O3��N�I�̃��\�|�^�~�A�암�̃E���ƃC���_�X��E�݂̃��w���W����_���C����Ƀi�C����⒆���̟͐��ł��O2000�N���ȑO�ɓs�s�����n���Ă������Ƃ��m���Ă���B�i�c�ӌ��� ���}�ЕS�Ȏ��T�u�s�s�v���ځj�s�s�����ɐ�����r�����E�����r���́A�͂��߂͉J���̔r���Ɏg���鎩�R���H�E�@���Ȃǂ�ʂ��ĉ͐�։^��A�s�s�O���֔r�����ꂽ�ł��낤�B�s�s�v�悪�s����悤�ɂȂ�A�l�H���H�⑤�a�Ȃǂ̊J�����̉����H��������悤�ɂȂ����ł��낤�B
�a�b�Q�T���I�̌Ñ�C���h�̃��w���W���E�_����n���b�p�[�̓s�s��Ղɂ͂��łɁA�㉺�����̗D�ꂽ�{�݂��ł��Ă����B�Ñ�A�b�J�h�l�����̃��\�|�^�~�A�̓s�s�i�a�b�Q�Q���I�j�ɂ������֏��≺������Ղ�����B
�����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�Ñ�M���V���̓s�s�ł́A�������͂��납�֏��̈�Ղ�����������Ă��Ȃ��Ƃ����B
�M���V���̓s�s�ɑ��鐸�͓I�Ȕ��@�ɂ�������炸�A�M���V���̏Z��ɕ֏����������Ƃ����l�Êw�I�Ȏ����́A�����̂P����������Ă��Ȃ����A�܂������֏����������Ƃ����؋����S���Ȃ��B�i��Y�o�w�������猩���s�s�x�m�g�j�u�b�N�X1982 p76�j��Y�o�̂��̖{�Œm�����̂����A���Ït�ɖ�̃M���V���Y�Ȃ̂Ȃ��Ɂu�����ꏬ�H�v�Ƃ������̂��o�Ă���Ƃ����B���ׂĂ݂�ƃA���X�g�p�l�X�u���a�v�������B���̋Y�Ȃ̓r�b�N������悤�ȃX�J�g���n�̍�i�������i�L���Ȃ��ƂȂ̂����m��Ȃ����A�킽���̓M���V���Y�Ȃɂ܂������Â��̂Łj�B�����ŁA���ڂ����Љ�Ă݂�B
�u���a�v�́A�A�e�i�C�̔_���g�����K�C�I�X�̓�l�̓z�ꂪ�A���u����ŕ������ˉA�傫�ȕ��c�q�������Ă����ʂ���n�܂�B���̕��c�q�̓g�����K�C�I�X�������Ă��鋐��ȉ������i���]�����j�ɉa�Ƃ��ė^���邽�߂̂��̂Ȃ̂��B�g�����K�C�I�X�̓y���|�l�\�X�푈���������̂ɕ��𗧂ĂāA�V�̃[�E�X�ƒk�����邽�߂ɂ��̉������ɏ���ēV�������オ���Ă������Ƃ��Ă���B
�����オ�낤�Ƃ����l�g�����K�C�I�X�ɓz��̂ЂƂ肪�A�u���̂��߂ɁA���̋C�Ⴂ�����v������̂��A�Ɩ₢������B����ւ̃g�����K�C�I�X�̓����B
�Â��ɁA�s�g�Ȃ��Ƃ����p�́A�w���E�ÓT���w�S�W�P�Q�x�i���Ït�ɕ� �}�����[1982 p175�@�����͈��p�ҁj�B�u�����ꏬ�H�v�ɖ����Ă��āA�u�̂̃M���V���̒��ł́A�ƂƉƂ̊ԂɘH�n�������āA�����ɂ͉����������ς����܂��Ă����炵���v�Ƃ��Ă���B����̏�����ɂ́u���֏��H�v���o�Ă��邪�A�������̂��w���Ă���悤�Ɏv����B�i���łɁA�u��B�v���o�Ă���̂�����A�M���V���Z���̍l�Êw�I�����͂Ȃ��Ƃ��A�֏��͂������̂ł��낤�B�j
�Ђƌ������ɂ��Ă͂Ȃ��̂��A�����ƂȂ���B
������A�l�݂ȂɁA�����܂�ƁB
��B�������ꏬ�H��
�V���������ōǂ���A
�K�̌��ɂ͐�������B
���{�������̓s�s�f���Ă���ł��낤�u�f�։�S�v�̐}�i��4.6���j���v���o���B�܂����ł́A���E�̊e�n�̓s�s�Ɂu���֏��H�v�����������Ƃ��q�ׂĂ������B
�H��������ΎG�r���͐����邵�֏��͂Ȃ��Ƃ��r���s�ׂ͂������킯�ŁA�����̓s�s�O���ւ̔r���͕K�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��������R�I�Ȕr���H�ł܂��Ȃ����Ƃ̂ł����s�s���������ł��낤�B�����A�l�����W�≺���ʂ̑����ɂ���āA�l�H�I�Ȕr���H�i���H���a�≺���a�j����������A�l�́E�ԂȂǂʼn����E�o�H��s�s�O���֔r�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ����ł��낤�B�r���H�̈��L��s��(�`���a�ւ̔z��)����A�Ë��ɂȂ�����ǘH�ƂȂ����肷��B
�����H���K�v�ƂȂ�����ЂƂ̗��R�́A�~���̔r���ł���B�~���ʂ̈Ⴂ�ɂ���ĉ��������S���d�v�x�ɈႢ���o�Ă��邱�ƂɂȂ邪�A�s�s�����Ɉ쐅�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�ق�Ƃ��́A������̗��R�̕��������r������s���Ă��邩���m��Ȃ��B
�͐�ɉ������y�n�ɓs�s�����܂�A���Ƃ��Ƃ��������R�������r���H�Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ�B�K�v�Ƃ���A�^�́E�����a�Ȃǂ��l�H�I�ɍ����悤�ɂȂ�B���n�т̔r���ɂ���ēy�n���L������A���ߗ��Ēn������A�����ɓs�s������Ă����B���������ꍇ�́A���Ƃɔr���̋@�\���d�v�ł���B�͐�Ǘ��Ɖ������Ƃ��֘A���Ă���B
�������̏d�v�ȋ@�\���ӂ������Ă����B
| �q�P�r�����E�����r�� |
| �q�Q�r�~���r�� |
�M���V�������������Ñネ�[�}�ɁA���łɉ����������������Ƃ̓��S�[���M�ق��ӂ���Ă����悤�ɁA�悭�m���Ă���B���[�}�̏㉺�����⓹�H�ɂ��ẮA�����ł͐G��Ȃ����Ƃɂ���B�������A���[�}�鍑���S�ƂƂ��ɁA�鍑�̌ւ铹�H�≺�����Ȃǂ����S���A���[���b�p�̒����s�s�ɂ��̉������͈����p����邱�Ƃ͂Ȃ������B�s���ʼnu�a�����s���钷�������ƂȂ�B
�i5.2.a�j�F���Ă̏ꍇ
�Y�Ɗv���ɂ���ēs�s�ɐl�������W���A�H��̔����E�p�t�ɂ���ĉ������ꂽ�Ȋ����Ɍ��ɂ܂ŒB�����A���̂͂ĂɁA���[���b�p�ł��ߑ�I���������͂��܂�B�܂�A���[���b�p�̋ߑ�I�������́A������s�s�������P���邽�߂ɕK�R�I�ɁE���s����I�ɍ���Ă��������̂ł���B���{�̏ꍇ�̂悤�ɉ��Đ�i�̂���{�����Ȃ��瑢���Ă������̂Ƃ́A���{���قȂ�B
�����ŁA�L���ȃG���Q���X�́w�C�M���X�ɂ�����J���ҊK���̏�ԁx�i��g���� �㉺ 1990�j���Q�Ƃ��Ă������B�h�C�c�E�v���C�Z���łP�W�Q�O�N�ɐ��܂ꂽ�t���[�g���b�q�E�G���Q���X���A���̌o�c����H��̎��������邽�߂ɃC�M���X�̃}���`�F�X�^�[�֍s�����̂͂P�W�S�Q�N�̂��Ƃł���B
�����̃}���`�F�X�^�[�͐l����S�O���̈��H�Ɠs�s�ŁA�C�M���X�݂̂Ȃ炸�A���E�̖ؖȍH�Ƃ̈�勒�_�ł������B�����ł͏��C�͂Ƌ@�B�ނ��p�����A���Ƃ̒������i�W�̂��ƂɁA��K�͂ɐ��Y���s���Ă����B�i�꞊�a���E���R���� ������� �㊪p319�j�G���Q���X�́A�Z���u��P�� �H�ƃv�����^���A�[�g�v�ŁA�H�Ƃ��W�����l�����W�����s�s���`������邱�Ƃ��q�ׂĂ���B���̂����ŁA�����͂ł���u��Q�� ��s�s�v�Ŕ��ɑ��ʂȎ������W�߂āA�����h����}���`�F�X�^�[�̑�s�s�Ő�������H��J���҂�n���̌����������B���Ƃ��A���̂悤�ȋ�ł���B
�u�����̊X�H�́v�ƁA�s�s�̘J���҂̌��N�ɂ���_���̂Ȃ��ŁA����C���O�����h�̎G�����`���Ă���B�u�����̊X�H�͂����Ђ��傤�ɋ����̂ŁA�ꌬ�̉Ƃ̑�����������̉Ƃ̑��ւ킽���قǂł���B�Ƃ͉��K�ɂ������݂����Ȃ��Ă���̂ŁA���̂������̗����H�≡���ɂ͂قƂ�Ǔ�������Ȃ��B���̂��̕����ɂ͉����a���A���̑��A�Ƃɑ�����r������֏����Ȃ��B���̂��߁A���Ȃ��Ƃ��T���l����o�邲�݂�����r���������ׂĖ��ӑ��a�ɕ��肱�܂��B���̌��ʁA�X�H���ǂ�Ȃɐ��|���Ă��Ђ���т����ւ̎R�Ɉ��L�������邽�߂ɁA���o�ƚk�o���Q����邾���łȂ��A�Z���̌��N���ɓx�ɂ��т₩�����B���� �����Ă��̏ꍇ�A�Z���͂������ꕔ���ŁA���C������߂Ĉ����A����ł��đ��͊���A���킭�̂��Ă����������߂Ɋ����\�\�Ƃ��ɂ͂��߂��߂��Ă��āA�ꕔ�͒n���ɂ���B�Q��͏�ɂƂڂ����A�܂������Z�ݐS�n�������B������ЂƂ�܂̘m�������ΉƑ��S���̃x�b�h�Ƃ��Ă����A���̏�Œj�������A�V�����Ⴋ���A���ꓹ�f�Ȃ����Q�����Ă���B���͋����|���v���炵����ɓ���Ȃ��B�v�i��p84�j�킽���́A�����ł͂����ЂƂA�������Ɍ��т������ȉӏ������p���邱�Ƃɂ���B�Ⴂ�G���Q���X�̎����������邱�Ƃ��ł���ӏ��ł���B
[�}���`�F�X�^�[���s�X��]��ʂ肩�瑽���̗����H�ɒʂ���A��������ł�����ꂽ�����̒ʘH���E���ɑ���A�����ɓ���ƁA���ɗޗ�̂Ȃ��s���ƁA�s������܂�悲��̂Ȃ��ɓ��肱�ށB���ƂɃA�[�N��ɉ��闠���H�������ł���A�����ɂ͂���܂łɂ킽���������Ȃ��ŁA�������ɂ����Ƃ��X���ȏZ��������B���̂悤�ȗ����H�̂P�ł́A��������ł�����ꂽ�ʘH��������Ă�������̂������ɁA�h�A���Ȃ��֏�������B���̕֏�����₫��߂ĕs���ł����āA������Ƃ�܂����s�����召�ւ̂�ǂ����܂��ʂ炸�ɂ́A�Z���͗����H�ɓ��邱�Ƃ��A�����H����o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����[�f���[�V�B�����猩���낷��] �J����A�[�N�삪����Ă���A���邢�͂ނ����ǂ�ł���B����͋����A�^�����ȁA���L�̂����ŁA���݂����𑽐������ׁA��蕽�R�ȉE�݂̂ق��ɗ�����Ă���B�������V��̂Ƃ��ɂ͉E�݂ɒ������̕s������܂鍕�ΐF�̂ʂ���݂������A���̒ꂩ��͂�����ᏋC���K�X�̂��킪�����A���ʂ���P�S�Ȃ����P�T�t�B�[�g�����鋴�̏�ł����A�ς��������قǂ̂ɂ����������Ă���B���� ���̏��ɂ͏�̍����₵�H�ꂪ����A����ɐ�ɂ́A���F�H��⍜���������A�K�X�����H�ꂪ�����āA��������̔r����r���͂��Ƃ��Ƃ��A�[�N��ɉ^���B�A�[�N��͂��̂ق��ɁA����ɐڑ����鉺���a��֏��̒��g�����B�i��p107�`109�@[�@]�͈��p�ҁj�G���Q���X�́w�C�M���X�ɂ�����J���ҊK���̏�ԁx���M�͂P�W�S�S�`�S�T�N�Ɍ̋��ɂ��ǂ��čs��ꂽ�B
�Y�Ɗv���ɔ����Ă��܂ꂽ�H�Ɠs�s�̗ȏZ�����E�s�s���͖��炩���Ƃ��Ă��A�������ꂾ���ł́A���n�ȃu���W���A���Ƃ������������������q���I�ȓs�s��������ׂ��ł���Ƃ��������Ɏ����I�Ɍ��������̂ł͂Ȃ��B���̕����֍��������E�s�s���������Ȃ������̂́A�u�V�^���s�a �R�����v�ł������B
�R�����̓C���h�̃K���W�X����̕��y�a�ł������Ƃ���邪�A���ꂪ�S���E�I�ȗ��s���������̂́A�P�X���I�ɂȂ��Ă���ł���i��P�����s�P�W�P�V�`�j�B�R�����͐��E��ʂƗȓs�s���ɂ���ďo�������u�P�X���I�^�v�̐��E�I���s�a�Ƃ����悤�B
�p�X�c�[���́u�����̎��R�������ے�v�̗L���ȁg��������t���X�R�h�ɂ������͂P�W�U�Q�N�̂��Ƃł���B�R�b�z�̒Y�s�ۂ̔����͂V�U�N�̂��Ƃ����A�u�a���ہv�Ƃ����T�O������ȗ�����Ɛ�������̂ł���B����ȍ~�͂����ɐV���ȕa���ۂ���������邱�ƂɂȂ�B�܂�A�g�����̕a�C�͔������ɂ���Ĉ����N�������h�Ƃ����o�����l�ނɖK�ꂽ�̂́A���̂���Ȃ̂��B�u�������E�v�̑��݂��m���A���ꂪ���s�a�́u�����v�ƂȂ�ꍇ������Ƃ����F���͉���I�Ȃ��̂ł��������A�u�`���a�v�Ƃ����T�O���̂��̂́A���������ł��邩�Ƃ͓Ɨ��ɁA���ɌÂ����炠�����B
�R�������`���a�ł���Ƃ������Ƃ́A���̕a���ې����m�F�����ȑO����\���m���Ă������A�܂������̍��ł͂��ꂪ��������N�����Ă�����̂ł��邱�Ƃ��A���ꂪ�C���h�ɔ������邱�Ƃ��m�F�����ȑO����A�̌��I�ɒm���Ă����B�����Ă��̃R�������s�͂���߂čL��I�E���E�I�ł��邱�Ƃ���A�R�����h�u�ɂ͎�������łȂ��A���ۓI�ȑ̐����K�v�ł��邱�Ƃ��F������Ă����B���{�ł��A���v�N�ԂɃR���������s���������A���łɗm�������i���撲���j�̋����������M�S�Ɍ��u�̂��Ƃ�͐����Ă����B�i���쏺��w�a�C�̎Љ�j�x�m�g�j�u�b�N�X1971 p195�j���{�̎���I�Ȗh�u�E�D���u���Ȃǂ́A�s�������ɂ���ĉ��āi���ɃC�M���X�j�ɋ��܂�A�����O���̃R�������s�������~�ߓ��Ȃ������ЂƂ̌����ɂȂ��Ă���i�s�������P�p���Ȃ�̂��P�W�X�X�i�����R�Q�j�N�j�B
��ʂɁA�������ɂ��Ă̔F�������������Ɋւ��Ă͕s���ł���B�����ɂ͉��������̖{�����ǂ��ɂ��邩���l���錮������B���̂��Ƃ́A��ɘ_����B
�z���ǂ��r���ɋ��Ȃ����ďL�C�g���b�v�������锭���������āA���݂Ɠ����悤�Ȑ����֏����͂��܂����̂́A�P�W���I���̃����h���ł���B�������A�����֏��������͋��ݎ�莮�ł������B����������e�[���Y��ւ̒��ڂ̔r�����F�߂�ꂽ�̂��P�W�P�T�N�̂��Ƃł���Ƃ����B�����A�r���a�͊J�����ł���A�����╳�A���e�[���Y����������A�q����Ԃ̉��P�ɂ͌��т��Ȃ������B
�P�X���I�ɂ͂���ƁA����g�C���|�������|�e���Y�͕��o�Ƃ����u�ߑ�I�v�ȉ��������V�X�e�����}���ɕ��y�����B���̓_�ł������h���͑��̃��[���b�p�s�s�����[�h���Ă����B�㐅���̕��y������g�C���̕��y���\�ɂ����̂ł���B���������́u�����I�v�ȏ������}���ɐ�������A�Z������̉����̐v���ȓP�����e�ՂɂȂ����B�i���s��r�w�R�����̐��E�j�x������1994 p146�j�܂�A���[���b�p�̋ߑ�I�������̎n�܂�́A�͐�ւ̒��ڂ̉����E�H��r���̕��o�̃V�X�e���ł������B���R�̂��ƂɃe�[���Y��͉�������A�����̎搅�����e�[���Y��ł��������߂ɁA�����h���s���͕֏��E�H��̉����𐅓����Ƃ��Ĉ��ނ��ƂɂȂ�B�w�R�����̐��E�j�x�́A�C���h�ł̐����̌��������t�W�F�C���X�E�W�����\���̒��삩�玟�̂悤�ȂƂ���������Ă���B
�������́A�אl���p�𑫂��Ă��邻�Ńq���Y�[���k���A�̊���������̂��݂āA�ނ�ɂ̓f���J�V�[�Ƃ������̂������Ă���A�ƚ}���B�ł́A�E�G�X�g�~���X�^�[�̃f���P�[�g�Ȏs���̂��Ƃ��A��̂ǂ��\������悢�̂��낤���B�ނ�̓e���Y�͂̐��Ő����ƈ݂��݂����B�Ƃ��낪���ɐ��͏\���̕֏�������������̂����Ƃ���悤�ȕs���Ȓ��g����o���Ă���n�_�Ŏ搅���ꂽ�̂ł���B�i���Op148�j����g�C���ɂ���āA����g�C����������悤�ȗT���ȉƂ́A�Ƃ������Ƃ����A�������ɐ����ȁu���I�ȋ�ԁv���ł����B���̑���ɉ͐삪����A�����̎s�������ꂽ�����������ނ��ƂɂȂ����B�i���ۂɂ́A���������܂Ȃ��Ńr�[�������ސl�����������Ƃ����B���������āA�R�������҂͏��E�q���������Ȃ����B�g�����p�̗��s�͂P�W�S�O�N�ォ��ł���B�g�����p���P�Ȃ�n�D�̗��s�ł͂Ȃ��A�P�X���I�̓s�s�\���ɂ�����邱�Ƃł��������Ƃ̔F���͏d�v�ł���B�w�R�����̐��E�j�x��T�͎Q�ƁB�j
�e�[���Y��ւ̉����E�����̕����́A�ƒ�r�������łȂ��������Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B�K�X��Ђ̔p�t�̃^���������������B��̃G���Q���X�̈��p�ɂ́A�}���`�F�X�^�[�̂��Ƃ����A�₵�H��E���F�H��E�����������E�K�X�����H�ꂪ�������Ă����B�܂�A�����̋ߑ�s�s�ɂ����ẮA�H��̌��݂ƍH��J���҂̈ڏZ�Ƃ������Ɏ��R�����I�ɐ������̂ł���A�H�ꂩ��̔r���Ɛ����r���������荇���ĉ����𗬂ꉺ��A�͐�ɕ�������邱�Ƃ��������Ȃ������̂ł���B
�i���{�ł͉��Ă����{�ɂ��ĉ�����������������߂ɁA�H��p�t���������������邱�Ɓu���������v��O��Ƃ����B�������@��P�O�A�P�Q���ȂǁB
���������u�����������v�Ƃ������̂��̂��̂��A�������͍��ƁE�n���s�����p�ӂ��Č��݂��A���������o������S�����͂���𗘗p����i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�Ƃ����������A������Ă���B����́A����ɉ������͐�ɕ��o���Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ̗��ʂł���B�ƒ�ւ̌����T�[�r�X�Ƃ��Ẳ������Ƃ����ʂƁA��Ƃ��r�o����H��r���̏����������������������邱�Ƃ́A�܂�Ŏ����Ⴄ�B���A���̏펯���ʗp���Ȃ��̂ł���B���̓_�A�̂��ɍďq�����j
�s�s��������̉J���r���̂��߂Ɏ��R�ɂł��Ă��������x���E���a�𗘗p���Ă��������H���A����g�C����H��r���̔r�o�H�ƂȂ�A���̕s��������Ë����ƂȂ�A�y�ǂ���K�̒���ȉ����ǘH�ƂȂ�B�����H���J�������Ë������Ƃ������Ƃ��A�������́u�ߑ㐫�v���݂�ЂƂ̎w�W�ƂȂ�i�����ЂƂ́A�Nj��I���ʼn����������s�����ǂ����ł���j�B
���[�S�[���q�ׂĂ����悤�ɁA�p���ł͂P�X���I�������牺�����͏��X�ɕ��y���Ă��������A�����ڃZ�[�k��֗����̂Ă�_�ł́A�C�M���X�Ɠ������Ƃł���A�R�����̑嗬�s�i1831�j��h�����Ƃ��o���Ȃ������B
G. E. �I�X�}���ɂ��50�N�ォ��̑�K�͂ȃp���s�X�n�̓s�s�����̈�Ƃ��āC�����{�ǂƂƂ��ɉ���400km�ɋy�ԉ����������݂��ꂽ�B�p���̉������́C�����ƉJ���C����ɓ��H��̂��݂����ɂ��r����������ŁC����͍����ł������ƂȂ��Ă���B�܂������r���̂ق��ɁC�㐅���ǁC�K�X�ǂȂǂ̋����n�����݂����˂Ă���C�����ł͕�6m�C����5m�̑�f�ʂ����Ă���B�i����O�Y ���}�ЕS�Ȏ��T�u�������v���ځj�p���s�X�̉����E�J����n�����ɓ������ƂŎs���͂������ɐ����ɂȂ邪�A���ǃZ�[�k��ɕ�������̂ł��邩��A�Z�[�k����������邱�ƂɂȂ�B�Z�[�k��́A�͌��̊J���C�M���X�C�����������邱�ƂɂȂ�B
���Ċe�s�s�ł̉������H�����͂��܂����̂́A�P�X���I�O�����甼�ɂ����Ăł���B�n���u���O���P�W�S�Q�N����A�~�����w���E�x���������T�W�N����A�A�����J�ł͂P�W�O�P�N�Ƀt�B���f���t�B�A�ʼn��������ŏ��ɐݒu����A�T�W�N�Ƀj���[���[�N�̃u���b�N�����n��ɁA�P�N�x��ăV�J�S�s�Ɍ��݂���A�U�O�N�܂łɂ̓A�����J�̎�v�ȂP�Q�s�s�Ō������������ݒu���ꂽ�i����O�Y ���O���j�B��������A���ډ͐�E�Ώ��E�C�։��������������̂ł������B
�����h���ł��p���ł��A�����̕��������ł��邾�������ւ��ւ��A�s�s���痣�����Ƃ��s��ꂽ�B�������A�����K�͂����傷��ɂ�āA������̋��Ƃ�_�ƂɈ��e�����o�Ă���B���̂��߂ɁA�������̖��[�ŁA���炩�������������s���Ă��ꂢ�ɂ������������������Ƃ������Ƃ��s����悤�ɂȂ�B���̉��������̖��͎��߂T.�R�u�������̖{���v�ň������Ƃɂ���B
���[���b�p�̓s�s�̉��Ȃ��Ƃ��������グ���̂ŁA��Y�o�̂��̂悤�ȃo�����X�̂Ƃꂽ�]�����Ō�Ɏ����āA���ق��Ă��炤�B
���[���b�p�̏��s�s���A�s�s�̏ɑ��Ė{�i�I�Ɏ��g�ނ悤�ɂȂ�̂́A�y�X�g�ɂ��r�p����悤�₭��������n�߂Ă���̂��ƂƎv�����A(����)�C�^���A��h�C�c�̓s�s�ł́A�������̃V���{���ł��镬�����A�����������āA���̒��̃V���{���Ƃ��Ȃ��Ă������A���܂⑽���̓s�s�Ő����≺��������A���H�ܑ͕������悤�ɂȂ�A�s�s�������s���A�J�[���X���[�G��}���n�C���ɑ�\�����悤�ȐV�����s�s�v��ɂ��s�s�����݂��ꂽ�B�����ď��Ȃ��Ƃ��P�W���I���ɂ́A�V���g���X�u���O�A�t�����N�t���g�A�}���n�C���Ȃǂ́A�����ȓs�s�ɂȂ��Ă����悤�ł���B(�w�������猩���s�s�xp121)
�M���V���̃A�e�l�A���[���b�p�����s�s�̑����A�����ċߐ��̃p���A�����h���A�}���`�F�X�^�[�A����Ƀj���[���[�N�A�V�J�S�Ȃǂ́A�܂��Ƃɕs���ȓs�s�������B�������A��������Ĉ�ʂ̓s�s�ւƕ��Չ����Ă��܂��ẮA�^��������邨���ꂪ����B�X�y�C����C�^���A�Ȃǒn���C�̏��s�s�A�h�C�c�̃V���g���X�u���N�A�t�����N�t���g�A�}���n�C���A����Ƀx���M�[�̃u�����b�Z���A�I�����_�̃��b�e���_���Ȃǂ́A�͂₭���琴���ȓs�s�Ƃ��Ēm���Ă������Ƃ́A���łɏЉ���Ƃ���ł���B(��p152)
�i5.2.b�j�F���{�̏ꍇ
�u���̓s�E���v�͂�����x�A�b�s�[������m���Ă��邪�A�]�˂����{�ɂ��v��I�Ȗ����n��Ꮌ�n�։��������W���Ă��������߁A���H�E�^�͂����B���Ă����B����]�˂Ȃǂ̑�s�s�����łȂ��A��ʂɍ]�ˊ��̓������^�̏d�v���́A���炽�߂đS���I�ɔF�������K�v������B�������^���ێ�����ɂ́A�͐�ɏ�ɏ\���̐�������A���[�����邱�Ƃ����߂�ꂽ�B����́A�Ώ��E�͐�Ǘ��i�܂�A�����ʊǗ��j�����łȂ��A���ӂ̎R�x�X�т␅�c�E���n�ɑ���S�̓I�Ȗڔz��^�Ǘ����K�v�ł������B
�]�˂ł͌@�������B���Ă���A�@�������Ԃ����܂Ȃ�����߂��炳��㐅�Ƃ̋�ʂ�����������Ă������Ƃ́A�悭�m���Ă���B�����āA���q�̂悤�ɛ��A�͔_�n�֔엿�Ƃ��Ď{�����L�ĂȃV�X�e�����������Ă����̂ŁA���������̂͐����G�r���ƉJ���ł���A�J�����̌@���ł���قǖ�肪�Ȃ������B
�]�˂ł͂P�V���I���̐��ۥ�c���̂���C�q�����Ȃ�тɕ\�̍a�r�q�\���̉����r�Ȃǂ̊Ǘ��ɂ��āC�p�ɂɒ��G���o����Ă���B�܂��\�ʂ�ɖʂ����Ƃ͂R�ڂ������O�Ɂq�J�����̉����r���@��C�ӂ������āC�����̂��̂������Ȃ��悤�ɂƖ����Ă���B���̂悤�ȕ\�̍a�C�\���̉����C�J�����̉����́C�]�˂̒��X�����݂����Ƃ��ɂ��̐ݒu���l����ꂽ�̂ł������B�������ĉ����́C�J�����̉��������������剺���ƏW�߂��āC�x���֔r�����ꂽ�B�܂�A�]�˂ł͓����̓s�s�����̒i�K�͂Ƃ������A��ɂ͒��X�̈��̎����ɔC����`�ŁA�����̊Ǘ����s���Ă����B�܂��A���ꂪ���ۂɗL���ɋ@�\���Ă����B�������A����͍]�˂Ɍ����邱�Ƃł͂Ȃ��A�]�ˊ��̓��{�S�̂ɂ��Ĉ��̑��E���́g�����h���s���Ă������Ƃ́A�����̏؋�������B�i�����ł́A�n�Ӌ���w���������̖ʉe�x�i�����[1998�j����A���̈��p�����Ă����B
�]�˖��{�́C�������������x�z�̂��߂ɏ��߉�����s��ݒu�������C1666�N�i����6�j�ɔp�~���C�Ȍ�͉����̖��܂����ꍇ�ȂǁC���̂��т��Ƃɕ�s��C�����邱�Ƃɂ��Ă���B����Ɍ�ɂȂ�Ɠ���s�������S�������B�����̊Ǘ��͒��X�̕��S�ł��������C�ߐ������ȍ~�ɂȂ�Ɗ֘A���钬�X�������g��������C��p�S�����B�i�ɓ� �D�� ���}�ЕS�Ȏ��T�E���O�j
���ˌ��͔͂N�v�̒�����A�Ꝅ�̋֗߂�A�L���V�^���̋ֈ��Ƃ���������������x���̗̈�ł́A�W���I�Ȍ��͂Ƃ��ċ�����U������̂ł��邪�A���̑㏞�Ƃ�������ɁA���O�̓��퐶���̗̈�ɂ́A��ނ����������邻���Ď����̖R��������߂Ȃǂ��O�Ƃ��āA�\�Ȍ��藧�����邱�Ƃ�������̂ł���B����͗��Ԃ��Ζ��O�̋����c�̂Ɏ����̗̈悪���݂����Ƃ������ƂŁA���̎����͈��̊��K�@�I�����Ƃ��āA���ˌ��͂Ƃ����ǂ��قɐN�Q���邱�Ƃ͋�����ʐ�����ۗL���Ă����B�ip221�j���̓n�Ӌ���̘J��́A�]�ˊ����疾���O���ɗ��������O���l�̎c���������L�E���s�L�Ȃǂ����ƂɁA�ߑ�ȑO�̓��{�́g�ʉe�h���яオ�点�悤�Ƃ������̂ł���B�u���{�ߑ�ɂ��Ē�����������������Ƃ����r�����Ȃ��肢�v�i�{���u���Ƃ����v�j�ɓ˂���������A���̑s�}���������ׂ������ꂽ�P���ڂł��邱�Ƃ͖{���w���������̖ʉe�x���u���{�ߑ�f�`�T�v�Ƒ肳��Ă��邱�Ƃ��番����B���オ���҂����d�v�ȏ����B�j
�����ېV�Ȍ�A����ʂ�̗m�����z�Ȃǂ����{���ꂽ���A���H�e�a����������ꂽ�����ŁA�������~�݂Ƃ������z�ł͂Ȃ������B�s�s�̉����̕K�v�����F�����ꂽ�̂͂P�W�V�V�i�����P�O�j�N�̃R�����̑嗬�s�Ȍ�Ƃ�����B�I�����_�l�Z�t �i. �f����[�P�̈ӌ��ɂ���āC�P�W�W�S�`�W�U�i�����P�V�`�P�X�j�N�����_�c�b�蒬�Ȃǂɕ������������i�J���Ɖƒ뉘������j�����݂����̂����{�̋ߑ㉺�����̍ŏ��Ƃ���A�����K�ⓩ�ǂʼn�����Skm���~�݂��ꂽ�B�܂���������ɉ��l�O���l�����n�ɂ������K����̉��������~�݂��ꂽ�B
��̐_�c�b�蒬�̉������Skm�́A���ꂾ���ŌǗ����Ă�����̂ŁA�����s�̉������Ԍ��݂Ƃ����W�]�������č��ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B���̃A�h�o���[���I�Ȃ��̂ł������B�u�s�s�������v��v�Ƃ����Ă����܂�Ȃ����̂́A�P�W�W�X�i�����Q�Q�j�N�A�v�D�o���g���A���^��ցi�����ȉq���ǒ��E��w�j�������s�ɒ�o�����u�����s�������v�����v�����ł��낤�B(�������A���̌v�揑�͒��H���ꂸ�ɏI������B)
�J���������ɓ����ׂ����ǂ������������Ă���ӏ��B
�����ǂɉJ���𗬓������ނ�Ƃ��́A�����ǂ��ɂ�����ׂ��炸�B�V���ɂ���Ƃ��͏]���čH�������݂̂Ȃ炸�A�~�J�Ȃ����ĉJ���̊ǂɗ���������Ƃ��́A���ʐr�����Ȃ����ė����̑��͑傢�Ɍ����A�����̗��߂��ȂĎ��R�ǂ̒���|�����邱�Ɣ\�킴��̕s�ւ���B�������J���������ǂɗ��������ނ�Ƃ��́A�������ɂ��]���đ��̕��ʂ�������ȂĒ��a�@�E�h�ߖ@�E���@��p�Љ�����r������ɍ���Ȃ�͖ܘ_�A�����ǂ��ɂ��A���c��[�|���v]�@�B��p�ӂ�ɉ��Ă͂��̋@�B�͂𑝂�����ׂ��炸�B�i�w�����s���������v���x���ő吳�R�N �����s�������ǍĔ��s1978 p81 �����͊����J�i�����蕶�A���_�A��Ǔ_�Ȃ��j�v����ɁA�������ɂ���ƊNj���|���v�ꂪ���剻���A�H����傷��B���������̓_�ł��s���ł���A�ƌ����Ă���i�u���@�v�͔��̂悤�ȍL���n�ɉ������A�ؗ������ď�����@�B�t�����X�Ȃǂōs���Ă����j�B�S�N��̊����Ɠy�����ƈ���āA�o���g����͍H���S�z���āA�ł��邾�����ւōςލH�@���l���Ă��āA�����@���Ă��Ă���̂ł���B
���������̗p��������ЂƂ̗��R�Ƃ��āA�������͍~�J�̂��鎞�ƂȂ����Ƃʼn����ǒ��𗬂��鐅�ʂ����ɈقȂ�B�J���̂Ȃ����ʂ̏ꍇ�ł������ǂ����ꂢ�ɂ��Ă������߂ɁA�ǂ̒f�ʂ����`�ɂ���K�v�����邪�A����̐���͓����p�������ނƂ��Ă���B�܂��u�J���������ǂɒ��������ނ�̕��͑��N���ĉq���w�ҔF������Ƃ���ƂȂ�v�Ƃ������Ă���ip82�j�B
�u�q���w�ҁv�����̕��Q��F�����Ă���̂ɉ��Ăŕ������̗̍p�����Ȃ����R�ɐG��A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
���ď��s�{�ɉ����āA�J���������ǂɗ��������ނ�́A���{�~�ނ���ɏo�Â���̂����嫂��A�{�M�ɉ����Ă͉Ɖ��̕~�n�X�H�ƊT�˓������ɍ݂���ȂāA�J���̑����������ǂɗ��������߂��邱�Ɩ���炸�i���Op82�j�B���ď��s�s�łȂ��������ɂ��ɂ����̂����R���s���Ăł��邪�A���{�̏ꍇ�A�J���̑������u�X�H�v�̍a���ɏW�߂��r������Ă���]�O�ʂ�̕������g�p�ł��邱�Ƃ��w�E���悤�Ƃ��Ă���A�Ɨ����ł���B�܂�A�]�ˈȗ��̍a�����]���ʂ�J���r���ɗp������A�������͉�����p�ɂ��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����̂��o���g���E���^�Ắu�������v�̗p�̍����ł������悤�ɓǂ߂�B�{���́A�J���r���p�̊Nj����݂��܂߂Čv�悷�ׂ��ł���̂ɁB���̓_�A���Ɉ����P�W�N��̒����s���Ă̂ق����_�Ƃ��ēO�ꂵ�Ă���B�������A�����Ắu�������v���咣���邪�B
���A�̔r���ɂ��āA�o���g���E���^�Ă��ǂ̂悤�Ȍ����ł������������Ă����B���_�́A�u���A�͈����Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B
���A�͔_�Ƃ̔엿�ɋ�����K�v�i�ɂ��āA�����s���̕��A�͋ߌ��ɔ��o���A���̒l���v�Z����Ƃ��͋��z�Ɏ���ׂ��B�����������ď��s�s�̗�ɕ�ЁA�V�������ǂɗ������Ĕr������̕K�v�������B�i��p82�j���A�̔엿�Ƃ��Ẳ��l���܂������^���Ă��Ȃ��A�ƌ����Ă������낤�B���Ă̂܂˂����ĉ������Ŕr�����Ă��܂����Ƃ����߂Ă���A�Ƃ�������B���̂����ŁA�u����B�v�i����g�C���j�������͑������Ă������Ƃ܂��u���A�������ǂɗ������邱�Ƃ��ւ����v�Ƃ��Ă���B
���A�̔��o�@�ɂ��ẮA�]�ˊ��ȗ��́u���s�ɏ]�v���čs�����A����Ɂu���ǂ�ׂ߁v��悢�A�Ƃ��Ă���B
���A��������Ɖ����ǒ��́u�s���v�������A�Ƃ����S�z�͂Ȃ����Ƃ����̂悤�ɒf�����Ă���B���A�̉����ǔr���ɖ��o���ȓ��{�l�ւ̒�ĂƂ��Ă̔z���ł���B
���A�������ǂɗ���������A���̐v��p�ӂ�Ƃ��́A�q���㌈���ď�Q���ׂ����̂ɂ��炸�B���V[�����݂̂Ȃ炸]���Ă̎���ɒ�����Ɋǒ������̕s���́A���A��������ƔۂƂɊւ�������Ȃ�Ƃ��B�i��p82�j���́A�o���g���E���^�āi���H��R�T�O���~�j�́A�������A���{�Ɉڂ���邱�ƂȂ����̂܂܃^�i�U���V�̗J���ڂɂ����Ă��܂��B�����̒��N�̌��Ăł������u�s��������Ɓv�i�s�s�v�掖�Ɓj���\�Z�s���̒��ōs���Ă����ۂɁu�㐅���D��v���Ƃ�ꉺ�����͌�ɂȂ��Ă������B
�����������瓌���̏㐅�̕s�q���ȏ�Ԃɂ��Ă��C�Â���Ă���A�]�ˈȗ��̖؊ǂɂ�闬�����i�_�c�㐅�Ȃǂ��番������j�ł͉�����J���̗����������������A�`���a�̊������Ƃ��ĉ��ǂ������]�܂�Ă����B��L�o���g���́A�����ɏ㐅���Ă������Ă���A�㐅�������̌�ɉ������ɂ�����Ƃ��ĉ������ꂽ�̂ł���B
�O�����n�����_�ސ쌧���瓌���{�ɕғ������̂��P�W�X�R�i�����Q�U�j�N�̂��Ƃł��邪�A����̍ő�̗��R�́A�����ł��鑽����̊m�ۂł������B�����s�̋ߑ�I�����͂P�W�X�V�i�����R�O�j�N��ڕW�ɍH�����s��ꂽ�B
�R�N�̒x��ŁA�����R�Q�N�P�Q���P�O���A�S�s�ւ̋������J�n����B[�s�s�v����]�V�Q�̐������Ê��̓��H���Ē��肳��A�킸���R�N�̒x��ŁA����̌�ނ��Ȃ����{���ꂽ�̂͂Ȃ��ł��낤���B�ЂƂ��ɓ`���a������˂Ă����_�ɓ��͋��߂��悤�B�����P�X�N�̉āA�����͂Ђǂ��R�����ЂɌ������Ă���A�ۂɉ����ꂽ�������̂܂܉ƒ�ɓ͂��Ă��܂�����܂ł̗������]�ː����͋��|�̓I�ƂȂ�A���������Ă��㐅���ǂ����Ȃ������ɂ͂����Ȃ������B�i���X�ƐM�w�����̓����v��x��g�����ド�C�u�����[1990 p251�j�������A����̂Ȃ��悤�ɂ���K�v�����邪�A�R�b�z�̃R�����۔������P�W�W�R�i�����P�U�j�N�ł���A�������̒i�K�ł́u����܂ł̗������]�ː����͋��|�̓I�ƂȂ�v�Ƃ����Ă��A����̊��o�Ƃ͓����ł͂Ȃ��i�a���ۂ��咣����R�b�z�Ɖq���w���Ђ̃y�b�e���R�[�t�F���̑Ό����������̂��P�W�X�Q�i����25�j�N�P�P���Q���̂��Ƃł���B�y�b�e���R�[�t�F���̓R�b�z�̃R�����۔|�{�t�����݂ق��Č��������A���a���Ȃ������j�B�`���a�Ƃ����T�O�͂���������̂����A���܂������́A�����E���L�Ȃǂ�r������u�q���w�I�\�h�@�v���嗬�̎���ł������i��4.2�߂ŏЉ���u��������v�̐�`���̒��ɁA�u�q���@�v�Ƃ������j�B�㐅�����������ĉq�����d������Ƃ����R�����\�h�@�ɑ��āA�R�b�z�̃��N�`���Ȃǂ�p����Ɖu�I���@���嗬�ƂȂ�u�������璍�˂ցv�̓]�����s����̂́A�吳�����ł���i���X�O�f��p252�j�B
�P�X�O�V�i�����S�O�j�N�A�y�ؔ��̓��叕���������s���������s�̐V�����������v�������܂Ƃ߂��i�u�����s�����v�������v�j�B�����ł́A�o���g���E���^�Ăƍ��{�I�ɈႤ�����Ă���Ă���Ă����B
�����H���̖ړI�́A�K���̐��H�ɗR��āA�J���y�щ��������č������r��ɒ�����ނ邱�ƂȂ��A���̕��s���n�ނ�ɐ悾���}�ĔV���s�O�ɔr����������Ƃ���ɂ���i�w�����s���������v���xp126 �����͊����J�i�����蕶�A���_�A��Ǔ_�Ȃ��j�����ẮA�J���r���Ɋւ��āu�����@�v�i�������j�Ɓu�����@�v�i�������j������Ƃ��A���������̗p���闝�R�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
- �����͍~�J�ʂ������A�J���r���͉����r���Ɠ��l�ɖډ��̋}���ł���B
- ���H���������Ȃ���A�u�d�ԓ����n�߁A�������z�d�b�n�����v�Ȃǂ����łɏc���ɑ����Ă��铹�H�ɁA�J���p�E�����p�̂Q�{�a���݂���͍̂���ł���B
- �������ɂ���������͍a�����P�{�ōς݁A�H��ߌ��ł���B
- �~�J�̂��тɁA��ʂ̉J���ɂ���ĉ����ǂ�����B�ǂ���a�ƂȂ�̂ŁA�����C�U���e�ՂɂȂ�B
�����A���ł��ēx�q�ׂ�悤�ɁA���̒����Ă𓌋��s���̗p���Ĉȍ~�A���{�S���̓s�s�ō��������嗬�ɂȂ��Ă������ƂɂȂ�B�����āA�s�s�����剻���Ă����s���قǁA�J���̍������r�����{���I�ɓ�������N���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�����Ă̕��A�r���ւ̑ԓx�����Ă����B
���A�������ǂɂ��Ĕr������́A���ď��s�s�̊���Ȃ��嫂��A�{�M�ɂ����Ă͕��A�͔_�ƗB��̔엿�ɂ��ĔV�������ɔr�o����̏K���Ȃ��B�R��Ɏ����̐i�^�ɔ��ЁA�Q���Ɖ��̍\�������ߐ���B��݂�����̒��N�����̌X�������嫂��A�{�v��ɉ��Ă͔V�����e������x��Ȃ��B�i��p144�j�����̘_���̓_���g���E���^�ĂƂقƂ�Ǔ����ł���B�u���A�͔_�ƗB��̔엿�v�ł���Ƃ��Ȃ�����A����g�C�����牺�����֗�����镳�A�������Ă����܂�Ȃ��B�������Ă��������Ƃ��Ă̓����Ɏx��͏o�Ȃ��A�Ƌ@�\�I�ɂƂ炦�邾���ŁA�_���Ƃǂ߂Ă���B
�����Ɣ�͂R�R�U�U���~�ŁA����͖����S�O�N�x�̓����s�̑������K�͂̂Q�D�T�{�ł������B���ꂪ���ۂɓ��������͔̂���s�Y�s���̂P�X�P�P�i�����S�S�j�N�U������ŁA���̂Ƃ��������ǎ��������ݒu���ꂽ�B
�o���g���E���^�Ă��^�i�U���V�ɂ����ē����̉��������{���摗��ɂȂ��Ă���ԂɁA�������@�E�����|���@�Ȃǂ��P�X�O�O�i�����R�R�j�N�ɐ������Ă���B���̂���ɁA���{�̋Z�p�҂ɂ��ŏ��̋ߑ�I���������s���Ă���B�����s���̌v��łP�W�X�X�i�����R�Q�j�N�ɒ��H�������s�̍������������ł���B
�����s�������������������̗p���Ă���́C�L���i�P�X�O�W�N���H�j�C���C���É��C�����i��������P�X�P�P�N���H�j�̓s�s�ɑ����Ĕ��فC���R�C���C���R�C��Îᏼ�C�����C�啪�̏��s�s�������������������݂��Ă������B�Ȍ�C��Q�����E���O�̓��{�ł͍��������嗬�ƂȂ����B�i����O�Y ���O�S�Ȏ��T�j���A�L���Ȃǂ̉��������ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��A���������邪�A�킽���͍��͂����Ɏ��L���]�T���Ȃ��B�����̒n���������|�����O���̕ϓ����ǂ������蔲�����̂��ɊW����̂��A����Ƃ����W�Ȃ̂��B�����ɋ������Ă���s�s���A���فC���R�C���C���R�C��Îᏼ�C�����C�啪���牽���ǂ݂Ƃ��̂��A�g����������݂����{�ߑ�n���j�h�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��l�������Ȃ�B������������Ǝ��W���đS�W���s���\�z����悤�Ȃ��Ƃ������A���{�̂������͂�����炢���B�������H���̋���v���W�F�N�g�ɔ�ׂ�ق�̂͂������ōςށB
���{�ōŏ��ɍ��ꂽ����������́A�O�͓�����������ŁA�v�H�͂P�X�Q�Q�i�吳�P�P�j�N�B�u�U���h���@�v���p����ꂽ�B�����A����͂��܂������Ȃ������Ƃ����B�����ł̏�����ғ��̗l�q�����Ă������É�����ł́A���łɐ��E�̎嗬�ƂȂ��Ă����u�������D�@�v��p���Ă̎��p�����s���Ă������B
�������j�̎����i�����s�������ǕҒ��Ȃǁj�⒘��������Â��ǂ�ł݂����A��O�̓��{�ł̉��������ɂ��錤���͉��Ă̐����ɒx��Ȃ��悤�ɁA�M�S�ɍs���Ă����Ƃ����ėǂ��Ǝv���B�������W�̌���ɂ���Z�p�҂�֘A����̑�w�����҂Ȃǂ́A�������Ă����ƌ����邾�낤�B�����̐S�ȓ_�́A��O�̓��{�ł́A��������肪�s�s�v��̏d�v����Ƃ��Ĉʒu�Â����邱�Ƃ͂Ȃ��A�g�]�T������Ύ蓖�Ă���h�Ƃ������x�̈����ŏI�n���Ă����A�Ƃ������Ƃ��낤�B
���q�̂悤�ɁA�]�ˊ��ɂ͓s�s���A���x�O�_����������z�V�X�e���������ɂł��������Ă����B���̃V�X�e���͔_������s�s�֍앨���A�s�s����_���֛��A���Ƃ����Ӗ����z�V�X�e���Ȃ̂ł������B�������̓`���I�Ƃ͖��W�ɁA�����E�吳�E���a�Ə��K�͂Ȃ���ߑ�I�s�s�̉���������������A���A���͐�E�C�֗��o����V�X�e�����ł��Ă������B����ƕ��s����
- �s�s�ւ̐l���W���ɂ���āA���A�r�o�ʂ̑���
- �ߍx�_�n�̑�n��
- ����i����A�哤�����A�ߗӎ_�ΊD�A�����j�̕��y
���̑O���N�\�ŕ\���Ă����B
| �P�X�P�X�i�吳�W�j�N | �����s�͎s�c�̖������ݎ�� |
| �P�X�Q�O�i�吳�X�j�N | �����s�͎s�c�̗L�����ݎ�� |
| �P�X�Q�P�i�吳10�j�N | �u�����֏�����K���v�ŏ����̕֏� |
| �P�X�Q�Q�i�吳11�j�N | �����s�̉������ɐ����֏����t���ƂȂ� |
| �P�X�Q�R�i�吳12�j�N | �k�В��O�ŁA�s�S�E������186km�̉����� |
���̊ԁA�s�s�I�������͏��X�ɍL�����Ă͂����B���ɁA�吳�����珺�a���N�ɂ����Ă̕s�i�C����Ɂu���Ƒ����H���v�ƌĂ�鎖�Ƃ��s��ꂽ�B�i���a�Q�`�V�N�A���Ɣ�R�V�T���~�œ����R�̎�n���45.5km�̉������������Ă���B�Ȃ��A�s�i�C�ɂȂ�Ɖ������H���Ƃ����p�^�[���͐����ς�炸�ɁA�s���Ă���B�j�����A���A���^�ԑ唪�Ԃ≘�q�n�ԁE���q�����Ԃ̍s��́A��Q������܂łȂ��Ȃ�Ȃ������B�i�o�L���[���J�[�́A���s�̍H�������Ƃ������|�ے��̋�S�ɂ���ď��a�Q�V�N�Ɋ��������B���ɁA���ɑς�������S���z�[�X�̍H�v�A���̒����A�ȂNj����[����S�k�́A����܂��悵�w�o�L���[���J�[�͂��炩�����I�x�i���|�t�H1996�j���s�����|�̐�i�s�s�ł��������ƂȂǁA���̖{�ŏ��߂Ēm�����B�j
�����̉����̐��ӂŁA���Ă͂�����ł����������u���q�D�v�̎��Ԃ��A��́w�o�L���[���J�[�͂��炩�����I�x�ɏo�Ă����̂ŏЉ�Ă����B�́A���q�M�ɏ���Ă����l�̒k�b�Ȃ̂����A���������������������L�^�͂߂����ɂȂ��B��l�͖ܘ_�A�u���[�J���[�����̎�̂��Ƃ͘b��������Ȃ�����B
[�쓇�蓔�䉫�A���}�C���Ƃ����悤��]�����̏ꏊ�ɍs���ăo���u���J����ƁA���F���т����S���[�g�����D�̌��ɂÂ���ł���B����Ȃ���r�o����킯�ł�����ˁB���ꂢ�Ƃ��Ȃ�Ƃ��v���܂���ł������A�[����������܂����ˁB�������R���V�̂Ȃ��ɂ���E�W���Ƃ��A�������ɂ����ł��傤���ˁA�����߂��͂��߂Ƃ��Ă��̂��������̒����A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��W�܂��Ă��܂�����B���S�A����H�ƏW�܂��Ă��܂����B�ip148�j�����Ȃ̎���(�w���{�̔p�����x�W�W�C�X�P�C�X�S�C�O�O)�ɂ��A���A�̊C�m�����̗ʁB
| ���� �N�x | 1963 | 70 | 75 | 80 | 85 | 91 | 95 | 97 |
| ��3�^�� | 13,122 | 13,622 | 13,263 | 13,158 | 10,151 | 7,340 | 5,984 | 5,679 |
| ���ݎ�蛝�A���́� | 20.5 | 14.9 | 12.4 | 11.8 | 9.7 | 7.3 | 6.3 | 6.1 |
����́A�o�L���[���J�[�Ȃǂɂ���ċ��ݎ���Ă��镳�A�ɂ��Ă̓��v�ł���(�܂�A�ŏ����牺���ɗ�����鐅��g�C���̕��͊܂܂�Ă��Ȃ�)�B�P�X�X�V(�����X)�N�x�ɂ��ẮA�P���̋��ݎ�葍�ʂ�9��2608 ��3�ł����āA���̂�����6.1�����C�m��������Ă���̂ł���i���{�S���A�ʂ̂Q�D�R�����v�j�B�����̊C�m������5,649 ��3���A�S���g���b�N �P�S�O�O��قǂƂ����̂�����A�Ȃ��Ȃ��������ʂ��B
�l���ł����ƂX�V�N�x�́A���l���P��2614���̂�������g�C���g�p�҂�9953��(78.9��)�A���g�p��(���ݎ��֏��̐l)2661��(21.1��)�B(��\�̍ŐV���X�V�N�ɂȂ��Ă���̂́A�w���{�̔p�����x�̍ŐV���Q�O�O�O�N���ڂ�����������ł���B���Ȃ��Ƃ��X�P�N�ł܂ł͒��҂͌����Ȃ��������Ă��āA���N���s�������悤�ł���B���s�҂͎Вc�@�l�S���s�s���|��c�B�������n�̔��s������ǂ̌����}���قł��������Ă������Ȃ��̂����A���ۂɂ͂������B�Q�O�O�O�N�ł𓌋��s�}���ى��f�����ł������Ă��A�R�X�s��s���̐}���ْ��킸���S�ق����q�b�Ƃ��Ȃ��B�Q�O�O�O�N�P�Q���̓��t�̂���Q�O�O�O�N�ł́u�܂������v�ɂ�
�����Ȃł́u�p�����������Ǝ��Ԓ����v�N���{���A���̌��ʂ����\���Ă���܂����A���̉���łɓ�����A����u�p���������v�Ƃ������ׂ����̂��A���́u���{�̔p�����v�ł��B�Ƃ��Ă���B�ɂ�������炸�A�X�Q�N�ȍ~�͖��N���s�ł͂Ȃ��A���ۂ̗��z������������ł���B���̂悤�ɁA�킽���̂悤�ȍݖ�̎҂������J���Ȃ̃f�[�^�ɃA�N�Z�X����͓̂���B�u�p�����������Ǝ��Ԓ����v�������J���Ȃ̃T�C�g�Ō������Ă��A��������Ȃ��B
�����܂ł��Ȃ��A�u���{�̔p�����v�͂킪���̔p���������̎��Ԃ��ꗗ���邱�Ƃ̏o����B��̊��s���ł���A���̌p���I�Ȋ��s�͊e���ʂ��狭���]�܂�Ă���Ƃ���ł��B
���ݏȂ��ɂ��鉺�����W�ł́A�S���I�u�����v�͂����炭���݂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B )
�]�˕���S�N�Ԃ̂������A���Ăɔ͂��Ƃ����s�s�������V�X�e���Ɠ`���I�ț��A�z�V�X�e���Ƃ��������Ă����A�ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����āA�����s���ȍ~�̓s�s�������V�X�e�����S�������Ă����̂́g���ẴV�X�e�����ǂ̂悤�ɓ��{�Ɉړ����邩�h�ł����āA�������Ă����`���I�ț��A�z�V�X�e������w���Ƃ����ϓ_�͂قƂ�nj����Ȃ��B
�����A�`���I�ț��A�z�V�X�e���̕��͐L�k���݂ȂƂ��낪�����āA��Q�����E���̍���Ȏ����ɂ͎��ƍ؉��ɃC����������肷��ۂɂ͌��悤���܂˂Ŕ싂�݂������肵���B�I���̐H�Ɠ��ɁA���w�엿����������Ȃ�����ɂ͛��A�����Ă͂₳�ꂽ�肵���B
���łɁA�����ɋL���Ă������A�����ł͑�Q�����̏I��育��ɂ͔R������g�����s�����āA�C�m�����̉��q�D���o�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B��P�̊댯���������B�C�m�����̋֎~���P�X�S�S�N�T���B�s�������f�����B�����s�������d�ԁE�����d�ԂɈ˗����āA�d�Ԃœs���̕��A���x�O�܂ŗA�����A���H�e�̔역����_�������ݎ���Ĕ��֎{���Ƃ������A�A�������肾�����B�S�S�N�U������n�܂�A�������T�R�N�R���܂ŁA�������T�T�N�R���܂ő������B���É��ł����S�����l�̂��Ƃ����{���Ă���B(�l�b�g��ł����S�̉������(���A�̓S���A��)���ڂ����B�܂��A���іw���{���A��茹���l�x�ɁA�����s�̏ꍇ�̒����V�����a�T�T�N�P�Q���Q�O�����̓��W����̈��p�������āA�����[���B)
�����{�����������݂ɖ{�i�I�ɏ��o���̂́A�o�ς̍��x�����i�K�i�P�X�U�O�N��j�Ɏ����Ă���ł���B����Ƃ��̎����ɂ������āA�H��r���E�ƒ�r���̉͐�ւ̃^�������ɂ���đS���I�ɉ͐�̉������}���ɐi�s���A���������݁E�p�������̕K�v�����}���ł��邱�Ƃ��F�������悤�ɂȂ����B��P�������������T���N�v�����͂��܂�̂��P�X�U�R�i���a�R�W�j�N�ł���B���̔N���A�d�v�ȉ���ƍl�������B
�����ېV�����P�������������T���N�v��܂łƁA����ȍ~�̓��{�o�ς̍��x�����i�K�ƂƂ��ɐi�W������{�̉������̖��Ƃ͋�ʂ��čl�������������B���̑O���E����̕����͂킽�������Ɏv��������Ɖ����ł���B���Ȃ킿
�O���i�����ېV�`��Q�����E����j�F����ɑ��āA
�����㔼�ɂȂ��ē��{�e�n�ɂ����āA�s�s���S�������ł��J���E���A�r���Ƃ����Œ���̓s�s�@�\�����o�����Ƃ��ĉ��������݂��s��ꂽ�B�R�����Ђ����������ƂȂ����ꍇ�������B�㐅�����˂ɗD�悳��A�摗�肪��́A�I�}�P�̓s�s�v��̂悤�Ȃ��̂ł������B
���{�̋ߑ㉻�̗��j�̂����ɂӂ��߂čl����ׂ��ł���B
����i���x�������`���݁j�F�O���̋ߑ㉻�̒i�K�ł́A���������݂͓s�s���݂ɂ�����傽����ł���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ������A���邢�́A��ɂ���Ă����B����̌���̖��Ƃ��ẮA����y�؍H���̑�g�̂Ȃ��ŁA������y�����̉a�H�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ���ԑ傫���B�����A�F�䏃�E�������q�Ȃǂ̏����̊w�҂̓w�́A���{�e�n�ɋN�������Z���^���A���{�o�ς̎����Ȃǂɂ���āA��������������x�̋O���C�����s���Ă����B���������A���P�̖ʂ����邱�Ƃ͔F�߂Ȃ�������Ȃ��B
���{�̓y�؊������u�傫�����Ƃ͂������Ƃ��v�Ƃ������{�o�ς̔��ǂɔ����ĉ����������Ӑ}�I�ɂ˂��Ȃ����̂ƁA���Q��������̐i�W���d�Ȃ��Ă�������ł���B
�͐��ݍH���E�_�����݁E�C�݂̌�ݍH���▄�ߗ��āA�������H�E�V�����̌��݁A�s�s�̓O��ܑ�(����Љ�)�ȂǂƘA�����Ă���B
�����A�킽�������{�̋ߑ�|����̉������j�����Ă��Ă����Ƃ������邱�Ƃ́A�������͂����̔r���s�ׂɒ��ڂȂ��鎄�I�ɓ_����n�܂���ł���ɂ�������炸�A�s���̎�̐������S�ɍ������ɂ���A�u���㗊��v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃ��B�����̐S�I�p�����u���㗊��v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B���Ԃ��Č����A�������̂��Ƃ����S�ȃu���b�N�E�{�b�N�X�ɂ��āA�u����C���v�ɂ��Ă��܂��Ă���B���̏d�v�ȕ���(�l�Ԑ����̏d�v�ȕ���)���A���̓I�ɐ����邱�ƂŎ����Ă�����̂���������̂��낤�ȁA�Ǝv���B��킭�́A�킪���I�ɓ_�ɔ����邱�̕���Ɏ�̓I�Ȍ��ʂ��������āA�̂т̂тƐ����������̂��B
�������A���Ƃ͉����������̖��ł͂Ȃ��A�Ƃ����ׂ����B�ߑ���{�ɂ����Ă͓s�s���݂��̂��̂��u�O���v�ɂ͂��܂�A���킽�������u�������v�i�X���O�̏����̑薼�A�P�X�P�O�N�j�𑱂�����̂ł������B���̒��ŁA�s���̎��I�����ɑ�����������̓I�s�s����Ƃ����ϓ_����u�ߑ���{�̓s�s�v��v�����������Ƃ��K�v���Ǝv���B�u����v�Ƒ��ƂƑ�w�����ɂ���A�s�s�v�����点�Ȃ��ŁB
�ߑ���{�̓s�s�v��i�n���s�s�v��A����ѓs�s�v��j�j�����n�����ƁA���̉��ߖ@�̂Ȃ��Łu�ߑ���{�̉��������v�������Ƃ����̂��A�{���낤�Ǝv���B
�����܂ŁA���{�ߑ�|����̉������j���ȒP�Ɍ��Ă������A�����r���𒆐S�ɂ��Ă����B�ȉ��A�������̂ӂ��ڂ̏d�v�ȋ@�\�ł����J���r���ɂ��āA�������G��Ă��������B���{�ł͍~�J�ʂ��������A�r�����͂���߂ďd�v�ȉ����@�\�Ȃ̂ł���B
�����̏ꍇ���������Ă����B����(�]��)�͗�����E�r��Ȃǂ̐��n�̉�����ɔ��B��������ɂł����s�s�ł���A�����A�͐�ɂ͌b�܂�Ă����B���̂��Ƃ͂܂��A�^���������������Ƃ��Ӗ����Ă���A�]�ˎ���ȑO���玡���H�����s���Ă����B�]�ˎ���ɂ́u�����쓌�J�A�r�쐼�J�v�Ƃ�����A��H�����s��ꂽ���Ƃ͗L���ł���B���Ƃ��Ɨ���Ƃ�(���݂�)�����p�ɗ��ꍞ��ł����̂��A������𓌂ֈڂ��Ē��q�֎����Ă����A�r��͂��Ƃ̓��Ԑ�ɂ��ւ����B����ɂ���āA�^����h�������łȂ��A���^�̕ւ��v�����B
[����]�s������ыߍx�𗬂��͐�͍r��A���삨��э]�ː�̂R����͂��߂Ƃ��A�召�U�R����A�������W���V�U�R�O���[�g�������āA��ʏ�d�v�Ȉʒu�����߂Ă������łȂ��A�J���͂��̉͐�Ɏ��R�ɗ��ꂱ�ݕ�������Ă����B�ڍ���A�Ð�A�_�c��A������Ȃǂ݂͂Ȏs���𗬂��v�Ȕr���H�ɂȂ��Ă����B(�w�����S�N�j�x��R�� p709)������]�ː��������̋��͓��B�Ȃ��A���c��͍r��̉�����������(�]�ˎ���͑��ƌ����Ă���)�A���r��͂P�X�R�O�i���a�T�j�N�Ɋ��������r������H�̂��ƁB
�w�����S�N�j�x�͖����Q�O�N��͂��߁A�����̌����͉����X�U�Okm�ƌ��ς����A���̍��E�ɍa���̂Ȃ����������������Ƃ��Ă���B
��J���~��A�������r���H�ɕς��A�����܂����͓D�^�����邱�Ƃ�����A���H���ܑ�����Ȃ��������Ƃ������āA�����̓��H�ɂʂ���݂̑��������̂����̉��������������Ă��Ȃ��������߂ł���A�a���ɂ͉���������ĉ�┈�̔������ƂȂ�A�q���ォ������C�ł��Ȃ����ł������̂ł���B�܂����H����������Ɨ����̍a���̉������T���ɗ��p���邱�Ƃ������āA�L�C���@�����悤�ȏꍇ���������̂ł���B(��p709)��ł�����ƐG�ꂽ�r������H�́A�P�X�P�O(�����S�R)�N�W���̑�^���̂��߂ɍ�ʌ����瓌���s������̂����v�����Q���o�āA�����H���܂������V���Ɍ@�킵�č��Ƃ�����H�����s���Ăł������̂ł���B���݂̊╣����(�����s�k��)������c�삪�n�܂��Ă��邪�A���̑�H���܂ł͂��ꂪ�{���ł������B

�r������H�̍H���́A�����Ƃ��Ă͔��Ɏv����������H���ł��������Ƃ��w�E���Ă��������B�����ʐςP�O�X�W�����E�ړ]�ː��P�R�O�O�˂ŁA���C���̌@��@�����Ă���B���͓̉����ł����i�K�Ő������A���֑D�Ő�������Ɍ@�����B����͐l�͗��肾�����y�؍H���ɁA�킪���ōŏ��ɋ@�B�͂���������I�Ȃ��̂ł���B�ł��������H�͕��T�O�O���Ŗ�Q�Pkm�ł������B���܍s���Ă݂�ƕ����邪�A�l���͐�Ǝv���Ȃ��L���쌴���Ƃ��Ă��邱�Ƃɋ����B�������A�^�����̗V���n�Ƃ��ĂȂ̂����A���݂̓S���t���O�����h�Ƃ��ė��p����Ă���B
���̍H���̐ӔC�ҁE�R�m[������]�͓����ӎO�剺�ŁA�p�i�}�^�͌��݂ɂ��������������l�̓��{�l�Z�t�ł���B�R�̒m���ƌo���������Ă͂��߂Ă��̉���I��H�����\�������̂��낤�B���C���̌@��@�B�̍ŏ��́A�X�G�Y�^�͊J��H���̌㔼�i�P�W�U�O�N��㔼�j���Ƃ����B�������p�i�}�^�͂ł��g���Ă���B�����ʐϖ�P�Pkm2�͌��݂̏����߂̋�̖ʐςɑ�������B�n�c��P�Skm2�A�䓌��P�Okm2�B
�R�m�͌�ɓ����Z��(�����Ȃ̋Z�p�����̃g�b�v)�A���{�y�؊w���ȂǂɏA���Ă��邪�A���̐�����簂Ȑl���ԓx�͎���m��l�Ɋ�����^������̂ł������悤���B�r������H�̍H���̓r���̂P�X�Q�P(�吳�P�O)�N�ɋ@�B�w��ɏ����ꂽ�u���ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
[�r������H��]�H����͓s���Q�X�S�T���~�v�邱�ƂɂȂ�܂��B�Q�X�S�T���~�Ƃ����Ƒ啪�傫�ȋ��̂悤�Ɏv���܂����A�R�͈��|������R�Q�O�O���~�|����̂ł���܂��B�R�͂��������|�A����ōr��̐��Q���������Ƃ��ł���̂ł���܂��B�r��̐��Q�Ƃ������͖̂����S�O�N�ƂS�R�N�ʂ̍^���ł́A�����Əォ��Z�����ׂ܂��ƂT�U�������Z�����Ă��܂��̂ł��B�i�����j�r��㉺���łU�R�O�O���~�ʊ|����܂����A�܂��R�͂Q�|�ł��ꂪ�o�����ł���܂��B��������ƕS������������݂̂Ȃ炸�A�^�����o��Ƃ����l�����ɂ܂����A���������悤�Ȃ��Ƃ��v���܂��ƁA���ǂ��͏I�n�D�܂݂�ɂȂ��Ďd�������Ă���܂����A���݂��ɂ�����������s�ւ�E��Ŏd�������Ă����Ǝv���āA���������D���@���Ă���܂��B(����N�Y�w�]�` �Z�t�E�R�m�̐��U�x�u�k��1994 p152)�R�m�́w�]�`�x��ǂ�ŋ������Ƃ́A�R����H�����Ȃ��Ƃ��Ă��̋L�O��E���Ɏ����̖��O���قƂ�ǎc���Ȃ��������Ƃł���B�r������H�̏ꍇ�́u����i���]���g�A�J�g�����q�^���䓙�m���ԃ��L���Z���׃j�v�Ƃ��āA�u�r����C�H���j�]�w���҃j�˃e�v�Ƃ��Ă���B(�R�m�ɂ��ẮA���Ɂw�ʐ^�W �R�m�^�㐢�ւ̈�Y�x�i�R�C��1994�j������B)
�r������H�̎v����������H�����l����ƁA�����|�吳���̐��{�E�����s�̎w���҂����̌����ƃX�P�[�������߂ĔF���������B�����͖����N�Ԃɂ͓����ɉ������H���������A����Ȍ���吳���珺�a��O���ɂ͗\�Z���P�`��Ȃ���A�Œ���̉��������݂������Ȃ������B����́A��P�ɕx�������̌R���D�捑�ƂƂ��Ė����ɗ\�Z���Ȃ��������ƁA��Q�ɂ�����������A��엿�Ƃ��ė��p����`�������������ƁA��R�ɍ��u���W�v�̓s�s�����Ȃ��������ƁA�Ȃǂ����̗��R�Ƃ��ďグ�邱�Ƃ��ł��悤�B�����S�R�N�̑吅�Q�́i��Z���ʂ̐l�́u�S�R�����イ����N�̑吅�v�ƌ����Ă����炵���j�A����������т͈�ʂ̓D���ɂȂ�A���̏H�͑D�Œʍs���邱�Ƃ������A���������Ēn�ʂ��������̂��P�Q���������Ƃ����B�܂�A�������H���͐摗��𑱂��Ă������{�E�����s�̎w���҂������A�u���̋K�͂̐��Q������ł��Ȃ��Ǝ�s�Ƃ��Ă̓����������ł��Ȃ��v�Ƃ������f�����Ď��{�����A�K���̋���H���ł������̂ł͂Ȃ����B �i�r��Ɋւ�����́A�r��u���j�����v�������߂ł��B�j
��ʘ_�Ƃ��ẮA�s�s����̔r���ɂ͎��̂Q�̉ۑ肪����B
- �J���̔r���B����͍a���ɂ���ĉ͐�֓����Ƃ������R�I�V�X�e���Ɏn�܂�B
- �n�����̔r���B�Ꮌ�n�т̔r���▄�ߗ��Ēn�̔r���ȂǁB
���������āA�s�s��������̉J���r����P�������������̉ۑ�Ƃ��Ĉ����悤�Ƃ�����A�g�������̋��剻�h�z���Ă�������������A�������A���̋��剻�ɂ͌��x���Ȃ��B���̂��Ƃ́A����y�؍H�����~�����Ă��������Ȃ��y�؊����|�y���ƊE�ɂƂ��ẮA����Ă��Ȃ����Ƃł���B
�������̋��剻�́A���������g���H�����h�ƂȂ邱�Ƃ��Ӗ�����B���������т̌���ɂ��鉺�����ł��邩��g�ŋ��H�����h�ł���B�Ƃ���ŁA���������g�ŋ��H�����h�ł����āA���ڍ���l�͒N�����Ȃ��B�����͎����ɋ���\�Z�����Ċ������B���Ƃ������y�؊֘A��Ƃ́A�����B�Z���͗��h�ȉ��������ł��邱�ƂŁA�����B���̍\�������邽�߂ɁA�������W�҂͖����u�ł��邾�������������̖��Ƃ��Ĉ���������v�B�{���͓s�s�v��⍑�y�v��S�̂̌�������K�v�Ƃ�����ł���̂ł����Ă��B
�ɒ[�܂ł������������H���́g�����`�h�́u���扺�����v�Ō��o�����B�n�������c�̂�P�ʂɂ��Đݒu�����u�����������v�ɂ������āA�����̎s�����ɂ܂������Đݒu����鉺�����̂��Ƃł���B�s�X�n�́u���W�v�������痣��āA����ȊNj���ݒu����K�v��������B����ɂ�����_�́A��5.3.c�����扺�����ň����B
���ܓ����ōs���Ă��鉺�����W�̋���H���́A���J�̍ۂ̐Z���E�×��h�~�Ƃ��āu�n���V���r�v���݂ł���B���H�E��V�����̒n���ɓ��a�P�Q.�T���Ƃ����S�K���ăr���قǂ̊Ǐ��Ԃ�����A�V���������閭������E�P������E�_�c�삪���ӂꂻ���ɂȂ�����A�n���u�V���r�v�֓������Ƃ���v��B�����̃T�C�g�_�c��E���� �n�����ߒr�����Ă��������B���ꂪ�A������x�̔×��h�~�ɂȂ邱�Ƃ͊m�����낤���A���S�łȂ����Ƃ������炩�B�q�[�g�A�C�����h�����������̉ĂŁA���ĂȂ��������W�����J�����邩������Ȃ��B�䂦�ɁA���̍H�������������A���̎��ͥ������Ɓg�ŋ��H�����h�͐���Ɋ������āA�Ƃǂ܂邱�Ƃ͂Ȃ��B
�킽���̐g�߂ɋN���������Q�Ȃ̂ŁA���X�����L�����Ă���P�X�X�X�N�V���Q�P���́u���n�V�h���Q�v�ł́A�P�O�O�o�ȏ�̉J���P���Ԃقǂ̊Ԃɒ����k��������n��]�Óc�n��̋����͈͂ɍ~�����B�s�s�^���Q�̔�Ў҂ɂȂ����Ƃ����D�ꂽ���|�[�g������B�u�s�s�^���Q�v�Ƃ������̂��d�v���Ǝv���B�]���^�̐��Q�́g��̕����琅������h�̂ł��邪�A�s�s�^���Q�́A���Ɓg���C��̉��������琅���t�����Ă���h�̂��B
��J�̏ꍇ�A����������Ȃ������́A���������ɉ͐�ɕ������邵���Ȃ��i�͐�ւ̏o�����u�J���f���v�Ƃ����j�B�������̏ꍇ�ɂ́A�������̕��ցE�������E�H��p�t�E�S�~�Ȃǂ����ډ͐�ɕ��o����邱�ƂɂȂ�B�������A�����J���́A�����E���H�Ȃǂɑ͐ς��Ă������o�Ȃlj��������E���D���܂�����ł���i����͕������ł������j�B�������̏ꍇ�́A���ʂ̏��Ȃ��ʏ펞�ɉ����ǂŒ◯���Ă��������͐ς�����C�ɉ��������Ă���B�䂦�ɏ����J���́A��ʂȁ^�Z����������C�ɗ��o����\�����悭�A������Ȃ���(�I�[�o�[�t���[��)�́A�s�s�͐�ւ��̂܂ܕ�������(��������Ȃ���^�ł��Ȃ���A�������ɐZ���ƂȂ�)�B��J�̎��ɖ������������͐�ɕ�������A����͍������s�s�����������I�ɕ������ލ���Ȗ���Ȃ̂ł���B�����āA���Ƃɏ����J���͉��Ȃ��A�Ƃ����킯���B
���́A���y��ʏȃT�C�g���u�������������̉��P�v����̈��p�i�����͈��p�ҁj�ł��邪�A�킸���Q�C�R mm �̍~�J�ŃI�[�o�[�t���[��������Ƃ����̂ɂ́A�����B
�����P�S�i2002�j�N�x�����݂ŁA���������g���Ă���̂́A�s�s���̖�P���E������ʐςŖ�Q���E�����l���Ŗ�Q���ł���Ƃ����i��L�T�C�g�ɂ͂����ƍׂ���������A�����J�����͐�Ɂu���֑咰�ہv���ǂꂭ�炢�f�o���Ă��邩�A�Ȃǂ������Ă���B��������Ă���ƁA�J�̍~��n�߂ɂ͓s�s�͐�ɂ͋߂Â��Ȃ����������A�Ǝv���Ă����j�B
- �����ƉJ����̊ǂ���Ŕr�����鍇�����������́A�������牺���������Ă����s�s�𒆐S�ɍ̗p���Ă��܂��B���a40�N��㔼�ȍ~�A�V�K�ɒ��肷��s�����ł͕��������������̗p���Ă��܂��B
- �J�V���ɂ́A��2�`3mm/h�̍~�J�ō��������������疢�������������o���邽�߁A���O�q����A�����ۑS��ɂ߂Ė��ł��B�����������̓f���i�J���f�j �͑S���Ŗ�3,000�ӏ��ł��B���̂��������s�ł́A��800�ӏ��ł��B
- �������������̉��P�ɕK�v�Ȏ{�݂̍\���y�ѕ����������K�肷��ȂǁA�������@�{�s�߂��������܂����i����16�N4��1���{�s�j�B
- ���P�v������肵�A�����Ƃ��ĂP�O�N�ȓ��ɑ�����{���܂��B
���������͍������̕������オ��Ƃ��Ă��A�J�ʂ̑������{�̓s�s�ł͕������̕����K���Ă���A��Ƀo���g���E���^�āi�����Q�Q�N�j�́u�J���������ǂɒ��������ނ�̕��͑��N���ĉq���w�ҔF������Ƃ���ƂȂ�v���o���Ă������悤�ɁA���_�I�ɂ���������������Ă��邱�Ƃ́A�P�X���I����̒���ł������B��Ɍ���悤�ɁA���{�̍s��������������̂��u���a�S�O�N��㔼�ȍ~�v�i�P�X�V�O�N�ȍ~�j�Ȃ̂ł���B
�s�s�̔r�����ŁA�����ЂƂ����Ă��������̂��ܑ��̂��Ƃł���B�y�̕\�ʂ�~�E�R���N���[�g�E�A�X�t�@���g�Ȃǂ̌ł��핢�w�ŕ����Ă��܂����Ƃ��B
���H���ܑ������O�́A�J���Ƃɓ����ʂ���݂ƂȂ�A�����܂肪�ł������̂ł���B���J�ƂȂ�A�^���̉\�����������B�^���Ƃ܂Ō���Ȃ��Ă��u�J���~��Ǝq���̒ʊw���o���Ȃ������v�i�w���������j�P�Q �����сxp363�j�Ƃ����悤�ȓ��H�͒������Ȃ������B���������āA���H�ɔr���a��݂��A�������ɓ����Ȃǂ́u�Z�����v���K�v�ɂȂ����B
���ߗ��Ēn�E�Ꮌ�n�тɓs�s������ꍇ�A�n�����ʂ������邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ́A�P�X�O�V�i�����S�O�j�N�̒����s���̓����s�������Ăɂ����������Ƃ����q�����B
���̌�A�g���b�N��o�X���D�������������ɑ���̂ŁA���H���r��A�J���~��Ɛ����܂肪�ł��Ђǂ��D�͂˂����ʂ̂��Ƃ������i�g���b�N�E�o�X���A��O�̓��{�ł͌R�p�̂��ߓ��ʕی�������Ă����j�B(�킽���͏I���܂��Ȃ����w�Z�֓��w�������ゾ���A�e����g�������h������������ꂽ���̂ł���A�g�n�l�̏オ��Ȃ��悤�ɕ����Ȃ����h�ƁB���ʂ𗚂��Ăʂ���ݓ�������āA�n�l���グ�Ȃ��̂͐_�Ƃɓ����������B����������o�X�E�g���b�N�E��p�ԂȂǂ�����Ă���ƁA�n�l���|�����Ȃ��悤�ɎP�Ŕ������肵���B)
���{�̓s�s�ł͏�V���̑��a�ȗ��̌Â��`���������āA�]�˂ł��r���a�����I�w���ɂ���č���Ă������Ƃ͒m���Ă���B�������A�����ȑO�ɂ͔n�Ԃ��g���邱�Ƃ͂Ȃ��A�M���������g�p�������Ԃ͓s����o�邱�Ƃ͂Ȃ������B�ߋE���̈ꕔ�ł͍]�ˊ��ɂ́A���Ԃ��ĂȂǂ̉^���Ɏg�p����A����~���ĕ⋭�������H���ݒu���ꂽ�Ƃ����i��Á|���s�|�����́g���ԉ҂��h�j�B
���{�ł̉הn�ԁE�捇�n�Ԃ̑����͖����P�O�N��ɓ����Ă���ŁA���H�̋ߑ㉻�i�ӐΓ��H�E�ܑ����H�A�����̊g���A�}�J�[�u�E�}��Ȃǂ̐����A�����E�g���l���j�͒x�ꂽ�B�A�X�t�@���g�ܑ�����K�͂ɂ͂��܂�̂͊֓���k�Ёi1923�j�Ȍ�̂��ƂŁA�����Ԍ�ʂ̕��y���{�i�����������҂��āA�{�i�I�ȕܑ����H���݂��͂��܂�B
���H�ܑ̕��́A�����Ԃ𒆐S�I�ȗA����i�Ƃ���Љ�i�g����Љ��h�j�Ɛ[����������Ă���B�i����Љ�́A�Ζ�������^�Љ�̊�\���̂ЂƂł���B�������E�����́u�A���v���L�[�E���[�h�Ƃ���Љ�ł���B����͎����ԎY�ƁE�Ζ��ƊE�ɂƂ��āA�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Љ���ł���B���H���݂œy���ƊE�������̂͂�������B
�D���E�����ԁE�q��@�ɂ��A���́A���ĂȂ������悤�ȉ������E�����ȑ�ʂ����̂̈ړ����������A����ɂ���āA�͂��߂āA��ʐ��Y�E��ʏ���\�ƂȂ����B���Y�n�Ə���n����������Ă��邱�ƁA���E���܂����Ŋe�n���猴�������Y�n�֏W�܂邱�ƁB�A�����Ζ�������^�Љ�̃L�[�E���[�h�ł��邱�Ƃ́A�������Ă������l������B�j
���H�ܑ̕����͂��܂�ƁA�s�s�ł͘H�n�̋��A�~�n�̂��ׂĂ̒n�\��ܑ����Ă��܂��Ƃ���܂ŁA�ɒ[�ɑ���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�g�ܑ����Ă����ΎG���������Ȃ��h�A�g���Ɨp�Ԃ��~�߂���h�A�g�ʂ���݂̐S�z���Ȃ��h�ȂǂƂ������z�ł���B�ܑ������O�ꂵ�āA�~�����J�̑啔�����������ɗ��ꍞ�ނ悤�ɂȂ�Ɓi�~�J�̂����������������֓����ĉ����ƂȂ邩���u�J���������v�Ƃ����j�A��ʂ̉J���ɑ�����ʂȑK�v�ɂȂ�B�����Ȃǂ̂悤�ɓO�ꂵ�ĕܑ����Ɖ������ĂĂ��܂��Ă���s�s�́A�J�����������P�O�O���߂��Ȃ�B
�J���������������邽�߂ɁA�Z���ܑ����͂��߂��Ă��邪�ꕔ�ɂƂǂ܂��Ă���B��n���̉J���Z���ݔ��ɂ��ẮA���z��@�ł͂Ȃɂ��K�肵�Ă��Ȃ��̂������ł���B�����ł͋�̃��x���Łu�w���E�����v���s���Ă��邪�A�����͂��Ȃ��A�������Ԃł���炵���B�킽���Ȃǂ́A��n���ܑ��͂��ׂĐZ���ܑ����`���Â���悤�ɂ��ׂ����Ǝv���Ă���B
�����͂��̐��삪�L���A���_�ł͕��A�|�������Ƃ���������ŁA�ˌ����Ă����ɂƂǂ߂�B�@�芄��E�����͐�Ƃ����n�\�𗬂�Ă���͂��̐����A�n���̊Nj��̂Ȃ��֓����ď�����܂ŗ����A��������B���́u�l�H���v��������O���ƍl�����Ă��錻�������ł���B���������H�n�̍a�������Ă�����������ǂ����Ƃ�^���ɍl�������B
�Ⴆ�A���̈��p�͓����s�����ǂ̃T�C�g����ł��邪�A�ւ炵���ɏ����Ă���̂��A�Ȃ����Ȃ��B
�_�c��̖������ӂł͂X���ȏオ�A�܂��A���c��̗��������ӂł͂V���ȏオ�����̏������ł��B�������̕��y�ɂ�胊�o�[�T�C�h�͍���s���̂������̏�ƂȂ��Ă��܂��B�������̉��𗬂����c��̐��̂V���ȏオ�A���������ǂ��Ă��Ă��邱�Ƃ��A�u�������s�s�����̂�������v�Ɨ�������K�v������B�Í��̉����ǂ̒����Ă�����c��V���̐��́A�����̓s�s�����́u�����r�o����v�Ƃ����d�v�ȁE�K�R�I�Ȏd����S���Ă���̂ł��邪�A���̐l�H�I�Ȑ����́A���R���Ԍn�̐[���ȋ]���̏�ɍ���Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂����Ȃ��B�������A���̐����������ǂʼn^��ł������������̍ŏI�i�K�ŁA���ʂ̐Ζ����g�����u�R�ď����v���s���Ă���̂�����ł���i���̓_�A��q�j�B
�F�䏃�́w���Q���_�x�̂Ȃ��ŁA�u���݂̉q���H�w�̂R���Z�p�v�𐔂��グ�āA
|
�R���w�E������i�w���{ ���Q���_�x���I���[1988 p243�j�B
�Έ�M��́u�������ƒP�Ə�������Ă��܂������Ƃ��A���{�̉��������j�̂Q�剘�_�ł����v�ƌ����Ă���i�Έ�M�E�R�c���A�w���v���x�����o��1994�j�B���̂悤�ɍ������ɂ͂��܂��܂Ȗ����܂�ł���B�i�Έ�M��̂��̖{�́A��������肪�P�Ȃ�����ł͂Ȃ����{�������Ƃ̓������܂��ł��邱�Ƃ��͂��߂ċ����Ă��ꂽ�A�킽���ɂƂ��Ă͋M�d�Ȗ{�ł������B�������q��ǂݎn�߂��̂͂��̌�ł���B�j
�����A���{�̉������̖��͂����܂ł��Ȃ��A�����������ɏW���킯�ł͂Ȃ��B�u�P�Ə��v�����d��ł��邵�A�u���扺�����v�����[���ł���B
��ŁA�����Ȍ�̉������j�́g���������̖��h�ƌ������Ƃ��������ł����A���{�������̈����ʂ������o�Ă��āA�����Ƌ���y�����E���Ƃƌ�p�w�҂�́A�s�����Ŕ�Ȋw�I�Ȑ���𐄂��i�߂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�i�����a�E�C�^�C�C�^�C�a�ŁA���{�̊w�҂������ɕs���`�ł���^������c�Ȃ�����̂ł���^�����������銯�����}���������̂����킩�����B����ꂪ�m�����u���x�̂Ȃ��̉Ȋw�v�Ƃ����̂͂����������̂ł������B�j
�����A�����������{��������u���x�̂Ȃ��̉Ȋw�v�̖��̔w��ɂ́A�����s���̔��I�ԓx������̂ł͂Ȃ����B�����������̐K�̖����u����C���v�ɂ��Ă��܂��Ă����A�Ƃ����悤�ɁB�t�Ɍ����A�킪���I�ɓ_�ɗ��r���邱�ƂŁA�݂��炩�̎��������������i�ނ��Ƃ��A�����͂ł���̂�������Ȃ��B
�i5.3�j�F�������̖{��
�i5.3.a�j�F�������̋@�\
�������͓s�s�ɕK�R�I�ł���A�Ƃ����Ƃ��납��o�����āA�������̋@�\�ɂ��āA�l���Ă݂悤�B
�s�s�̂�����͔��ɑ��l�ŁA���̓K�ȁu��`�v�������B���Ɠs�s�E�H�Ɠs�s�E�����s�s�E�`�p�s�s����ȂǁA�s�s�̋@�\�I�������������̂������������Ă݂�A���̑��l�����悭������B�����A���_�ł͓s�s�̊��S�Ȓ�`��K�v�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���̑��l�ȓ����̂����̂ЂƂu���W�v�ɒ��ڂ�������B
�l���̖��W�E��Ƒ̖̂��W�E���Z�̖��W�E����̖��W�E���Y�̖��W�����B�����Ƃ���ɑ������W�܂��Ă���B���x�����A���l�ȓ������W�܂�B
�����u���W�v���Ӗ�����Ƃ���́A
- �l�H���i�����A���H�Ȃǁj�̏W�ς��N���邱�ƁB�l�Ԃ̐������̑������A�l�H���ɂ���č\�������悤�ɂȂ�B
- ����ɂ���Ă��܂��܂́g���Ёh����u�Ă���Ƃ������ƁB�Ƃ������A�ӎ��I�ɂ����ړI�Ƃ��āu���W�v���s����B�O�G�̐N���Ȃǂ̖h��̂��߂ɏ�ǂ�z�����s�s�͂悭�m���Ă���B���������u�l�I���Ёv�����łȂ��A�u���R�̋��Ёv������B�����Ŏ��R�̋��ЂƂ����̂͏����E�����E�Q���E���Q�Ȃǂ̂��Ƃł���B
- �l�H�I���̂Ȃ��ł̐����B�Z���͂�����H��i�ς܂ł��l�H�I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����B����s�s�ł͂��ꂪ�O�ꂵ���u�Z�p���v�Ƃł������ׂ����x�E���x�E���o�Ȃǂ̃R���g���[�����ꂽ�����ł̐������A���ۂɍs���Ă���B����Ȃ��ł͌���s�s�ł̐������قƂ�Ǖs�\�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�����قǂ��i�u�Z�p���v�Ƃ�����͕��}�S�Ȏ��T�̍��ځu�����v���R���M�ɂ��j�B
- ���́u���W�v����O�֔r�����ׂ��������̂��̂����邱�ƁB�G�l���M�[�I�ɂ́u�p�M�v�ł���A�����I�ɂ͌ő̏�u�S�~�v�Ɖt�̏�u�����v�ƋC�̏�u�r�K�X�v�ł���B���W���r�������Ȃ�ɂ�āA�����́u�r���̃V�X�e���v��s�s�̕K�R�I�Ȋ�{�ݔ��Ƃ��Đݒu������Ȃ��Ȃ�B
�J�����ł��邾���n���ɂ��ݍ��܂��A�n������L�x�ɂ��A�n�\����̐��̏������v���Ĕp�M���v�邱�Ƃ��d�v�ł���B�n�\����̐��̏����̂��߂ɂ��ܑ�����Ă��Ȃ��n�ʂ��I�o���Ă��邱�Ƃ͏d�v�ł���B�v����ɁA�s�s�ɐ��z��������Ƃ������Ƃł���B�i�����ł��Ȃ��̂́A��������́u�R���v�ł���B�����s�����ǂ̃T�C�g�ɂ��ƁA�Q�O�O�P�N�̘R�������U�D�S���ł���B���ꂪ�A���ؑ�_���̗����ʂ��Ă���Ƃ����B�܂�A�������瓌���̒n���ɂ��ꂮ�炢�̐���Z�������߂Ă���̂ł���A�����Ƃ����ϓ_����͘R���͖��ʂȂ̂����A�n���̎���C�E�n�������l����Ɩ��Ӗ��Ƃ͂����Ȃ��̂ł���B����������̘R����Z���̌��ۂ��A����ł͏d����炵���B�j
�ő̏��u�S�~�v�̖��́A�������p��������ł����āA���ꂪ�����ɐ[���Ȍ���̖��ł��邩�́A������v���Ȃ��i�K�������s�s���Ɍ��肳��Ȃ��j�B�S�~�o���̕��ʁE�p�����̃��T�C�N���E�p�����̏ċp�E�p�����̎̂ďꥥ�����̂ǂ�ЂƂȒP�ɉ����̂������Ȗ��͂Ȃ��B
���_�̎��ł��镳�A�́A�����������z�̃��x���̖��ł���̂�����A�����ɂ�镨���z�ɂ̂��Ă��Ή��������͂����A�Ƃ������������݂��Ă���i��q�j�B����ɑ��āA�p�������́A�Q�O���I�㔼�Ɏ����ĉ�R������ƂȂ��Ă��܂����B����́A�����z�ɂ̂�Ȃ�����(�v���X�`�b�N�Ȃ�)����ʂɔp�������Ƃ����������炳�ꂽ����ł���B�����́A�����ċp��������ق��Ȃ��̂����A�ċp�ɂ��Y�_�K�X�̔����ɂ�鉷�g�����A�_�C�I�L�V���Ȃǂ̗L�Q�����̔����̖��Ȃǂ�����A�ċp�����Ƃ��������ȕ��@�������������@�Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��̂ł���B�킽���́A�u�p�����̃��T�C�N���v�Ƃ�����@���{���ɗL���Ȃ̂��ǂ����ɂ��āA���Ȃ���^�I�ł���B���T�C�N�����邽�߂ɐV���ɔ�₷�ޗ��E�G�l���M�[�̎��x���g�[�^�����L���ɂȂ��Ă���̂��B���̕��ʂɂ��āA�S�������Ă���B�������A���_�͈̔͂���̂ŁA�p�������ɂ͓��݂��܂Ȃ����Ƃɂ���B�����A���A���͔p�������̈ꕔ���ł���̂͊m���ł���A��ʉ����Ĉ������������̋}���������Ă���悤�ȏꍇ�́A�ǂ�ǂ�̈���z���Ă�������ł���B���Ƃ��A���������̍ŏI�i�K�ŏċp����������̂����ݕ��ʂȂ̂����A������ǂ̂悤�ɕ]�����邩�A�Ƃ����悤�Ȗ��̏ꍇ�ł���B
�킽���́A�����܂ł̍l�@���s�s�ɂƂ��āA�������͕K�R�I�ł����ƌ��_�������B
�������́A��{�I�ɂ́u�����v��s�s�O���֔r�o���鐅�H�ł���B�͂��߂͓V�R�̐��H�����p���ꂽ�ł��낤���A�a�E�@�芄��Ȃǐl�H���H������A�J���ł��������̂��A���L�E�u�a�Ȃǂ�h�����߂ɈË��A�ǘH�ƂȂ��Ă����B
�s�s�́A�s�s���́u���W�v���ďZ�ށ^�����Ƃ���ł���B���̓s�s���������A�ǂ�ȖړI�̂��߂Ɂu���W�v���Ă��悤�Ƃ��A�����Ő����Ă���Ƃ��������ŕK�R�I�ɂ��肾���r�������E�p�M(�Y�_�K�X�E���A�E�����r���E�S�~)������B�����r������V�X�e���́A�s�s���s�s�Ƃ��ċ@�\���邽�߂̕K�R�I�ȃV�X�e���ł���A�ƍl������B
�s�s������O�Ȃ���肾�����A����G�r���̏��u�́A�s�s�����̐��藧�����炵�Ĕ����Ă���ׂ���{�@�\�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�������ɂ�������������B
���̊�{�@�\���ʂ�����Ȃ��Ȃ�Ɠs�s�͕���B����́u���s���v�̌`�œs�s���P���ł��낤�B�u���ݐ��v���s������͂邩��O�ʼn��������@�\���Ȃ��Ȃ��āA�s�s�́u���W�v�����ቺ���͂��߁A�s�s�Ƃ��Ă̎��������A�S�[�X�g�^�E�������͂��߂�B
�]�˂̂悤�ɛ��A��_�����L���Ŕ�������Ă����V�X�e��������ꍇ�ɂ́A���A�������������Ɉς˂�K�v�͂Ȃ������B���̑���ɒ������֏��Ƌ��ݎ��Ƃ����������K�v�ł������B�㐅�����ݔ������ɂ��������Đ����֏������y���͂��߁A���ꂪ�������ɐڑ�������������U�o������ƁA�������֏��̂����Ƃ������ɖ߂邱�Ƃ͕s�\�ł���B���̈Ӗ��ł́A�����֏��͕K�R�I���A�Ƃ������B
�����A���ݍL�܂��Ă��鐅���֏��i�̌`���j���K�R�I���Ƃ́A�Ƃ��Ă��v���Ȃ��B�����O��Ƃ��Ă��i�����j���ǂ̕����͂��邾�낤�B��i�����j�̕������l���鉿�l�͂���Ǝv���i���Ȃǂɂ�鐴�@�@�j�B�����������ɂ��Ă͑�5.4���g�ѕ֊�̏������Ř_�������ł���B
�Ȃ��A��������̍ŏ��̐����֏��́u�Z�����v�ł������B
[������]���������Ă����Ŕr�o���鉘���͑�n�ɉ������i�������j������A���H�ɗ��o���Ȃ��悤�ɂ��Ď��R�Z���ɂ܂����A��Ɣ��̔������ɂȂ��Ă����B�܂���J���~��Ƃ��ӂ�ė��o����Ƃ�������i������ꂽ�̂ł���B�i�w�����S�N�j�x��R��p710�j���̂��ƁA�吳����ɂ́u�P�Ə��v���g����悤�ɂȂ����B�������ɂ����s�����̂łP�X�Q�P�i�吳�P�O�j�N�̌x�����߂ɋK�肪����Ƃ����B���̓_�A�������Ȃ��ڍׂ͕�����Ȃ��B�������A���̃^�C�v�̏������܂Ŏg��������ꂽ�B����Ɋւ�����́A��i5.3.d�j���l�������ň����B
�����ЂƂ������Ɋ��҂����d�v�ȋ@�\�́A�J�����s�s�����ɑؗ����Ȃ��悤�ɁA���₩�ɔr�����邱�Ƃł���B����́A�~���ʂ̑������{�̓s�s�ȂǂɂƂ��Ă͂�邪���ɂł��Ȃ��@�\�ł���B
�����l���Ă݂�ƁA�{���͉J���́A�u�����v�Ƃ��Ĕr���̑ΏۂɂȂ�ׂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ͎����ł���B�X�сE�����c���ɂƂ��ẮA�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂��B�s�s�ɂƂ��ĉJ�����r���ΏۂƂȂ�̂́A�Z���E�^��������Ăł����āA�s�s�Z���̏㐅���́A�����I�ɂ͐����n�̍~�J�ɂ���Ă܂��Ȃ��Ă���B�܂�A�J�����͂��߂��牺���Ƃ��Ĉ������݂̓s�s�̉������V�X�e���́A�ƂĂ��g����Ȃ��������Ă��邱�ƂɂȂ�B������A���̋@�\�ɂ��ẮA�l�������Ă݂鉿�l������B�g�J���������Ƃ��Ȃ��V�X�e���h���l������͂��ł���B
�����ł������Ƃ��Ă��A�s�s�ɂ�����J���r���̋@�\���d�v�ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��B�����āA����́u�͐�Ǘ��v�̖��Ɗ֘A���āA���z�S�̂̂Ȃ��ōl���Ă����ׂ����Ƃł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�͐�Ǘ��Ƃ��������A����͐��Ǘ��i�������m�ہA�Z���E�^����j�����̖��ł͂Ȃ��B�Ώ��E�͐�𗘗p���Ă���̂͐l�Ԃ����ł͂Ȃ��A�����鐶�������p���Ă���̂ł���B�����鐶�������̐������Ă�����̒��Ől�Ԃ������Ă����Ƃ����̂��A�l�Ԃ̐����l���Ƃ��Ė]�܂����B�܂�A���z�͐��Ԍn�S�̂̒��ōl���Ă����ׂ��ł���A�ƍl����B
�i�����g�������h�Ƃ����l���Ȃ����z����A�_�����݂�R���N���[�g�Ōł߂��ݍH�������Ղɔ��z����Ă���B�g���n���H�h�Ƃł����������悤�ȁA�y�؉��̗͔C���̋���H���́A�����Y�Ɨp�������Ƃ����l���Ă��Ȃ����z�ɂ���Ă͂��߂ĉ\�ł���B���ۂɂ́A���͂��ׂĂ̐��������p���Ă���̂ł���A���鐅�n�͖����̐����ɂ���āA���p����Ă���̂ł���B�j
�J���𑼂̉����E�r���Ɠ���̊ǘH�Ŕr�����鉺�����̕������������Ƃ����B�J���p�̊ǘH��݂��āA�����E�r���Ƃ͕ʂɂ������������������Ƃ����B�����ɂ��ẮA�O�߁i5.2.b�j�u���{�̉������j�v�ŏq�ׂ��̂ŁA�J�肩�����Ȃ��B
�������̋@�\�̂R�ԖڂƂ��Ĉ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�H��r���̏����ł���B
���Ƃ��A��Ɉ��p�����G���Q���X�w�C�M���X�ɂ�����J���ҊK���̏�ԁx�̂Ȃ��ɁA
���� ���̏��ɂ͏�̍����₵�H�ꂪ����A����ɐ�ɂ́A���F�H��⍜���������A�K�X�����H�ꂪ�����āA��������̔r����r���͂��Ƃ��Ƃ��A�[�N��ɉ^���B�A�[�N��͂��̂ق��ɁA����ɐڑ����鉺���a��֏��̒��g�����B�Ƃ����`�ʂ��������B�P�X���I�O���̃}���`�F�X�^�[�ŁA���R���H�ւ́u�H��r���v�̕����̎��Ԃ������Ă���B���̏����P���ׂ��A�ߑ�I��������ݒu����̂ł��邩��A�u�H��r���v���u�����v�̒��Ԃɓ������͕̂K�R�����������B���̂悤�ɁA�H��r������ʂ̉������Ɏ������������������Ƃ����B
�������A��Ƃ̊����ɔ����H��r���ƁA�s�s���̎��I�����ɕK�R�I�ɔ����ƒ뉘���Ƃ������Ō����������������̂́A�����炩�ɂ��������B�s�s�����K�R�I�ɔr�o���鉘���E�����ƁA����Ƃ̊����ɂ��r���B���̓�͂����Ȃ��Ƃ��_���I�ɂ͋�ʂ���Ĉ�����ׂ��ł���B�����������͍��E�����̂��A�ŋ��ɂ���Č��I�ɐݒu������̂ł��邩��ł���B�i�����Ƃ����̐��Y�����ɂ���čH��r�����o���Ƃ������Ƃ�����B�ʂ̊�Ƃ͂܂�ŏo���Ȃ��B�����Ƃ͗L�Q������r�o����A�ʂ̊�Ƃ͏������ɂ����L�@�����ʂɏo���B�܂�A��Ƃ̔r���͂��܂��܂ł���B�������A�����̊�Ɗ����͎��I���v�Nj��̂��߂ɍs���Ă���B
����ɑ��āA�s�s���̎��I�����ɕK�R�I�ɔ������ցE�����r���́A�������Ă���Δr�o�����B����͔C�ӂł��Ȃ����r�o�����ɂ��܂���Ƃ������̂ł��Ȃ��B
�O�ҁE�H��r���͎��I�C�Ӑ�������B����ɂ������āA��҂͕��ՓI�ł���A�������̌������̍������̂��̂ł���B�j
�������͈�x�����Ă��܂��ƁA�����ȒP�ɂ���ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߂ɁA�v��̒i�K�łǂꂾ���̊�Ƃ��H��r�����o���������ς����Đv���邱�ƂɂȂ�B�������A��Ƃ̐��Y�����́u���I�v�Ȍo�ϊ����ł����āA�\��ʂ萶�Y���s���邩�ǂ����͕ۏ̌���ł͂Ȃ��B�i�C�������Ȃ��čH��c�n�̗U�v���_���ɂȂ����A�ȂǂƂ����b�͂�����ł������B���������H��r��������邱�Ƃ������Ƃ���ƁA�����̐��Y�����̂��߂ɂ��炩���ߏ\���ȏ����\�͂̂��鉺����������Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A�ŋ��ɂ���Ăł���B�����ɂ������������剻���₷�����@������A��Ƃ̐��Y�����ւ̉ߓx�ȕی삪����B�����܂ł��Ȃ��A��Ƃ͔r�����H����ŏ��������Ċ��֕������邱�Ƃ������Ƃ��ׂ��ł���B�_���I�ɂ����������A�������Z�p�I�ɂ������Ȃ̂ł���B���܂ꂽ����̔p�t�����̔�������ŏ�������̂��A�����Ƃ��e�Ղł��邩��B
����ɁA���[���Ȗ�肪����B�H��r���͉ƒ뉘���̂悤�Ɏ�Ƃ��ėL�@�I��������ł��Ă���̂ł͂Ȃ��A�L�Q�Ȗ��@�������܂�ł����莩�R�E�ɂ͑��݂��Ȃ������ł������肷��B�������A�r�o�����ʂ��ƒ뉘���Ƃ���ׂĔ�r�ɂȂ�Ȃ��قǑ��ʂł��邱�Ƃ����ʂ�(�ƒ뉘���Ɠ����x�̗ʂƎ��̊�Ɣr���ł���Ȃ�A�����������֎����̂͂��܂�Ȃ����낤)�B�������A���s�@�ɗL�Q���������H��r���Ƃ��ĉ������֗����o���Ă͂����Ȃ��Ƃ����͂��邪�i�Ⴆ�Ή������@��P�Q���̂Q�j�A���ꂪ���ۂɎ���Ă��邩�ǂ����̌����͓���B�ᔽ�̌�����������Ȃ��Ǝ��������R�������A�ᔽ�͏��m�̏�ł��̂�����A�[��ɕ���������J�̍~��͂��߂Ƀ^�������ȂǁA�H�ꑤ���m�b���i��B
�������̍H�ꂩ��̔r������������A�ƒ�r���Ƃ���������ĉ���������ɒB���邱�ƂɂȂ邪�A�������ꔖ�܂��đ�ʂƂȂ�����������������̂́A�X�̍H��ō����O�̔r������������̂ɂ���ׂāA��r�ɂȂ�Ȃ��قǍ���ł���B���̓_�́A������łׂ̂��u��������ŏ�������v�������Ƃ��ׂ����Ƃ������Ƃł���B
���̂悤�ɁA�̒ʂ�Ȃ���Ȑ��x�ł���u���������v�ɂ��āA�������q�͂��̂悤�Ȍ���I�ȍ����������Ĕᔻ���Ă���B
�H��r�����������ɂƂ肱�ސ���́A�����āA���m����R���炨���Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�����̂�Z������Ƃ̔p�������̐ӔC�������肷��Ƃ����A�͂�����Ƃ������j�̂��Ƃɂ����Ȃ��Ă����̂��B�u���a�S�Q�N�A���Q���{�@������߂����ĎY�ƍ\���R�c����\�������ɁA��Ƃ̌��Q�����S���y�����邽�߂������������ꂽ���Ƃ̂P��������v�i�F�䏃�j���Ƃ������[�I�Ɏ����Ă���B�i�w�������@�\�\�@���Đ��̓N�w�@�\�\�@�x�����V��1983 p36�@�����͈��p�ҁj���a�S�Q�N�͂P�X�U�V�N�ŁA�S����Q�i�����͂��܂����N�ł���i�V�������a67�E�l���s����67�E�x�R�C�^�C�C�^�C�a68�E�F�{�����a69�j�B�P�X�V�O�N�̂�����u���Q����v�i���Q�֘A�@�Ă��P�V�����������j���z���āA�P�X�V�P�`�V�Q�N�ɂ����Č������i�̔����������ɏo��B
������������w�i�̒��Ɂu��Ƃ̌��Q�����S���y�����邽�߂ɉ����������ꂽ���v�Ƃ����Y�ƍ\���R�c��̓��\�������čl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�u���������v�Ƃ��������́A�g�������͖{���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���ׂ����h�Ƃ����������̖{���ɂ������ʼn߂ł��Ȃ��d��Ȗ����͂��ł���B�������̌��������A��Ƃ́u���Q��v���ӂ���ł��܂��āu��ƍ��Ɓv�́u�����v���Ȃ߂��悤�Ƃ��Ă����B�{���́A�������̌������́A�s�s���̎��I�ɓ_�ɔ����镳�ւ̕��Ր��ɍ��������̂ł���̂ɁB
�������q�́A�Z���^���ɂ���Č��ݏȂ��ԓx��ύX�������Ƃ����̂悤�Ɏw�E���Ă���B
���ݏȂ͓����A�������@�̌��O����u���ׂĂ̍H��r�����������֎���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������ł������A�P�X�V�O�N��̑S���I�ȗ��扺�������Ή^���̂Ȃ��ŁA�u���s�������@�̂��Ƃł��A�H��r�����������Ŏ���Ȃ��������v��͉\�v�Ƃ����悤�ɑԓx��ύX���Ă��܂��B�Z���^�������������Ƃ���ł́A�����Ƃ��čH��͎��ȏ����A�������͐����r���Ɛ����������r���ɋ߂��H��̔r�������������Ƃ����悤�ɁA�v���ύX���Ă���Ƃ��낪��������܂��B�i�������q�w���̂��̐��xp51�j���̂悤�ɂ��āA�P�X�W�O�N��ȍ~�A�������s�������X�ɘH�����C�����Ă��Ă���B���ƂɃo�u�������A������ɋꂵ�ޒn�������c�̂��g����H���h��`�ɂ��Ă��Ȃ��X�����͂�����Əo�Ă��Ă���B
���{�̉��������l����ۂɖ����ł��Ȃ����ƂƂ��āA�����s���������g�����̓꒣��h�̖�肪����B
�����E�吳�����ʂ��āA�����s���i�㐅�E�������Ƃ��Ɋ܂ށj�͓����Ȃ̊NJ��������B���a�P�R�N�ɓ����Ȃ�������Ȃ��Ɨ��������A�����s���͂��̗��Ȃ��u���ǁv�i�����NJ��j���邱�ƂɂȂ����B���A�����Ȃ͂f�g�p�ɂ���ĉ��U������ꂽ���A���a�Q�Q�N�ɓ����Ȃ̏��Ǖ��������ݏȂ������p�����B���������āA���ݏȁE�����Ȃ́u���ǁv�ƂȂ����B���a�R�P�N�ɂ͒ʎY�ȏ��ǂ́u�H�Ɨp���@�v���������A����ɍ����̎���ӂ₵���B���a�R�Q�N�ȍ~�́A�㐅���͌����ȁA�������͌��ݏȁA�������A�I��������͌����ȁA�H�Ɛ����͒ʎY�ȂƁA�u�����s���̎O�����v�Ƃ������ƂɂȂ����B
�ȏ�A�������̖����͂��Ă��āA���̂��ꂼ��قȂ�R���Ɛ��������R��ނɕ��ނł��邱�Ƃ����������B�����̎�ނƂ��āA�\�����Ă����B
|
�@�@�@�@�@���� �ƒ뉘���i�䏊�E���C��̎G�r���A�����֏�����̕��A�j �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�� �� �������� �J���i�~�J�A�~��A�Z��j �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@���� ���Ə�r���i�H��A���Ə��A�����A���̑��j |
�i5.3.b�j�F��������
�s�s�����̉����E�s�p���𐅗��ɂ���ēs�s�O���֔r������̂��A�������̋@�\�ł���B���̏ꍇ�A�Ȃ����𗘗p����̂��ɂ��Ă͑�5.5���������ӂ��ގЉ��ł����Ǝ��グ����肾���A����Ō����A�u�n���̐��z�̈ꕔ�ɏ���āA����𗘗p���Ă���v�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B���ɉ����n��������Ő����Ƃ��āi�n���̏d�͂�p���āj�s�s�O���֗����o���̂����A���̐��͂₪�Đ��z�ɂ���Ăӂ����т��ꂢ�Ȑ��ƂȂ��Ė߂��Ă���B
���z��f���炸�ɕۂ��Ă���A�g���ĉ����������ĂщJ���ƂȂ��Ė߂��Ă���̂ŁA�z���Ă�����ł��g����B������A���s���Ɏg����B���̂悤�ȕ����z�̃V�X�e����ۂ��Ă��闬�̂͑��ɂȂ��B���������āA�������������g���̂ɂ͕K�R��������B�i�n�������I�ȕK�R���ł���B�j
�����̕����ʂ����Ȃ��ꍇ�́A�͐�Ȃǂ��{�������Ă��鎩�R��p�i�������E�A���̓����j�ɂ���āA�����͏���邪�A�����ʂ����̌��x����Ɖ͐쉘�����[��������B�͐쉘�����i�ނƁA�Ώ�������C�̉����ɂȂ���B
��������镨�����Ő��������Ă�����͐�̔������̐H���ɂȂ�Ȃ����̂ł���ꍇ�ɂ́A�����������R��p�̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B�ߑ�H�Ƃ����W���A�H��p�t�������ɗ����悤�ɂȂ�ƁA��҂̖�肪�[���ɂȂ�B
�͐�Ȃǂ̊��ւł��邾��������������Ȃ����߂ɁA�������̏I�[�ʼn��炩�̏����A��������������悤�ɂȂ�B
�ŏ��́A���a�r��݂��č��D�Ȃǂ𒾓a�����A�㐟�ݐ����������Ƃ����������Ƃ�ꂽ�B����́A�����I�����Ƃ������Ƃ��ł���B
�����ɂ͕��A�◿�����E�c�тȂǂ��n��������A�����ƂȂ��ė���Ă���̂ł��邩��A���a�����������ł́g���ꂢ�h�ɂȂ����Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A�����ɂ͂͂��߂����i�̐��n�t���r�o�����H��p�t���������邱�Ƃ�����B�����̏L����F�Ȃǐ��̒��ɗn�����Ă��镨������ׂȕ��V���́A�����I�����ɂ���Ă͎�菜�����Ƃ͂ł��Ȃ��B����Ȃ�A�ǂ�����悢�̂��B���ꂪ�ӊO�ɓ��ł������B
�P�X���I���ɂ́A���Ă̌������ł��܂��܂ȕ����ɂ�鉺�������̌������J�n����Ă����B���̌����͂�������A���I�̊Ԃ�ʂ��Ɛ��̉��ꂪ������Ƃ������n�����ł悭�m���Ă��鎖�����o���_�Ƃ��Ă���A�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�ł́A���I�w�ɂ���āA�Ȃ��A�������ꂢ�ɂȂ�̂��B����ɂ��āg�h�߁h�i�������j���ʂ������l���Ȃ��ƁA���̖{���ɋ߂Â��Ȃ��B�h�ߌ��ʁi�z�����ӂ��߂āj�͊�{�I�ɂ͕����I�Ȍ��ʂł���B���I�w�ɐ�������������ɂ���āA���ꂪ�H�ׂ��� ���Ƃ��{���I�ł���B
�Ⴆ�A���̓]����̐�̃V�~�����[�V�����ł���u�U���h�i��j���@�v�́A�Ӑ�ςݏd�˂��h���ɉ������T���Ƃ������@�ł���B�g����̂̓S���S�������Ӑł���A�h�ߌ��ʂ͊��҂ł��Ȃ��B����ł����������邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł���B����́A�ӐΕ\�ʂɔ������������B���A�������̗L�@�����������ĕ������邩��ł���B���̏ꍇ�A���������͋�C�ƐڐG���Ă����Ԃł��邩��D�C���ۂȂǂ��ɐB����B���̎U���h���@�̌������J�n���ꂽ�̂́A�A�����J�̃}�T�`���[�Z�b�c�B���[�����X�������ŁA�P�W�X�P�N�̂��Ƃł���Ƃ����i����G�v�w�]�ˁE�����̉������̂͂Ȃ��x�Z�o��1995 p135�j�B
�����h���̐̕\�ʂɂ��Ă���ۑw���͂����āA�����ŋ�C�������Ȃ���ɐB�����錤�����s���A�u�������D�@�v�Ƃ��Ď������ԁB�i���D sluge �Ƃ����̂́A�������̉�A�܂�����ɐ������V�����t�����Ă��邱�Ƃ�����A�Ō`�Ɖt�̂̒��Ԃ̏�Ԃ̂��́B�D��̂��́B�D�Ƃ����Ă��y�������Ă���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�������̗L�@�����������ɐH�ׂ��āA�������̑̂��\�����镨���Ƃ��ČŒ肳�ꂽ���̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B����ȊO�͐��ƒY�_�K�X�ɂȂ��ĕ�������Ă���B�j�������D�@���ŏ��Ɏ��p�����ꂽ�̂́A�P�X�P�S�N�C�M���X�ł���B�A�����J�ł͂P�X�P�U�N�ȍ~�����ɑ�K�͂ȏ����ꂪ���݂��ꂽ�B
�������D�@�́A�����̍ۂ�v�����N�g�����D�C�����i��C�𐁂�����A�v���y���Ő��ʂ���������A���Ԃ������ɒ��߂ĉ�]������Ȃǁj�̂��ƂŔɐB�����A�������̗L�@����H�ׂ�����B�L�@����H�ׂ�Δ������͑��B����B�܂�A�������̗L�@�����������̑̂Ɂu�����v�����̂ł���B
���̒i�K�Ŋ������D�@�̉^�]���~�߂�ƁA�����͂��ꂢ�ɂȂ��Ă��邪�������̗ʁi�܂�A���D�ʁj�������Ă���B�X�ɉ^�]�𑱂��āA�������������̑̓��̉h�{������ł��邾���g�������h��Ԃ����o���i�u�����ċz�v�Ƃ����j�B�����ʂ�z���Ɣ������͎��Ŋ��ɓ���A���D���ו�������đ��肪�o���肷��B�����ŁA���傤�Ǘǂ��^�C�~���O�ʼn^�]���~�߁A�s�p�̔������̑́i���D�j�����o���i�u�Ђ������v�Ƃ����j���ƂɂȂ�B
���B�ɂ�鐶�̗ʂ̑������u�����v�ƌĂсA�����ċz�⎀�łɂ�錸�����u�ى��v�ƌĂ�ł��܂��B���V�������قƂ�NJ܂�ł��Ȃ��p���̏����ł��A�����ċz���قڏI��������_�ł́A�t���[���ɋ��������G�T�i�a�n�c�ʁj�̖�U�O�����ى�����܂����A��S�O���͉��D�̌`�Ŏc��܂��B�i�{���~�T�w���o�C�I�w����x�Z�o��2001 p89�j�܂�A�������̗n��L�@���̂S�����x�����D�Ƃ��Ďc��Ƃ����̂ł���B�V���������������ė�����A���̉��D�̈ꕔ�͎�[�^�l]�Ƃ��ĉ����Ă�邪�A�̂�����]�艘�D�Ƃ��Ĉ��������A���̏����i���������A�E���A�ċp�Ȃǁj�ɐi�ށB
���̂悤�Ɋ������D�@�����ۂɉ^�]����ɂ͍��x�ȋZ�p�ƌo�����K�v�ŁA��C�𐁂����ނ��߂ɓd�͂��g���B�������A��ʏ������\�ŁA���ݑS���E�ŗp�����Ă��鉺�������̒��S�I�ȕ��@�ł���B
�����쌴�𗬂��Ȃǂ�T�^�Ƃ���D�C�����ɂ������āA�b����h�u�̌��C����������B���t��͂�}�ȂǁA���⓮���̎��̂Ȃǂ��A����ɒ��ށB����ƁA�_�f������D�C���ۂ��������邪�A�₪�āA����炪�_�f���g���ʂ����Đ��ꂪ���C�I���ɂȂ�ƁA���C�I�����̂��ƂŊ�������ۂ��������͂��߂�B�c���Ă����L�@���̕����́A���C���ۂɃo�g���^�b�`�����B���̌��ʁA���f��Y�_�K�X�A�M�_�A�|�_�ȂǂƂȂ�i���f�����ۂȂǂƂ����j�B����ɂ���琅�f�Ȃǂ�H�ׂă��^�����������郁�^�������ۂ��������͂��߂�B������ɂ���A�L�@���͊��S�Ɂu�����v����Đ��Ɗ��ނ��̋C�̂ƂȂ�B
���ꂪ�A�b����ǂԂ���u�N���A�u�N���Ɓg���C�h�iᏋC�j���킫�オ���Ă��錻�ۂł���B���̃K�X�̓��^�����U���A�Y�_�K�X���R���A���̂ق��ɏ��ʂ̗������f�A�����C�Ȃǂ���Ȃ�Ƃ����B
�����ł́A���_�ɊW�������ŁA���^�������ۂɂ��ĐG���B�i��ɁA�Íۂ̂Ƃ���ł�����x�o�Ă���B��5.5.b���A���E�ہE�Í��j
���^���ۂ͗L�@���̖��[�����҂Ƃ��Ă̈Ӌ`���傫���B��ʂɍD�C���������̕�����p�̕����z�n�ɂ���������͋���Ȃ��̂ł��邪�A�D�C���ۂ̍�p�͂��Ȃ炸�_�f�̏��������������߁A�����ł͌��C���ۂ̍�p���d�v�ɂȂ�B���^���ۂ͐��f������邱�Ƃɂ���Ă��̌��C�����ɎQ�����Ă��鐅�f�����ۂ̊�����������ƂƂ��ɁA�݂�������L�@����Y�f�P�̉������ɂ܂œO��I�ɕ�������������ʂ����Ă���B�i�É�m��w�Íہx����o�ʼn� p135�j�����̌��C���ۂ̊������V�~�����[�g�����̂��A����������Łu���C�����v�Ƃ��u���������v�ƌĂ�Ă��鏈���H���ł���B
�ʏ�́A�D�C���������I��������Ƃ̗]�艘�D�i�X���b�W�j�̏����Ƃ��čs����B�L�@�������^���ɂ���̂�����A���D�ʂ�����A�����ɔ������闰�����f�ɂ���ďd�����C�I�����s�n�����ƂȂ��Ē��a����B���C�������ɕa���ہE�����Ȃǂ����ł���B�ʋC�̕K�v���Ȃ��̂Łu�������D�@�v�Ȃǂ̂悤�ɓd�͂��g���Ĕ��C����K�v���Ȃ��B�����������^���͔R���Ƃ��ăG�l���M�[���ƂȂ�B���̂悤�Ɍ��C�����͂������ƂÂ��߂Ȃ̂����A���C�����̌��_�́A�����Ɏ��Ԃ������邱�Ƃł���B����ł͒ʏ�͑傫�ȃ^���N��p�ӂ��A�����`�P���̏����̎��Ԃ��K�v�ł���B���������āA���̏����@�̂����ꂽ�_�͔F�߂��Ă��A���݂́g�]�T������h�s���Ƃ������x�̕⏕�I�Ȉʒu�Â��ƂȂ��Ă���B�i���c�A�̃T�C�g�������D�Ə����K�X�i2001/12/5�j�ɂ��ƁA�u�������D�����ɂ����錙�C�������@�̍̑��͂Q�U�D�S���Ƃ��܂荂���Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�j
�����́g�悲��h�́A��{�I�ɕ��A�E�䏊�S�~�Ȃǐl�Ԃ̐����Ƃ��Ă̊����i�H�ׂ邱�ƁA�r�����邱�Ɓj�ɂ������L�@�I�r�o���ł����āA�������������̂��H���A���̏z�̂Ȃ��̔������ɔC�����Ƃ������@�ŏ�������Ă��邱�ƂɂȂ�B���������g���̂́A���̂ł��鉺���ɑ����ʏ����ɓK���Ă��邩��ł����āA�P�ɐH���A���̒��̐����ɔC����Ƃ������ƂȂ�A�ؕ֏��̓�{����̋��ɕ��A�E�䏊�S�~��H�ׂ�����Ƃ������@�ł��悢�̂ł���B
����l�����R�l�Ƃ����ꍇ�Ɂi�������Ȃǂ̐l�H�I�{�݂��Ȃ������Ƃ����ꍇ�Ɂj�A���̕��A�E�H���J�X�Ȃǂ��H���A���̃��[�g�ɏ���Ă��ǂ��Ă��������̓����l����B���̍Ō�̍s���i�Y�_�K�X�Ɛ��Ȃǂɕ��������Ƃ���j�܂ł��ǂ�A���A�E�H���J�X�Ȃǂ͊��S�ɕ�������A�������̑̂Ɏ�荞�܂ꂽ��i�����j�A���@���ɂȂ�����i�ى��j���Ă���B���̔��������₪�Ď��ɁA�ʂ̔������ɂ��ׂ���B�����āA�n���̕����z�ɉ�����āA�Ăяz���͂��߂�B���̐H���A���̓��̈ꕔ���Ƃ肠���āA�l�H���E�H�Ɖ������̂����������ł���B���������āA���́u���R���f���v�Ƃ�������u����������悤�ȉ��������ł���A���ꂪ���z�I�ȉ��������Ȃ̂ł���i�O��5.3.a�ŁA�u�����v�Ƃ������̂͂����̂��Ƃł���j�B
���R�̉ߒ��ł́A�H���A���������z�̕����Ƃ��ē����āA�S�̂����I����n������Ă���B�X�̕����͓����Ă���̂����A���̑S�̂͂ЂƂ̐����|�����n�Ƃ��Ĉ��肵�Ă���̂ł���B���������āA�����Ŗ��ɂȂ�̂́A���̈ꕔ���ɉ����������荞��ł��A�����z���r�ꂸ�ɂ�����ƍs���Ă��邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃł���B�_�n�łƂꂽ���̂��z���Ă��Ƃɖ߂��Ă��邩�B�R�łƂꂽ���̂��R�ɖ߂��Ă��邩�B�q��łƂꂽ���̂��q��ɖ߂��Ă��邩�B�C�łƂꂽ���̂��C�ɖ߂��Ă��邩�B
�l�Ԃ����ۂɂ��Ƃɖ߂��Ă��K�v�͂��Ȃ炸�����Ȃ����A�z���Ă��Ƃɖ߂��Ă��邩�Ƃ����ϓ_�ʼn����������邱�Ƃ��d�v���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ⴆ�ΐ��z�́A��{�I�ɂ͑��z�G�l���M�[�ɂ���Đ����C����C�����㏸���ĉJ�_�ƂȂ邱�Ƃŏz���N����̂ŁA�����ꂩ��������ꂽ��̐��z�͂���قǐS�z����K�v�͂Ȃ��B�ނ���A�㉺�����̓�������o���܂ł̊Ԃ̊ǘH���A�V�R�͐�̐���D���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����肪����B�Y�f�z�ƒ��f�z�ɂ��Ă͑�5.5.b���A���E�ہE�Í��ŐG���B�����ɂ́A�ۂ��������z�����݂��Ă���B�������A���f�͐l�H�̒��f�Œ�H��̍��o�����f�������ɂ���ׂāA�ɉ��ہE�E���f�ۂȂǂ̓������x���A�z�����Ă���B�����������ɂƂ��Ă���߂ďd�v�Ȍ��f�ł��邪�A�����_�����C�ɏo�đ͐ϕ��ƂȂ胊���z�ƂȂ�n���w�I���x�ƁA�l�Ԃ��߃����_�ΊD�Ȃǂ̔엿��y���ɂ܂��A���ꂪ�H���ƂȂ��čŏI�I�ɉ���������o����鑬�x�͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǑ����B���ɁA���f������Ώ��ȂǕ�����ʼnߏ�ɂȂ�x�h�{���͔����������B
�����ЂƂd�v�Ȋϓ_�́A���Ƃ��Ƃ̎��R�̕����z�̂Ȃ��ɑ��݂��Ȃ��������̂��A�l�Ԃ��V���ɉ����Ă��Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B�������R�T���N�̗��j�̂Ȃ��ō���Ă����A�H���A������{�Ƃ��镨���z���A�����Ă��Ȃ�����������l�Ԃ������Ă��Ȃ����Ƃ������ł���B�i�����z�ɂ͐����������Ȃ��Ƃ���������n�������I�z�����݂���B�܂��A���z�ł���B����ɁA�}�O�}������v���[�g�^���A��C�̓�����C���Ȃǂ�����B���A�n�����g���̖��́A�l�Ԋ������n�������I�����ɂ܂ʼne����^���Ă��邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃ��j
�H���A���̏z�̂Ȃ��̔������̎�ɂ����Ȃ��������A�s�s�̉������ɂ͂��肱�߂A�z�����܂����ꂸ�A���Ă��܂��B����͂P�͍H��r���ł���i������u�����v�����Ƃ������Ƃɂ��ẮA���q�j�A�����P�̌��O�͓s��̉J���ł���B�����������ɍ��������߂�ƁA�������̐H���ɂ͂Ȃ肦�Ȃ���������������E���Ă��܂��L�Q�����₪������\��������i�����J���̖��́A��5.2.b�����{�̏ꍇ�ň������j�B
�]�艘�D�̏����́A���͂����Ƃ���������܂�ł���B�������̉������p���t���b�g�͑�K�͂ȉ���������̎ʐ^���ڂ��ďI����Ă��邱�Ƃ��������A�����̊̐S�ȂƂ���͉���������ł͏I����Ă��Ȃ��̂ł���B�s�s���p�������������ŏI�I�ɂǂ��֎����čs�����Ƃ������Ƃ̂Ȃ��ɁA�������V�X�e���̂������₤���ɂ̖��_�����݂��Ă���̂ł���B
�����̏ꍇ�A�w�����������P�O�O�N�j�x���甲���o���Ă݂�Ɓip222�`223�j�A
- ��O�A�����p�ɎU�z�������Ă����B
- �펞�̐����A���D�^���D�̉^�]������ƂȂ�A���D��V�����������Ĕ엿���͂��܂�B
- ���a�R�O�N�㔼�A�]�艘�D����ʂƂȂ�A�엿�Ƃ��Ă̎��v���������B�E�����D�̖��ߗ��Ă����������悤�ɂȂ����B
- �ċp�������͂��܂����̂��A�����s�ł͏��a�S�Q�N���䏈����ŁB
�ʂ����Ȃ��A�d�����ȂǗL�Q�������ӂ��܂Ȃ��ꍇ�́A�C�m�����E�엿���̂������������������Ӗ����������i�u�^�������v�����������Ɉ����Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B�����Ȃ��Ƃ��g�ň��h�ł͂Ȃ��j�B���ƂɁu�엿���v�́A�u���A��엿�Ƃ��Ďg�p����v�Ƃ������{�Љ�̓`���I�V�X�e���ɂȂ��݂₷���Ƃ��������łȂ��A���̏����@�͏ċp�����Ƃ���ׂ��z�^�ł���Ƃ��낪�{���I�ɗD��Ă���B���ݏ������邵���Ȃ��s�v�������Ȃ��A�Ƃ����_���d�v�Ȃ̂ł���B�w�����������P�O�O�N�j�x����Y���������p����B
���D�̔엿���Ƃ́A�����D�i���a�r����Ђ�����������̖������̉��D�j�𒾓a�Z�k�����̂��A���D�������œV���������A����ӂ��Ĕ_�Ƃɔ��p����Ƃ������̂ł���B���̕��@�͂��łɈꕔ�Ŏ��{����Ă������A�i���a�j�P�X�N�ȍ~�A�O�͓���������Ŗ{�i�I�ɊJ�n�����B���́u���D�엿�v���Y�Ƃ����Ӌ`�̂��鏈���@�������s���Ȃ��Ȃ������R�̑�P�́A�P�X�U�O�i���a�R�T�j�N����̉����ʂ̋}���ȑ���ł���B
���ɂȂ�ƁA���肩��̔엿�s���f���āA�L�@�엿�Ƃ��č������l�������D�엿�̎��v�͂��������������邱�ƂɂȂ�B���̂��߂Q�P�N�ɂ͎ʼnY������ŁA����ɂR�Q�N����͍���������ł����D�엿�̐��Y���J�n���ꂽ�B�ip222�j
| �N | 1950 | 1960 | 1965 |
|---|---|---|---|
| �������� | 50�� | 104�� | 188�� |
����ɂ���āA���x�������i�P�X�U�O�N��j�ȑO�ɂ͉\�ł������u�V�������v�ȂǂƂ����q�̓I���@���Ӗ��������Ȃ��Ȃ������Ƃ��A��������悤�B
��Q�́A��������ӂ̑�n���ɂ���āA���D�������̑��݂��ł��Ȃ��Ȃ�A���L��n�G�̔�������艻���āA�V������������Ȃ��Ă������ƁB
��R�͉����֗L�Q�������������Ă��邱�Ƃɂ��A���D�엿���엿�Ƃ��Ă̈��S���ɋ^�₪�������悤�ɂȂ������ƁB
�V�������ɑ��āA�l�H���������z�����̂ɂ͕K�R��������B�l�H��������ċp�����ւ́A���ƈ���ł���B
�u�S���Ŕ������鉘�D�̂V�U�����x�i�����d�ʃx�[�X�j���ċp����v�Ă���Ƃ����i�R�`�������D�����{�݂Ɋւ��鍧�k������j�B���D�̂W���͏ċp����Ă���A�Ƃ������Ƃ��B�R�`���̑O�L�T�C�g�ɂ��ƁA�R�`���ł͉��D�̂S�U�����R���|�X�g�i�͔� compost�j�����Ă���A�Ƃ����B�S�����ς̐������m�肽���̂����A�ډ��s���i���Ȃ��Ƃ��Q�����͏��Ȃ����j�B�܂�A�R�`���͉��������̕��ʂł͗D�����Ƃ������ƂɂȂ�悤���B���̃T�C�g�̎��̂悤�Ȏw�E�́A�Q�l�ɂȂ�B
�����P�Q�N�x�ɐ��肳�ꂽ�z�^�Љ�`�����i��{�@�ł́A�p�����̔r�o�}���i���f�B���[�X�j�A�����̍Ďg�p�i�����[�X�j�A�Ďg�p�ł��Ȃ��Ȃ������̂̍Đ��g�p�i���T�C�N���j�����߂��Ă���B�܂�����ł́A�Ǘ��^�Y�Ɣp�����ŏI������̎c�e�ʂ����ɕN�����Ă��錻����l������A�L���Ȏ����ɂȂ蓾�鉺�����D�������p�����邾���łȂ��A�R���|�X�g�̎��v�����ł��ɂȂ��Ă������ƁA�ƒ{�r�����ɂ��R���|�X�g���V���ɑ�ʂɎs��ɏo�Ă��邱�Ƃ��\�z����邱�ƂȂǂ���A�R���|�X�g�ȊO�̐V���ȗL�����p�@���m�����邱�Ƃ��ً}�̉ۑ�ƂȂ��Ă���B�i�����͈��p�ҁj�u�R���|�X�g�̎��v�����ł��ɂȂ��Ă���v�Ƃ������Ƃ��[���ł���B�������A�Ȃ��Ȃ̂��낤���B���{�̔_�Ƃ̂�������C�ɂȂ��Ă���B
����̒��ɂ������u�ƒ{�r�����ɂ��R���|�X�g�v�Ƃ����̂́A���T�C�g�̒��������Ă����B���̂悤�Ȏ������Ƃ����̂��B
�����P�U�N�P�P���P������A�u�ƒ{�r�����̊Ǘ��̓K�����y�ї��p�̑��i�Ɋւ���@���v�̓K�p�ɂ���ς݁E�f�@�蓙�̕s�K�ȏ������o���Ȃ��Ȃ邽�߁A�͔쉻�{�݂ɂ��R���|�X�g�����i�߂��Ă���B�i���E�n�P�O���A�P�O�O���A�{�Q�O�O�O�H�ȏ�̑�K�͒{�Y�_�Ƃ��@���̑Ώہj�����̕��ւ������ɗ����āA���ꂪ�R���|�X�g�i�u�͔�v�ƌ��������̂ɁA���������Ȃǂ̉ߒ���������ꍇ�́A���̋ƊE�ł́u�R���|�X�g�v�ƌ��������炵���̂��j�ƂȂ��ēc���֖߂��Ă���̂Ȃ���������A�d���������Ȃǁu���������v�̐S�z�̂Ȃ��Ƃ���ł��A�u���v�̓��ł��v�Ƃ����Ō�̈�����n����Ă��܂��̂��Ƃ���ƁA�W�]���J���Ȃ��B
���{�͑��ʂ̐H�Ƃ��O������A�����āA�܂��Ȃ��Ă���i��T���~���x�ŁA�P�X�W�S�N�ȗ����E�ő�j�B�����H�ׂ��i�H�c���Ċ��Ă��j���Ƃ̕��A�E�����S�~�́A�ŏI�I�ɉ����������āA�R���|�X�g�ɂ��āA���Y�n�̓c���֖߂��o�����X���Ƃ��B�������A���ۂɂ͂���Ȃ��Ƃ͂��Ă��炸�A�����⒂�f�����Ƃ̓c���ւ��ǂ炸�ɁA���{�̌Ώ��Ȃǂɑؗ����Ă�������ɕx�h�{���Ώ������܂�Ă���B���{�̓c�����u�R���|�X�g�v��K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂́A���ۃ��x���̃A���o�����X�̖��Ƃ��l������B���{�̔_�Ƃ̎��ۂ́A�Ⴄ���R�ɂ��̂����m��Ȃ����A��ǓI�ɂ͂����������Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�_�앨�̌��Y���Ŕ엿�E�_��E��������A���{�ɗA�����āA����ĉ����������ĂW�����ċp�������Ă���B�����E���f�Ȃǂ̉h�{�f�̈���I�Ȉړ��i���Y��������{�ցj�������Ă���B���Y���̓y��͍r�p���A���{�̌Ώ��E���p�E�ߊC���x�h�{������͔̂������Ȃ��̂ł���B
�����A�]�艘�D�̏����@���l�����ŁA�Y��ĂȂ�Ȃ����Ƃ́A�u�����D�v�Ȃ���̂��A����߂Ĉ����ɂ����㕨���A�Ƃ����_�ł���B�X�W���������ł��鐶�����������̉�ł��邩��A�ƂĂ�����₷���B�a���ۂ��܂܂�Ă���B�ł��邾���������������A�����₷���q���I�ɂ����S�E���肵�����̂ɂ���K�v������B�@�B�I�ɒE�����Đ����V�T�����炢�ɂ��ďċp�F�ɓ����B
�ċp�F�̂Ȃ��ŁA�]�艘�D�i�Ƃ����Ă��v����ɔ������̎��[�ł���j���R����B�Y�_�K�X�ȂNjC�̂ɂȂ���̂ƁA�D�ƂȂ��ĔR���c����̂Ƃɂ킩���B��҂̒��ɂ̓����Ȃǂ��܂܂�Ă���̂ł��邩��A�ċp�D����X�Ƀ��������o�������Ȃǂ��ׂ���Ă���B
�P�Ȃ�L�@�������ł���Ȃ�܂������A�H��p�t�������Ă���u���������v�ł́A�d�����Ȃǂ������Ă���B���˂�����ӑ�C�֕��o�����d�����Ȃǂ͗L�Q�ł��邩��������B���Ƃ�����\���B���̍H��ʼn�����������r�ɂȂ�Ȃ��قǔ\���I�ł��邱�Ƃ͖��炩�i�������ł͔Z�x���Z�����ƂƁA�����Ȃ镨�����܂܂�Ă��邩�悭�������Ă���j�B
�i5.3.c�j�F���扺����
�������́A�s�s�̓����̂ЂƂł���u���W�v����K�R�I�ɂ͂��܂�B�s�s���g�債�s�X�n���}���ɖc������Ƃ��A�����������̎s�X�n�ƈ�̂̂��̂Ƃ��āA�Ƃ��ɖc�����Ă������Ƃ����߂���B�������͉����Nj����͂�߂��点�����̎��R�������v��̂ł��邩��A�n�`�I�Ȏ��R�����ɋK�肳��Ă���B���̂��ߎs�����̋敪�����z���āA�����̎s�����������ݒu���鉺�����������I�ł���ꍇ������B�u���扺�����v�ɂ��āA�����Ƃ��D�ӓI�ɗ�������A���̂悤�ɂȂ�B
�w�����������P�O�O�N�j�x�ɗ��扺�����̎n�܂�����̂悤�ɐ������Ă���B
���扺�����́A��s�s�n��̐������𑁊��ɉ������A�l���}���n�тȂǎs�X�n�ɂ����鉺�����ݔ���L�@�I�A��̓I�ɂ����߂邽�߂ɔ����������̂ŁA���a�S�O�N�ɑ��{�̐Q���여�扺�������ŏ��ɐ������ꂽ�B����Ȍ��s�s�ɂ����炸�L��I�ȉ�����������@�Ƃ��đS���I�Ɏ��{����A�U�O�N�����݂Ŗk�C�����牫��܂łS�O�s���{���W�T�����ɂ̂ڂ��Ă���B�ip676�j�Q���여�扺�����́A�����Ȃ��Ƃ����̐ݒu�̎�|�͍��������������ƍl������B���́A���̌�ł���B�u����Ȍ��s�s�ɂ����炸�L��I�ȉ�����������@�Ƃ��đS���I�Ɏ��{����v�A�s�X�n�ȊO�̂Ƃ���ɁA�s�����̋敪�����z���āA��K�͂ȉ���������낤�Ƃ����̂ł���B
���闬��ɉ������n��S�̂��ЂƂ̉������̈�Ƃ݂Ȃ��ċ���ȉ������Ԃŕ����Ƃ���B�ЂƂ̗��悪�����Ă��鎩�R��p��S�ʓI�ɐl�H�I�ȉ������Ɏ�荞��ŁA��K�͂ɊNj��Ԃ����A����ȉ���������ŏ[���X�P�[�������b�g�����ĉ����������s���A�Ƃ����̂����扺�����́g���荞�ݕ���h�ł���B
�������@�́u�p��̒�`�v�i��Q���j�ɂ́A���̂悤�ɏ����Ă���B
4�D���扺�����u����v�Ƃ��������̗��R������Ȃ��̂ŁA����ł͉��x�ǂ�ł����ɓ����Ă����Ȃ��B�@���Ƃ����̂́A���Ă��Ă��������Ƃ������B�����̌`���I�Ȃ��鑤�ʂ��A��ʓI�ɂƂ肠���Ė@�����́E����Ƃ��Ă��邩��ł���B
���ς�n�������c�̂��Ǘ����鉺�����ɂ��r������鉺�����āA�����r�����A�y�я������邽�߂ɒn�������c�̂��Ǘ����鉺�����ŁA�Q�ȏ�̎s�����̋��ɂ����鉺����r��������̂ł���A���A�I���������L������̂������B
���̒�`�́A�u�����̎s�����ɂ܂������ē����������ł��邱�Ɓv�v����ɁA�̐S�Ȃ��Ƃ͂��ꂵ�������Ă��Ȃ��B�`�C�a�C�b ��� �̎s����������A���ꂼ��̉������ǂ�ڑ����鑾�������Nj����A�����s�������т��đ����Ă����킯���B���̊����Nj��̏I���ɏ[���傫�ȁu�I��������v��ݒu���A���̏�����ꃖ���ŁA�����Nj��ɂȂ����Ă���S���̎s�����̉����������ς܂��Ă��܂��B���ꂼ��̎s�����œ����悤�ȏ����������̂ɂ���ׂāA�����ƁA���オ�肾�Ƃ����킯���B
�`�C�a�C�b ��� �̎s�������т��ĉ��тĂ��āA�I��������ɂ܂Ŏ��銲���Nj���z�����Ă݂ė~�����B�`�C�a�C�b ��� �̂����̍���������Ⴂ���֏��Ɍ���ŘA�˂Ă����ł��낤�B�Nj��̒��ʼn��������R����������������ł���B����ƈ�Q�̎s�����`�C�a�C�b ��� �́A����������Ⴂ���ւ���͐�̗���ɕ��U�E���z���Ă���悤�Ȉ�Q�ł���ꍇ���A�����I�ł���A���́u���扺�����v�Ȃ���̂ɂӂ��킵�����ƂɂȂ�B
�����Nj����R�z�������āA�قȂ鐅�n�̎s�����Ɛڑ�������̂́A�����̃|���v�E�A�b�v���K�v�ɂȂ����肵�āA���炩�ɕs�����ł���B���������āA�́u�Q�ȏ�̎s�����̋��v�ƌ����Ă��邪�A���ۂɂ��ЂƂ̐��n���������́i�����́j�s�������܂Ƃ߂ĂЂƂ̉������n�ɂ��A���[�������ꃖ���ōς܂��悤�Ƃ������z�Ȃ̂ł���B����Łu����v�Ƃ��������̗��R�͂킩�����Ǝv���B
�������@�ɏ���̗��扺�����̋K�肪�������̂́A�P�X�V�O�i���a�S�T�j�N�̂�����g���Q����h�ɂ����Ăł���i���q�̂悤�ɁA���Q�W�̖@�߂��P�V�{���ꋓ�ɉ����E������������B�u�����������@�v�����̈�������j�B���扺�����̐ݒu�E�Ǘ��͌����Ƃ��ēs���{�����s���Ƃ���A�ȂǗ��扺�����̖@�I�ʒu�Â����͂��߂Ė��炩�ɂȂ����B
���̂Ƃ��������@�̖ړI�Ɂu�����p����̐����̕ۑS�Ɏ����邱�Ɓv��������ꂽ�B���̎����̓��{�́A�P�X�U�O�N�ォ��̍��x�������̂��Ȃ����Q��肪�s�[�N�ɒB���Ă���A�g���Q����h�ň��̏C�����v�炴��Ȃ������̂ł���B�i�����̊������̗�Ƃ��č]�ˎ��ォ��̓`��������c��ԉΑ��̒��~���悭�m���Ă���B���c��̉������[�������邱�Ƃɂ���āA�P�X�U�R�`�V�V�i���a�R�W�`�T�Q�j�N�̂P�T�N�Ԃ́A�ԉΑ����~�ɂȂ��Ă���B�g���Q����h������ň��L�Ȃǂ��Ȃ���P����A�ԉΑ��͍ĊJ���ꂽ�̂ł��邪�A���c��̓R���N���[�g��݂Ōł߂�ꗼ�����ӂ͎�s�������H�⍂�w�r���̌��z���s���Ă���A�����ƌi�ς��ӂ��߂������I�ȓs�s�v��̎��_���Ȃ��������Ƃ�Ɋ���������B�j
�u������������āA����ȉ͐���Ƃ���ǂ����v�Ƃ����悤�ȃL���b�`�E�t���[�Y���A�������ǂ̃p���t���b�g�ɂ͕K���o�Ă���悤�ɂȂ����B���̂���������ŁA���ۂɂ́A�u���扺�����v�̋���H���̌v�悪�����ɂԂ�������ꂽ�B�i���̓_�̔ᔻ�́A�������́u���_�v�́y�S�z�����ė~�����B�j
���{�o�ς̍��x�������ȑO�ɂ́A�w���ӂ̏��K�͂ȏ��X�X�Ƃ��̎��ӂɓ_�݂���_�Ƃ���Ȃ�W���ł������Ƃ��낪�A���x��������ʂ��ĕ����Z��Ȃǂŋ}���Ɏs�X�n�������悤�Ȃ��������n��ł́A�s�������z�������������������̎s�����������ݒu���邱�Ƃɍ����������邱�Ƃ�����A�Ǝv���i���́u�����s�̗��扺�����ɂ��āv���Q���j�B
�������A���̎�@���A�s�X���n��ȊO�̔_�R���Ɍ��x�Ȃ��L����ƁA�g�p����Z���ɂƂ��ẮA�����b�g�����d��ȑ��Q��������B�u���W�v�̏������݂�����Ȃ��悤�Ȓn��ŁA�����I�ȉ������ݔ��́A�������ĕs�����Ȃ̂ł���B
���̏ꍇ�A���̌v��ŗ��v��̂́A����\�Z����ɂł��钆�������ł���A����y�؊�Ƃł���B�悤����ɁA�ŋ��𒆉��ƒn���̗����p�C�v�����v�Ƃ��ĕ��z���Ă������̂������������ł���B�����ł��邩�炱���A�u���扺�����v�v��́A���͂ɐ��i���ꑱ���Ă���B�������q��̉ʊ��Ȕᔻ�ɂ���ė��_�I�Ȕj�]�͖��炩�ł���̂ɂ�������炸�A�g���������h�͌��݂ł���B
�u���扺�����v�������N�������_���A�S�_�����Ă݂��B
- �y�P�z
���ۂ̂Ƃ���A���́u���扺�����v�̌v�悪�A�ǂ������Ƃ���ł܂����Ă��邩�Ƃ����ƁA����\�Z�E����H���Ƃ����Ƃ��낪���ڂ̌����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��B���\�N�v��ł��邽�߂ɏ����ɂ����Ă����������Ȃ����ƁE�l���\����o�ϔ��W�\���Ȃǂ̗\�����O���\�������邱�ƁE�s�����̍������������邱�ƁB���x��������Ɍv�悵�ď����\���𗧂ĂĒ��H���Ă��A���̂̂��̕s���ɂԂ����āA�ڍ����Ă��܂��B
- �y�Q�z
�������[�ɂ����鋐�又����́A���̏�������ӂ̏Z���ɂƂ��ẮA���̎s�����̉������킴�킴�ڑ����Ă��Ď����̂Ƃ���ŏ�������A���̂��߂̐ݔ��ł���B������A�����ꌚ�݂Ɏ^�����ɂ����A���Ή^�����N���₷���B������̏o�������A�E�����r�������̏����Ȃ�܂��䖝�ł��Ă��A�����̎����̂̂��܂�������̂Ƃ���Ɏ����Ă��ĕt����Ƃ����̂ɂ͉䖝�ł��Ȃ��B
- �y�R�z
�s�s�̓����ł���u���W�v�ɂ͂ӂ��킵���������Ԃ��A�Z��_�݂����Ԃ̔_���W���ł͕s�����Ȑݔ��ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�_�݂���Z����J�o�[���鉺�����Nj��̈ꌬ������̕��S���ُ�ɑ��傷�邩��ł���B
�����悤�ɁA�s�����̊Ԃ����Ԋ����Nj��́A���X�ƒ���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����������ݒu���Ȃ��Ă��ނ��Ƃɂ��L�����������ɑ��E���Ă��܂��B
- �y�S�z
���扺�����̌��\�Ƃ��āA�͐�̏�������B�ЂƂ̐��n����搅���㐅�Ƃ��Ďg�p���������A�����ƂȂ��ĉ������𗬉����邪�A���̉����������ł����Ă����̐��n�ɖ߂����ɁA�ł��邾���͌��߂��ɏ����������āA�Ō�͊C�ɕ������邩��ł���B���̒ʂ�ł���A���̐��n�̐�͂˂ɐ���Ȑ��i��x���Nj����������Ă��Ȃ����j������Ă���A�Ƃ����킯�ł���B
����Ƃ����ϓ_����͖]�܂������Ƃ̂悤�Ɏv���邪�A���͐[���Ȗ�肪����B����́A��̐����g�����тɐ��ʂ������Z�ɂȂ�A�ꍇ�ɂ���Ă͉͓����������āA��������Ȃ���ԂɂȂ�B�J���~�����Ƃ����������B�����āA���Ƃ̐�̐��͊����Nj��Ƃ������剺�����̂Ȃ��𗬂�Ă���̂ł���B����́A�l�H���̍ł�����̂ł���B
���̈Ӗ��ł͗��扺�����́A�͐�Ƃ������R�I���݂�ے肷����̂ł���B�����u�������v�Ƃ������Ă��炸�A�͐�͐������̈ړ��H�Ƃ����l���Ă��Ȃ��B���̍l�����ɑ��ẮA�͐�����R�E�̐����̏d�v�Ȉꕔ�Ƃ��ĔF�����A���̊����߂����Đ������鑽���̐����i���A������������ɂ�����S�́j�̑��݂��ɍl����Ƃ������ꂪ�Βu�����B
�����u���扺�����v�̍l�����̒��ɂ͈��̂܂��Ƃ��Ȃ��̂��܂܂�Ă����A�Ǝv���B�����A���{�o�ς����x����������o�u�����ւ����鎞���Ɏ��ۂɘI�o�����̂́A�O���e�X�N�ȁg���厖�ƐM�h�Ƃł������ׂ����̂ł������B
���扺�������u�����������T���N�v��v�œƗ��������ڂƂ��Ď��グ����̂́u��Q�������������T���N�v��v�i�P�X�U�V�`�V�P�j�ł���B�����Ɣ�X�R�O�O���~�B�@�I�Ɉʒu�Â������m�������̂��A�O�q�̂悤�ɉ����������@�ŁA�P�X�V�O�N�́g���Q����h�ł̂��Ƃ������B�u��R�������������T���N�v��v�i�P�X�V�Q�`�V�U�j�ł́A�����Ɣ�Ȃ�ƂQ���U�O�O�O���~�ɂȂ��Ă���B���̎����A����y�؎��Ƃɐɂ��݂Ȃ��ŋ����������܂ꂽ���Ƃ��悭�킩��B���́u��R�������������T���N�v��v�́w�����������P�O�O�N�j�x�ł̐��������p���Ă������B���扺�����̎��ƂɎg��ꂽ�ŋ��̖���I���z���𖡂키�ׂ����B
�Ȃ��ł������B�����邽�߂̎��ƁA�Ƃ��ɗ��扺�������Ƃ͋��͂Ȑ��i���}���邱�ƂƂȂ�B���̂��ߗ��扺�������Ƃ̎��Ɣ�́A��Q���T���N�v��̂U�{���ɂ�����R�U�O�O���~�ɁA�����Ɣ�ɂ��߂銄�����U�D�T������P�S���ɂ͂˂��������ip239�j�u�S���v�i��P���S�������J���v��j���u�V�S���v�i����Q���j�ɍX�V���ꂽ�̂��P�X�U�X�N�T���̊t�c�ł���B�u�J���\���̑S���ւ̊g��Ƒ�K�̓v���W�F�N�g�v���g����h�������i�S���͌o�ϊ�撡�^���y�������肵�Ă���B���݂͂P�X�X�W�N����̑�T���S���Łu�Q�P���I�̍��y�̃O�����h�E�f�U�C���v�j�B
�P�X�V�O�N��̗��扺�������݂������Ƃ��h��ɑł��o���ꂽ����A�S���ɗ��扺�������Ή^�����L�����Ă������B���̉^���̗��_�I�x���ł������������q�̂��̎����̒���w�s�s�̍Đ��Ɖ������x�i���{�]�_��1979�j����A���扺�����͏Z���̐������P�̂��߂Ƃ��������ɂ����ꂽ�H��U�v�̊�Ր����ɂ����Ȃ��A�Ǝ咣���Ă��镔�������p���Ă����B
�����E���E���É��Ȃǂ̏]���̌������������H��r�����܂�ł������A���̊����͂P�`�Q���ł���̂ɁA���扺�����͏��Ȃ��ĂQ���A�����Ƃ���͂V���S���i����E����[�扺�����߉Y����������\�\�܂��v�挈�肳��Ă��Ȃ��j�ɂ��Ȃ��Ă���B�����������������A�s�X�n�����̌��ʁA�Z��n�ɍ��݂��Ă���������Ƃ̔r��������A�₪�đ��Ƃ������Ă��Ă��܂��Ƃ����o�߂����ǂ��Ă���̂ɑ��A���扺�����͂ނ��덡��̍H��U�v�̂��߂ɐ�������悤�Ƃ��Ă���B�ip85�j�S���̔��Ή^���⒆�����q��̓w�͂ƁA�s�����ɂ͂��������{�o�ς̏ɂ���āA�u���扺�����v���݂ɂ��čs�����̈��̏_��A������������B�i���Ƃ��A�P�X�W�R�N�Ɍ��ݏȂ́A�s���{���ɑ��āu�ύX����K�v���������Ƃ��ɂ́A�x�Ȃ��A���扺�������������v���ύX������̂Ƃ���v�Ƃ����ʒB�������Ă���B�j�����A�S���̂������̗��扺�����v��͐��i����A���������邱�Ƃ������ł���B���{�̃f�[�^�͍��y��ʏȃT�C�g�����扺�����̎��{�� ���Q�Ƃ��ė~�����B
�s���ŁA���������H�ƒc�n�͂ǂ����K���Ƃ������A�p�������������̂������邱�Ƃ��H�ƗU�v�̏d�v�ȏ����ɂȂ��Ă���B���扺�������v�悳��Ă��錻�n��������������Ă݂�ƁA�l�Ƃ͂܂�ŁA�H�ꂳ�����Ȃ���A�����ɋ���ȉ��������K�v�Ȃ͂��͂Ȃ��Ƃ����悤�ȂƂ��낪��������B
�������͂��܂���֘A�{�݂ƊŔ��������A���e�͎Y�Ɗ�Վ{�݂ւƕς���Ă���̂ł���B���݂̉���������̍ł����헧���������͂����ɂ���B�ip86�j
�킽���̓y�n���̂��铌���s�̗��扺�����Ɋւ��āA�������c���Ă����B
�����s�̋敔�͌��݉��������y�����قƂ�ǂP�O�O���ɂȂ��Ă���B�������������������Ă��������n��ɑ��āA�P�X�V�O�N��ɓ����ė��扺�����̐ݒu�𑣐i���͂��߂��B
���̒n��͋}���Ɏs�X�����i�s���Ă����A�������̗v�������������B�����j���[�^�E���̂悤�ȋ���c�n�̌��݂��s���āA����ɂ��킹���������������s��ꂽ�B�����j���[�^�E���̓����J�n���P�X�V�P�N�R���ŁA�쑽�������ꂪ�^�]���J�n�����B
�w�����������P�O�O�N�j�x�����̂悤�Ɏ��ȕ]�����Ă���̂́A����Ӗ��Ő����ł���B
�����K���ɂ��āA�����n��ł͗��扺�����ɑ����قǂ悢���Ή^���͂�����Ȃ������B�t�ɂ����A�������������ɂ�镾�Q���A���ꂾ���傫�������Ƃ������Ƃł������B�ip241�j�����x�O���敔�`�����n��̋�ʂȂ��A�S�ʓI�Ɉ�l�Ɏs�X�n�����Ă����B���̂悤�ȋ���s�X�n�����]�܂������Ƃ��ǂ����̋c�_��ʂɂ���A���̒n��̎s�����̋�敪���ɂ�炸�ɗ��扺�����̖Ԗڂň�C�ɕ����Ă��܂��Ƃ����̂ɂ́A������������A�Ǝv���B��Łu����Ӗ��Ő����ł���v�ƌ������̂́A���̈Ӗ��ł���B�ނ���A������㗬��Ȃǂɂ����闬�扺�������Ó����ǂ����Ɋւ��ẮA�����s�X�n�Ƃ͕ʌɕ]�����ׂ����Ǝv���B
�����n��́A�����여��ƍr��E�݈�ɕ�������B�r�썶�݈�͍�ʌ��ɂȂ�B�����여��͍��݁i�k���j�ƉE�݁i�쑤�j�ɕ�������B�����q�s�E����s�E�O��s�͂��ꂼ��Ɨ��̌����������������Ă���B
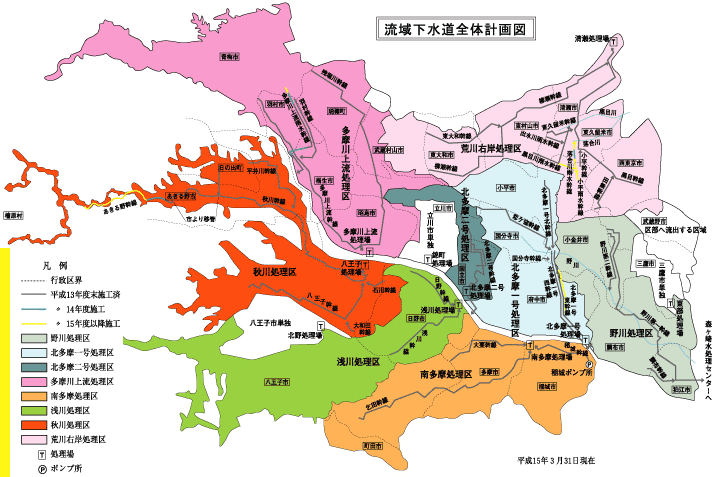
�����s�������ǃT�C�g���i�ꕔ���ρj
�킽�����R�O�N�������Z��ł��������R�s�͍r��E�݈�ɓ���B���̒n��́A��x��E������E���ڐ�E�ΐ_���̗���ł���A�����̒����͐삪�r��i���c��j�ɗ������邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���̒n��͔�r�I���R�ŋ}���Ȏs�X�n�����i�s���Ă���A���̒n����ɂ���P�O�s�����ꂼ�ꏈ������ʂɂ���]�T���Ȃ������B���̂��߂ɁA�u���扺�����v�����ɂ���ĉ���������������Ƃ����̂ɂ́A���������������B
- �����n�捶��
- ������㗬������
- �k�����P��������
- �k�����Q��������
- ��쏈����
- �i����s�P�Ƃ̌����������j
- ������E��
- �H�쏈����
- ��쏈����
- �쑽��������
- �i�����q�P�Ƃ̌����������j
- �r��E��
- �r��E�ݏ�����
- �敔�Ƃ̋��E��
- �i�O��s�P�Ƃ̌����������j
- ������s�̈ꕔ
�����͐���������ɏW�߂�ꏈ������A�����ōr��ɕ��������B���������āA�����s�̐����E��ʌ��Ƃ̒����Ɏ�Ԏ�����悤�ł���B�s�s�v�挈��͂P�X�V�Q�N�P�Q���B
�i5.3.d�j�F�l������
�u���扺�����v������Ȃ��̂ɂȂ肪���ł���A�������A�X�P�[�������b�g��������������Ƃ͌���Ȃ����Ƃ�O�߂łׂ̂��B�܂�A���̒n��ŏZ�������W���Ă���̂��A�܂�ɕ��U���Ă���̂��ɂ���ĉ������̂�������ς��ׂ����A�Ƃ����l�������K�v�ł��邱�Ƃ��킩��B�Z��x�ƌo�ϓI�ɍœK�ȉ������̂�����A�Ƃ������ł���B
�������Ԃŕ����ĉ���������������ɏW�߂�A�Ƃ��������́A�Z�����x�̍����Ƃ���ɓK���Ă���B�Z��������Ȃ�ɓ_�݂��Ă���悤�ȂƂ���ł́A�Nj����Ȃ����ČX�̏Z���ɂ����ĉ������������Ă��܂��l���������ӂ��킵���B�����炭�A���̒��ԓI�Ȍ`�ԁA�_���W���ȂǂŏW���P�ʂɋ����̏������݂���̂��K���ȏꍇ�����蓾�邾�낤�B�������q�͂�����W���������ƌĂ�ł���B�����āA�l�����x�i�Z���̖��x�j�̂������ɂ���āA�œK�̉������̌`�Ԃ����ꂼ�ꂿ�������Ƃ����߂��Ă���B���̍l�����́A���쌧����s�̉������v��́u���A�Z�X�����g�v���˗����ꂽ�Ƃ��ɁA�͂��߂Ē�����ɂ���Ē�Ă��ꂽ���̂ŁA���̌o�܂́w�������F���Đ��̓N�w�x�i�����V��1983�j�ɏڏq���Ă���B���̃��|�[�g�͋�P���s�̎s�����������u�������v�ȂǁA�ƂĂ������[�����̂ł���B
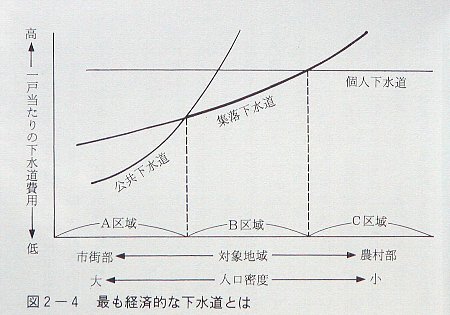
�l�����x�̍����s�̒��S���͌����������A��◣�ꂽ�Ƃ���ɂ����܂��đ��݂���W���ɂ͏W���������A�l�����x���Ⴂ�n��ɂ͌l�������Ƃ����悤�ɁA�g��������ׂ����Ƃ��咣�����B�W���������́A�P�O�O�˂Ƃ��Q�O�O�˂Ƃ��̏W���̉������P�����ɏW�߂ď�������V�X�e���ł���B�i�w���̊��헪�x��g�V��1994 p69 ��}���j������́A�l�������ɓK���Ă���̂͂P�w�N�^�[���iha 100���l���j������S�O�l�ȉ��̐l�����x�̏ꍇ�Ƃ��Ă���i�O�f���ŁA���{�̐l���̂R�`�S�����Y������Ƃ��Ă���j�B��}�̂a�n��Ƃb�n��̋��ڂ̐l�����x�̖ڈ��ł���B
�W�O�N��̂͂��߂ɒ������q�炪��P���s�̊��A�Z�X�����g�Ɏ��g�ޒ��Œ�Ă����A�l�����x�ɂ���ĂR��̉��������g������������́A���̍������E�o�ϐ������Ăł���B�͂��ߔے肵�Ă������ݏȎ��g���u�������}�b�v�v�Ƃ����`�ŔF�߂���Ȃ������B
�������W�҂̑����́A���̋�P���s�̌v��������Ƃ��A�u��펯�v�̈ꌾ�ł����Â��܂����B�������A�R�N��A���̌��ݏȎ��g���A�������}�b�v�����Ɣ��\������܂���ł����B�����ĂāA�������}�b�v�쐬�}�j���A�����P�X�W�U�N�ɏo���܂����B�������}�b�v�Ƃ́A������P���ł�������ƁA�܂��悲�ƂɌ������������W�����������l���������̋敪�������n�}�̂��Ƃł��B�i�w���̂��̐��x�ǔ��V����1990 p59�j�l�������͒������q�̑���ł����āA�s���p��ł��������Ƃ����B�悤����ɁA�e�Ƃ��Ƃɍ������Ƃ������u�����A�ƒ납��̉������������ď��ꂽ���𑤍a�⏬��Ȃǂɕ�������Ƃ������Ƃł���B
�������́u�����v�Ƃ́A�ƒ뉺���̂������A�ƎG�r���i�䏊�A����A���C�j�̗��������킹�ď�������Ƃ����Ӗ��ł���B���j�I�ɂ��P�Ə��Ƃ������̂����݂����̂ŁA����Ƌ�ʂ��邽�߂ɍ������Ə̂��Ă���̂ł���B
�P�X�U�O�N�ォ��V�O�N��ɂ����āA�Ƃ肠�����g�g�C���𐅐�ɂ������h�Ƃ����v���͋����A�������̖��ݒu�n��ɒP�Ə������y�����B�P�Ə��͉ƒ뉺���̂������A�����݂̂��s�����u�ł���B����ȊO�̎G�r���͏��������ɗ����Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂��߂ɁA�䏊�╗�C�̖����E��܂Ȃǂ��͐�E�Ώ��ɒ��ړ���A���{�S���ʼn������i�B ���������h�~�@�i�P�X�V�P�N�{�s�j���ɂ��A�H��A���Əꂩ��̎Y�Ɣr���̋K�����i�݁A�킪���̐��ւ̉��������̑��̂��̂��A��ʂ̉ƒ납��r�o����鐶���r���Ƃ�����悤�ɂȂ����B���̌����́A�܂����l���̂S���̂P�ɑ������鉺���������n�悩��̔r���ł���Ƃ����킯���B�ނ��A�Y�Ɣr�������������̎�v�����̂ЂƂł��邱�Ƃ͕ς�肪�Ȃ��B
���̕\�́A�P�X�X�X�N�́u��������̉���̌����v�i���������j�ł���B
| �@ | �����p | �ɐ��p | ���˓��C |
|---|---|---|---|
| �����r�� | 67.6 | 53.4 | 47.5 |
| �Y�Ɣr�� | 21.1 | 34.4 | 42.6 |
| ���̑� | 11.3 | 12.2 | 10.0 |
�����ł��łɁA�Q�O�O�Q�N�x�̉��������y���A���p�Ґl���ʂɕ\�����f�[�^�������Ă����i�������\�j�B
| ������ | �_�ƏW���r���{�� | ������ | �R�~�v�� | �ȏ�v | �������l�� | ���l�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,257 | 311 | 993 | 38 | 9,599 | 3,070 | 12,669 |
| 65.2�� | 2.5�� | 7.8�� | 0.3�� | 75.8�� | 24.2�� | 100 |
�u�������l���v�Ƃ����̂́A�������E�_�ƏW���z���{�݁E�������E�R�~���j�e�B�v�����g�Ȃǂ̂�����̎{�݂ɂ��Ȃ����Ă��Ȃ��ꍇ�������Ă���B���̉ƒ�ւ́A���A�ɂ��Ă̓o�L���[���E�J�[�Ȃǂŋ��ݎ��ɍs���Ă���̂��낤���A�G�r���͂�����ɂ�����փ^���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̑����ɋ����B���l���̖�S���̂P������B�i�����̃f�[�^�͂P�X�X�X�i�����P�P�j�N�x����P�Ə��͂��łɏ����������Ă��炸�A�f�[�^�̕\�ʂ�������Ă���B�Q�O�O�P�N����͒P�Ə��̐V�݂͎�����֎~���ꂽ�B�܂�A�P�Ə������ݒu���Ă��Ȃ��ƒ�́u�������l���v�Ɋ܂܂�Ă���Ƃ������Ƃł���B�Q�O�O�O�N�̃f�[�^�ł́A�P�Ə���2537���l�A��������914���l�ƂȂ��Ă���B�Ƃ���ƁA�������l���̂W���͒P�Ə��g�p�҂ł��邱�Ƃ��A���������B�j
�P�Ə��̋K��͂P�X�Q�P�i�吳�P�O�j�N�̌x�����߂ɂ����̂ڂ�̂��Ƃ����B�q���W�҂̊Ԃł́A���̒P�Ə��͏@�\���Ⴍ�ے肳��Ă����B��㓖���f�g�p�̎w���������āA�������ɐ�ւ��鏀�������Ă����Ƃ����B�P�X�S�X�i���a�Q�S�j�N���z��@�𐧒肷��Ƃ��A���ݏȂ͌x�����߂̒P�Ə������̂܂܍\����Ƃ��ē���Ă��܂����B����ȗ��A���ݏȂƌ����Ȃ̓꒣�肠�炻���������āA�������������ԔF�߂��Ȃ������B�i�����͒������q�w���̂��̐��xp62�ӂ���Q�l�ɂ��Ă��܂��j
�������A�P�Ə��̏����\�͂̈����Ɖƒ�G�r���̃^�������Ƃɂ���āA�͐쉘���̌����̂ЂƂƂ����悤�ɂȂ��Ă������B���̂��߁A�P�X�W�R�N�ɋc�����@�ɂ����@�������A�W�T�N������{���ꂽ�B�W�V�N���獇�����̐ݒu�ɕ⏕�����o�����ƂɂȂ����B
�������q�́A�P�Ə������F�߂Ȃ��������ݏȂ���������F�߁A����ɁA�⏕���܂ŏo���悤�ɂȂ����o�܂��A���̂悤�ɐU��Ԃ��Ă���B
�P�Ɖ������́A���{�Ǝ��̂��̂ł��B�����������r���[�Ȃ��̂�ݒu����̂�F�߂������łȂ��A���K�͂̍����������邱�Ƃ��ɂ킽���ĔF�߂܂���ł����B�i�������q�w���̂��̐��xp62�j�P�Ə��̋֎~��v�����鐺�͑������炠�����Ă������A���ۂɏ��@�̉����ŒP�Ə��̐V�݂��֎~���ꂽ�̂��Q�O�O�P�N�B�������A�������ւ̐�ւ��́u�w�͋`���v�Ƃ��ꂽ���߂ɁA���݂̒P�Ə��̂��߂ɉƒ�G�r���̃^���������ˑR�Ƃ��đ����Ă���̂�����ł���B�i��ŏq�ׂ��悤�ɁA�������l���̂W�����x���P�Ə��g�p�҂ł��邱�Ƃ���������邪�i�����̂Q����ɑ����j�A�������s�����������ł��āA�������ɐ�ւ��Ă�����̑唼�͖h���������ł���B���扺�����Ȃǂ̋���y�؎��Ƃɂ����ʂ������ɁB �j
�ƒ�p�̍������̑�P�������ݑ�b�̔F������̂́A�P�X�W�T�N�S���A��P���s�Ɋւ��鎄�̒�Ă��o����ĂR�N��ł����B�����s�͗��N�̂P�X�W�U�N�R���ɐ����n��ŁA��������ݒu����ƒ�ɂ��āA�P�Ə��Ƃ̍��z��s���⏕���A�������̐ݒu�����シ�邱�Ƃɂ��܂����B
�Â��āA���N�̂P�X�W�V�N�Ɍ����Ȃ́A�s���������������ƔF���O�ŁA�������ɕ⏕�����o���ꍇ�A���̂R���̂P���������S���邱�ƂɌ��߂܂����B���� ����͓��{�̉������̗��j�ʼn���I�Ȃ��Ƃł����B�i���O p60�j
�����J���ȃT�C�g�Ɍ��݂���ŐV�́u���������v�i�����P�Q�N�Q�O�O�O�j�ɂ́A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă��āA�ˑR�Ƃ��āu�P�Ə��v���V�݂�����邱�Ƃ��킩��B
�V���ɐݒu���ꂽ���S�̂ɐ�߂鍇���������̊����́A�S�����ς�1989�i�������j�N�x��10.0������1999�i����11�j�N�x��R�l������70.9���ւƒ����ɏ㏸���Ă�����̂́A�ˑR�Ƃ��Ēn��i���͑傫���B���̔��������������w���{�̔p�����x�������Ȃ̂����A�u�V�݁v�������ɂ��Ă͍������̊����������A�Ƃ������Ƃ��������������Ă���B�������q�̂悤�ɁA���ݏȂ𒆐S�ɓ��{�̊����͒��N�P�Ə��̐ݒu�������i�߂Ă����̂ł����āA���̂��߂ɗݐς��Ď��ێg���Ă�����̐��́A�P�Ə������|�I�ɑ����̂ł���i���\�A�ʼn��i�j�B�����̍쐬���锒���ނɂ́A������́u�挩�̖��̂Ȃ��v�Ȃ��錾�t�Ȃǂǂ���T���Ă��A�J�P�����Ȃ��B
| �@ | ������ | �P�Ə� | �� |
| �g�p�l�����i���l�j | 957 | 2515 | ���l��12614 |
| �Α��l����i���j | 7.6 | 19.9 | �v27.5 |
| ���v�l����i���j | 27.6 | 72.4 | �v100 |
| �g�p�l���^�ݒu�� | 9.5 | 3.4 | �@ |
| �ݒu���i����j | 101 | 736 | �@ |
| ���v�ݒu����i���j | 12.1 | 87.9 | �v100 |
�Ȃ��A���̕\�ŁA�ݒu����Ŗ�X�����߂�P�Ə����A�g�p�l����Ŗ�V���ɗ����Ă���̂́A�P�Ə������т��Ƃɐݒu����邱�Ƃ������i�P�����̎g�p�Ґ�����3.4�l�j�ɑ��āA�������̓}���V�����̂悤�ȋ����Z��ɂ��ݒu�����^�ݔ������邱�Ɓi�P��ӂ�g�p�Ґ�����9.5�j�f���Ă���B
�S���i�S���������������y���i�s�������c��j���T�C�g���獇�����̍\���}�E�T�O�}��q�����B�i����́A�ЂƂ̗�ł��B�����@������ł͕s���ł����A�ŏ��̂T�l�p�̃R���p�N�g�Ȃ��̂ŁA�P�~�Q�~�P�D�W�����炢�B�X�O���~���x�B�j
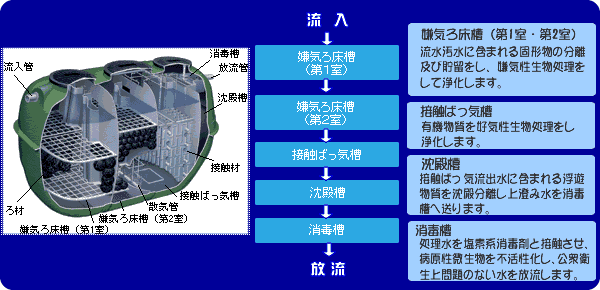
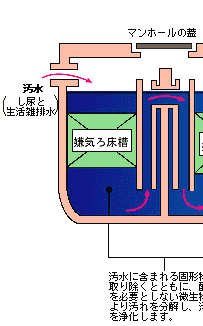 |
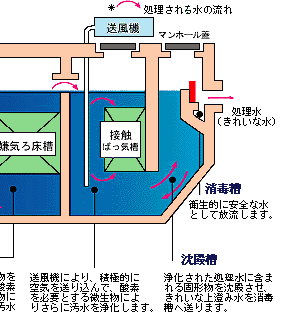 |
|
�u�P�Ɓv�ɂ���u�����v�ɂ���A�����ɔ�������ɐB�����A���A�Ȃlj���������������ɐH�ׂ����āA���ꂢ�ɂȂ������������������Ƃ������̂ŁA���̌����͌����������̏�����̊������D�@�Ɠ����ł���B�����A�e�ƒ�Ŕ����������̑��u�������̂ł��邩��A������x���̌�����m���āA�������ɂƂ��ėL�Q�Ȗ�i�Ȃǂ𗬂��Ȃ����Ɓi�Ⴆ�A�g�C���|���̍ۂ̉��_�j�A�������̐H�ו��ɂȂ�Ȃ������i������܂Ȃǁj�𗬂��Ȃ��Ȃǂ̋֎~��������邱�ƁB����ɁA����I�ȕێ�E���|��A���������ɐB���������ꍇ�̏��u�ȂǓ���I�ȃP�A�[���K�v�ł���i����ێ���Ǝ҂ɔC���邱�Ƃ��A�������\�j�B
���Ƃ��L���s�̃T�C�g�ł́A���Ɋւ��Ďs���ւ��̂悤�Ȍ[�ւ����Ă���B
���͐����Ă��܂��I |
���̂悤�ȓ���I�ȁu�S�Â����v�͂Ƃ������A����I�ȕێ�_���Ȃǂ��ƒ�ōs���͓̂���Ƃ����l���������낤�B�����A�Ђ�����Ԃ��Č����ƁA�����������ɗ����Ă���ƁA�����̕��A�̂��܂��N���ǂ̂悤�ɂ��Ă��邩�ɂ��āA�܂��������S�ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃł���B����͌��S�Ȏ����I�Ȑ������Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B
�e�ƒ낪�������������ɔ������Q��ɐB�����āA������̕��A�Ȃǂ̂��܂������ł���~�j�}���E�V�X�e��������Ă��邱�Ƃ������A���S���Ƃ����l���������낤�B�܂�A���͉��������ł���܂ł̌q���̈ꎞ�I���u�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ����z�I�ȉ��������V�X�e�����Î��I�Ɏ����Ă���A�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B�������āA�����̏o�������̂��ł��邾�������̋߂��ŏ������Ă��܂��A�Ƃ����B����������́A�f�B�X�|�[�U�[�̂悤�ȋ@�B�I�ȏ����ł͂Ȃ��A�������Q�������Ă����Ă���ɏ������Ă��炤�Ƃ����g�����h�̊��o������B
�������A���ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A����ȉ^�]�����Ă��Ă����D�i�������̉�A���[�j�����܂��Ă���̂ŁA����I�ȉ��D�������u�Ђ������v���K�v�ł���Ƃ������Ƃ��B�o�L���[���J�[�ɗ��Ă�����ĉ��D���������Ă��炤�B�ʏ�A�P�N�ɂP��ȏ�̉��D�����Ɛ��|���`���Â����Ă���B
�Ђ������ꂽ���D�́A���A�����{�݁^�����������{�݁^���̑��ŁA�ʏ�̏������[�`���ŏ��������B
�i��5.2.b�߂Œ����w���v���x���Љ���Έ�M�̍�肾�������́A���N���g�̊k�̒�����̂��g�����̂ŁA���ɗD�ꂽ���\�������Ă���B�Έ䎮���̃z�[���y�[�W�ɂ��ƁA�����̐����̑��x������߂Ēx�����Ă���̂������Łi0.3���^���A��ʂ̏��ł͂U�`�V���^���j�A���l�Ȕ����������ݒ����Ă��āA�L�@����H�ׂĂ����B�������I�����Ԃɓ���ƁA�]�艘�D���قƂ�ǐ����邱�ƂȂ��A�P�O�N�ȏ㉘�D�����������ɕ��u���ĉ^�]����������Ƃ����B�������A�������̐����͂���߂ėǍD��BOD 1 ppm���ւ��Ă���B�Έ䎮�̎��ۂ��O���[���E�R���p�j�I���E���|�[�g��������₷���B
�Έ䎮���g���Ă���̌��L�䂪�Ƃ̐Έ䎮�������E�̌��L�́A�����b�N�X�����������ɍD�������Ă�B�������A���̑̌��L�ł͋Ǝ҂ɔC���ĉ��D���������Ă���悤�ł���B�܂��A���܂��^�]���ł����A��J���Ă���P�[�X������悤���B�g�Έ䎮���h�Ō������Č��Ă��������B�j
�ߑ�|����̓��{�ł́A�u�����͉������ŏ���������́v�Ƃ����������g�M�h���������B���������Ă̐M�Ȃ̂����A���j�I�ɂ͊��哱�Ō`������Ă����g�M�h�Ƃ����Ă������낤�B���Ă̏��s�s�łP�X���I���玎�s����I�Ɍ��݂��Ă����ߑ�I�������V�X�e�������f���Ƃ��āA���{�̓s�s�֓�������̂����{�̉��������݂ł����āA�͂��߂́A���Ă̋Z�p�҂̎w�����A������������{�̋Z�p�҂ɂ���Č��݂���Ă����B
�������ɁA���Z�p����{�l���g�ɂ���̂͑����������A�g�l�Ԃ̐����ɂƂ��ĉ������Ƃ͉����h�Ƃ��������I�Ȗ₢��Y�ꂽ�����͔|�̋Z�p�ł������B�܂��A�����ł��������炱���A���₭�Z�p��g�ɂ��邱�Ƃ��ł����Ƃ�������B�]�˂̒��̌@�芄�艺���╳�A��엿�Ƃ��Ďg�p���邽�߂ɐ������Ă����L�ĂȃV�X�e���i���ƒ����E�ڑ��E�����g���Ȃǂ̃V�X�e���j�Ȃǂ��A���j�I�ɐؒf���āA���Ă̓s�s�|���������f�����ڐA�����̂ł���B
���Ɗw���p�ӂ������f�����A���{�̋Z�p�҂����{�Ɍ��݂���B���ۂɂ́A�㐅�����ɂ��A�������͗\�Z�s���̂��߂˂Ɍ�ɂ���Ă����B���̂��߁A���A�엿�̓`���͑�Q������܂Ŏc�������A�f�g�p�̉q���w���Ɖ��w�엿�̓����ɂ���āA���{�o�ς����x�������ɓ��鍠�ɂ́A�قƂ�ǔے肳��Ă��܂��Ă����B�����āA�u�����͉������ŏ���������́v�Ƃ����g�M�h�����������B
�������͊����p�ӂ��A���͂���Ɉˑ����Ď����̕��A�E�G�r���̏��������ցg�ۓ����h����B
�l�������i�������j�́A�����̕��A�E�G�r���ɂ��āA���ȐӔC���Ď����̖ڂ̓͂��͈͓��ŏ��������A�\���ɐ���ȏ������𒆐����Ƃ��ė��p���A���a�E����Ȃǂɕ�������g���Ȋ����I�h�ȏ����n��̌�����B���̓���I�ȑ̌��́A�������r�o������̂ɂ��ĊS�������߂̏d�v�Ȍ_�@�ƂȂ�B
�l���������ӂ��킵���̂́A�Z�����_�݂��Ă���悤�Ȕ_�R���W���ł���A�Z���̎��ӂɏ����Ȑ������Ȃ���A���̐����ł̎��R��p�������҂����B�l����������̕��������Z�����ӂ̐����ɖ߂邱�Ƃɂ���āA�������������ێ��ł��邱�Ƃ����������B�����������̊��𗬂��삪�����ꂵ�Ȃ����ƂɊ�^���Ă������������B���R�A�������̐����ɂ��āA�����̐ӔC�ɂ����āA�S�������ƂɂȂ�B�i���_�̑�1.1���u�킽���̑̌��v�ŁA�c���N�����߂������R�A�n���̓c�ɉ��~�ɂ́A���삪����Ă������Ƃ�������ƋL���Ă������B���R���璼�ڗ���o���Ă��鏬��ŕ��T�O�p���Ȃ������ł���B���̊��Ƃ�����A����������݂Ȃ��̏���ł���Ă����B�[���ɂȂ�ƁA�ǂ̉Ƃł���w����[�ɏo�ĕĂ��Ƃ��ł����B�������̉ƂŎg���킯�ł��邩��A���ꂽ���𗬂��Ȃ��悤�ɋC�����Ă����̂͌����܂ł��Ȃ��B�����������삪�������𐔖{����Ă����B�_�Ɨp���̂��߂̗p���H�͕ʂɈ����Ă������B���ݐ��͕ʂɎR���̐�܂Ńo�P�c�ŋ��݂ɍs�����P�ɒ����Ă������B�j
�l�������ɂ��čl���Ă���ƁA�����ɂ͉��������ɂ��Ă̂��錴���I�͌^�����݂��Ă��邱�ƂɋC�Â��B�����������͂��̔͌^���ƂĂ��Ȃ���K�͂Ɋg�債�����̂ɂ����Ȃ��̂����A��K�͂Ɋg�傷�邱�Ƃɂ���āA�X�̐l�тƂ́A�����̔r�o���̍s���ɂ��ĊS�������Ƃ��ł����A�܂��A�����̐����̏�Ɏ��R��p�������Ă��邱�Ƃ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�����������̌����I�͌^�̓������A�����グ�Ă����B
- �i1�j�@�����̔������ŁA�����ɏ������邱��
- �i2�j�@�ł��邾�����K�͂ł��邱�ƁA�g�̏�̑��u�ł��邱��
- �i3�j�@���R�̏z���ێ����ĉȂ�����
- �i2�j�@�ł��邾�����K�͂ł��邱�ƁA�g�̏�̑��u�ł��邱��
�i5.4�j�F�g�ѕ֊�̏�����
�g�ѕ֊�i�����ł́A�I�}���ƕ\�L����j�ɂ́A������������Ǝv���B�O�߂̍Ō�ŏq�ׂ��悤�ɁA�u���v�Ƃ����l��������������������Ǝv���B�킽���͂����l���Ă���B�ȉ��A���̐߂ł͂킽�����z������]����u�����̃I�}���v�ɂ��āA�ł��邾���q�ׂĂ݂悤�Ǝv���B������A���̐߂͑��̐߂Ƃ͂܂��������i���قȂ�B���̂���ŁB
�Ȃ��A��i4�D4�j���g�ѕ֊�i���܂�j�ŁA�t�����X�E�����E�؍��E���{�́u���܂�v�ɂ��Ċ��q�����̂ŁA��������Q�Ƃ��ĉ������B�i�֑��Ȃ��炱���ł́A�u���܂�v�͊����̂��̂��A�u�I�}���v�͏����I�Ȃ��̂�\���Ƃ������Ƃ�����ŁA�g�������܂��j
�܂��A�I�}���̓������A���q�̂��̂������Ă����B
�l�������i�������j�̂����A�Ƒ��P�ʂ̂��́i�ŏ��K�͂̂��́j�́A���������ŏq�ׂ悤�Ƃ��Ă���I�}���Ƌߐڂ��Ă���B�킽���́A�l�������̏\���ȉ��ǂ������Ȃ���A�����ɂ����ōl���Ă���I�}���ɐ�ւ���K�v�͂Ȃ��Ƃ��v���Ă���B
- �r���ꏊ���A���R�Ɉړ��E�I���ł���B
- �l�i�����Ƃ��Ƒ��j�P�ʂł���B
- �r���p���Ɏ��R�x������B
- �r�����鎞�Əꏊ��I�ׂ�B��r�����āA���r������Ƃ����悤�ɁB
- ��C�̔n���i�}�[�g���j�̂悤�ɁA�r���^���|�Ǝ҂����肤��B
�Ƃ̎��͂Ɏ��R���H�������āA����ɏ[������ȏ�������������āA���R�͂ɂ����҂���Ƃ������͂��炵���Ǝv���B���������āA�l�������͈ێ����Ă����ׂ����ƍl���Ă���B�������A�����ōl���Ă���I�}���́A�킪���A�ڏ������邱�Ƃɂ���āA�M��������엿���ȂǂƂ��Ďg���邱�Ƒ傫�ȓ����Ƃ��悤�Ƃ��Ă���̂ŁA�l�������ƕ��p���Ă悢�ƍl������B �܂�A���������ł킽�����l���Ă���悤�ȕ��A�����V�X�e�����ł���A�i�l�A�����j�������͎G�r���̏��������Ƃ�����̂ƂȂ�ł��낤�B
�����̌g�ѕ֊�i���܂�j�̋@�\�́A��{�I�Ɂg�ȕւȕ֗��߁h�ɂ����Ȃ��B�召�ւ������ɗ��߂Ă����āA���ԂƏꏊ��I��Ŕr������A�Ƃ������ƈȏ�̋@�\�͂Ȃ��B�킽�����z�����Ă���I�}���́A����ȏ�́g���@�\�h���������āA�召�ւ̂��܂��Z�����ōς܂��Ă��܂����Ƃ��\�ɂȂ�悤�ɂ������A�Ƃ������Ƃł���B�g�����A�F����s�m�������Ԃ̉F�����s�����ĉF���D���łł��邾���̏z�n���\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����ۂɍl������悤�ȕ֏��̋@�\�������������h�A�Ƃ������Ɍ����r�e�炵���āA�킽���̈Ӑ}���`���₷�������m��Ȃ��B
�킽�����l���Ă���I�}���͓d�C�i�d�q�j���ł����āA�\�Ȃ�������������s���B�d�C�|���@���x�̑傫���E�d�ʂŎ�y�Ɏ����^�ׁA�l���������ʂł���悤�Ȃ��́B�@�\�������Ă݂�ƁA
�Ȃǂ��A�l������B
- �E�L�̔\�͂����邱�ƁB
- ���o���ۂɕs�������Ȃ��悤�ɏ�����������Ă��邱�ƁB
- ���̕�́A���̂܂܉���Ǝ҂ɏo�����ƒ�؉��Ŏg����B
- �����������邱�Ƃ��l�����邪�A����́g�������h�ɗ����B
�I�}���ɂ́A���݂̓s�s�̐��̂悤�ɉ������Ԃ�O��Ƃ��Ċe��َ̈��ȉ����̒��ɕ��A����������ł��܂��A���̏�ŏ����E��������Ƃ�����\�����������\��������B�I�}���́A�e�l����r�����ꂽ�u�Ԃɂ��̌ʂ̂܂�������������Ƃ��B
���Ƃ��A�����E��E�ꎞ�����Ƃ����悤�ȌʓI�����̋@�\���������I�}�����J�����邱�Ƃ͂ł��悤�B����ɉ����āA�������ɂ��{�i�I�ȕ��������܂ōs���g���@�\�I�}���h���\�ł͂Ȃ����B
���̃I�}���ŏ���������ŁA��ʃS�~�Ƃ��Ď̂Ă�̂ł��������A�l��Ƃ��čė��p����H���ɑ���ׂ�����Ă������B�����܂ł̍\�z�ł́A���̃I�}���͕��A���ł��邾���A���̏����ɕs�����Ȃ�������A�Ƃ������x�̂��Ƃ����q�ׂĂ��Ȃ��B
�������A���Ȃ��Ƃ����^�A�̎��I�Ⴂ���l���āA�킪�I�}���͍ŏ����畳�^�A�����Ĉ�����悤�ɂȂ��Ă���ׂ��ł���B���^�A�������I�ɂ܂������Ⴄ���̂ł��邱�Ƃɂ��ẮA��5.5.a����C�E���E�H�ו��ŏq�ׂĂ���B�A�͑̓��̍זE����ʉ߂��Ă���̂ł����āA�i���N�Ŕr������ł���j�܂��������ۂł���ȏ�ɐ����Ȃ��̂͂Ȃ��قǂ́A�������A���܂��܂ȉh�{�f�Ȃǂ��܂t�̂ł���B
�������Ď��o���ꂽ�A�́A���s���Ȃ��悤�ȏ��u���{����āA�A���Ɨގ��̂������ŗL�����p�����锤�ł���B��ւ͊�{�I�ɂ͔엿�Ƃ��Ă̗��p�ɉ���悢�B������ɂ��Ă��A���݂���ꂪ�s���Ă����ʂ̐��Ő��n���ĉ����ɗ������ƂŔ��߁A�ƒ�r���E�H��r���E�J���Ȃǂ̔��o�R�̕����ƍ������Ă��܂��͍̂ň��̕����ł���B
- ���ƔA�����Ď��o���A���ꂼ���L���Ɏg�p�ł���悤�ɏ������邱�ƁB
�I�}���̗L���ȓ������ő�����������H�v���Ȃ����ׂ����B�I�}���̗L���ȓ_�Ƃ́A
�Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B
- �l�P�ʂ̛��A�̗ʂ����ς邱�Ƃ��ł���B���������̏����������B
- �����ɐ����Ԉȏ�̎��Ԃ̗]�T���Ƃ�邱�ƁB
- ����߂ĉh�{���̍����A���Q�̔엿�����i��i�����j�ƂȂ肤�邱�ƁB
������ɂ���A�킽�������̓��̒��ɂ������̖��ς�U�蕥���K�v������A�g�g�ѕ֊�i���܂�j�͕֏��̊Ԃɍ��킹�ł���h�A�g���A�̏����͉������ɔC����ׂ����h�ȂǁB�g���₷���A���@�\�ŁA���`�ȃI�}�����g���͂��߂�A�֏������r���p��Ƃ��ẴI�}�������̒n�ʂ��l������̂ł͂Ȃ��낤���B�킽���ɂ͂����������҂�����B���[�r���E�g�C���ł���B����́A�H�ׂ邱�Ƃ́g�����h�Ɍ��������A�r���̎��R�x�̊g����߂������̂ł���B�r���̎��R�x�Ƃ́A�g���ł��E�ǂ��ł��E���R�Ɂh�Ƃb�l�R�s�[���ɂ܂Ƃ߂Ă��������B
�������A�킽�������̃I�}�����ǂ̂悤�ɃR���p�N�g�ɍ��@�\�ɂȂ낤�ƁA���R�̏z�n�̃V�~�����[�V�������痣�ꂽ��z�I�ȃV�X�e�����\�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B���̏z�n�ɂǂ����ŃA�N�Z�X����K�v������͂��ł���B
�g���A�̏����͉������ɔC����ׂ����h�Ƃ����g�M�h�ɂ��ẮA��i5.3.d�j�߂��l�������ŏq�ׂĂ������B�ߑ�I�ȓs�s�������̕��y�͂��������P�T�O�N�قǁi���{�͂T�O�N�قǁj�ł���̂ɁA�����������������Ƃ��܂��Ƃ��ȉ��������V�X�e���ł���Ƃ����M�͍L�������킽���Ă���B�����������X�l���x���Ɉ����߂����ƂɁA�����̐l�͂ƂĂ����a�ɂȂ��Ă���B�����A�g�H�ׂ邱�Ɓh�̌������咣����̂Ɠ������x�̏d�v���ŁA�g�r�����邱�Ɓh�̌������咣���Ă����̂ł���B����ɂ̓I�}�����������������Ă���B
�����������ւ̐M�́A������݂���Ō����A���������������ւ̔����ϔC�Ȃ����́A�g�ۓ����h�ƌ����Ă����̂ł͂Ȃ����B�����������������Ȃ��Ă��邩�ɂ��ẮA�m�肽���Ȃ��A�m�点�Ȃ��łق����A�Ƃ����u�����ϔC�v�ł���B���ۂɂ́A�����������͍��|�n�������̂��s���ŋ����g�����������Ƃł���B����ɔ����ϔC���邱�Ƃɂ���āA���łɉ��x���q�ׂ��悤�ɁA�����������̐K�̖����A�g����h�ɗa���Ă��܂��Ă������ƂɂȂ�B
�r�ւ͐����Ƃ��Ă̐l�ԂɕK�R�̍s�ׂł��邩��A�l�ɐ����錻�ۂł���B���̂��Ƃɂ͗�O���Ȃ��B�H�ׂ邱�Ƃ́g�h�i��j�Ƃ��Ĕr���s�ׂ�������B�����܂ł��Ȃ��A�H�ׂ邱�Ƃ͌l�ɐ����錻�ۂł���A�l���ʂɉ�������i�H�ׂ�j�����Ȃ��B�r���s�ׂ������ł���B�������Ɏ��I�s���Ƃ����Ă������낤�B�����A�r���s�ׂ����ՓI�ȋɎ��ł����āA�K���������I�ł���K�v�͂Ȃ��B�����̌��O�֏����J�����҂낰�ł��邱�Ƃ́A���{�̓c�ɂł͂Q�O���I���܂ŏ����̗������ւ̎p�����R�ł������̂Ɠ��l�A�����I�ɂ͉��̕s�v�c���Ȃ��B
�r�����̏����́A�X�l�ɐ��������ʂ̂܂܂ŁA�l�̃��x���ŏ�������̂������Ƃ������I�Łi�Ȋw�I�Ɂj�e�Ղł���B���̂��߂ɂ́A�����ꂽ�l�������i���j������Ƃ��H�v����邱�Ƃ�]�݂����B
��C�̔n���i�}�[�g���j�Ɍ�����悤�ɁA�I�}���ɂ͂��̐��̏����Ǝ҂������\�ł���B�s�s���ʂ̋Ǝ�Ƃ��āA�e�ƒ납��ł�I�}���������i��P�������������A�j���ǂ̂悤�ȃV�X�e���ɂ���ɂ���W�ρE�W�z���A�����엿���i�����Ȃǂɑ�Q�����������A�̔�����B���̐�又���Ǝ҂͊e�ƒ납��Ɣ̔��悩��ƁA��������Ή��邱�Ƃ��ł���B���݁A�S�~�̏W�z���Ȃ���Ă��邪�A����̗ގ��̃V�X�e�����l������B
���R�x�������āA���K�ŁA�o�ϓI���S���y���i���Ă͕��A���L���Ŕ��邱�Ƃ��ł������コ���������j�Ȃǂ́A�I�}���ɂƂ��Ă̗L���ȓ_�����B�������A�l�ޕ��Ղ̋Z�p�ɂȂ肤��̂Łi���ɓs�s�����ł͕K���i�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����j�A�J�����@�͏\���ɂ���B�����A���̎�̖����^�I�}�������i�Ƃ��ē�����A����s�ꂪ�҂��Ă���B
������x���肩�������B�s�s�̌����̕֏�����K�͐������̕����ɂ́A�������͂Ȃ��B�������̂���̂́A�Q�O���I�ɓ��{�̊����|����Y�Ƃǂ��ɂ���čl�����Ă����悤�ȁA��K�͂ȉ��������V�X�e���ł͂Ȃ��A�l�ʂŏ��K�͂ŁA�������G�l���M�[������^�łȂ��ݔ��ł���B���̈�Ⴊ�A�X�l�Ɋ��蓖�Ă��I�}���Ə��K�͏ݔ����x�[�X�ɂ������A�����V�X�e���ł���B�ʂ̃I�}�������@�\�ɂ��āA���K�́E�����ȏ����V�X�e���ɂ���A�Ƃ��������ɂ͏�����������Ǝv���B���̕����̋��݂́A���炪���A�͖��Q�^�h�{�L�x�ł���A�Ƃ����_�ł���B�����āA���̕����ɂ́A���K�́E�����̃n�[�h���W�z����\�t�g�E�V�X�e�����K�{�ł���B
���剻�����s�s�����W�ɂ́A����ȉ������V�X�e�����K�{�ł���B�������A����͓s�s�S�̂̉����r���E�p�M�̂��߂ɕK�v�Ȃ̂ł����āA�����̋������́g�h�i��j�Ƃ��Ẳ������ł���B�킪�I�}���͂��̉������V�X�e���̂Ȃ����盝�A�������\�Ȍ����������邱�Ƃ�_�����̂ɂȂ�ł��낤�B
�i5.5�j�F�������ӂ��ތ���
�i5.5.a�j�F��C�E���E�H�ו�
�킽�������l�ԂɂƂ��āA�����Ƃ��Đ����Ă����̂ɂǂ����Ă��K�v�Ȃ��̂�������A��C�E���E�H�ו��ƂȂ�B
��C�i���̒��̂Q���قǂ��_�f�j�͌ċz�ɂ���Ĕx����̓��Ɏ�肱�܂��B��C���̂ɂƂ��ĕK�{�ł��邱�Ƃ́A�ق�̐����Ă��ǂ̒����Ŏ��S���Ă��܂����Ƃ���A�^��̗]�n�͂Ȃ��B�����A�_�f�͑̓��ŒY���������g�R�₵�āh�G�l���M�[�����o���̂Ɏg����Ƃ����邪�A���̓����̌��@���Ȃ����̂悤�Ȍ��r�ŋ}���Ȍ��ʂ������炷�̂��A������ƍ��_�������Ȃ��قǂł���B
�l�b�g��ɁA�ᐙ���p�i��勳���j�u�@��w���猩���]���v�Ƃ����_�����������B���̂Ȃ��́u�]�Ǝ_�f���S�v����B
�]�̍זE�͂ǂ̂��炢�_�f���R�Ɏア���B�ċz��~��A�e����E�g�D���Ɏ���܂ł̎��Ԃ��r����ƁA��]�̕\�ʂɂ����]�玿�́A�킸���T���̌ċz��~�ōזE������ł��܂��B��]�玿�͐S������ł����������ł���A������������Ƃ��̕����̌����ʂ��s�����Ă���B�����ł�20���ȏ�זE�������邱�Ƃ��ł��A�S���قړ��l�ł���B�זE�ɂ���Ă͉����Ԃ������Ă�����̂�����A�]�̍זE�����Ɏ_�f�̌��R�Ɏア���Ƃ�������i�]�Ǝ_�f���S�j�B���̗��R�i�����@���j�͂悭�킩��Ȃ����A�_�f�������f�����ƁA�]�זE�͂킸�������Ŕj���̂ł���B�]�������Ɍ������_�f���g���A�Y�������i�u�h�E���j��R�₵�Ă��邩���A�z�������B�����āA���̔j��͔�t�I�ł���B
��]�玿 ���� �S�x ���i�� ���זE �T�� 20���ȏ� 10-20�� 2-4���� 20-70����
�������ċz���s���A�_�f����荞�ݒY�_�K�X�Ȃǂ�̊O�ɏo�����Ƃ𑱂��Ă��Ȃ��ƁA�����͈ێ�����Ȃ��B�u�_�f�̗���v�������āA����̂킸�������̑肪�v���I�ɂȂ�قǁA�����z���͐[���ȋ@�\��S���Ă���Ƃ�����B�̓��Ɏ_�f�𗭂߂Ă������Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ����Ă��������낤�B�i�Ȃ��A��C��21���قǂ̎_�f�͈�x�x�ɓ����đ̓��ɂ��̈ꕔ���z������A�ċC�Ƃ��đ̊O�ɏo�����Ƃ�17�`18�����x�ɂȂ��Ă���B�l�H�ċz�̌��Ό����L���Ȃ̂ł���B��C���̎_�f���U���ȉ��ɂȂ�ƒ����ɒ������̊댯�����j
���͐������܂Ȃ��Ǝ��Ɏ���B���̐g�̂ɂƂ��Ă̏d�v���́A�זE�t�E���t�Ȃǂ̑啔�������n�t�ł��邱�Ƃ���A�g�̍\�������Ƃ��đ��ʂɎg�p����Ă���i��U�O���j���Ƃ��炢�������[�������B�������A���ꂾ���ł́A�Ȃ��A�펞�i�����Ԃ����Ɂj�����ێ悪�K�v�Ȃ̂��A���̍����������d�v�����N���ł͂Ȃ��B�ʏ�P���Q�`�R���b�g���̐���ێ悵�Ă���Ƃ����B�����Đێ悳�ꂽ���́A�A�E���E��ւɂ���Ă������̊O�ɔr������Ă���B���Ƃ��A���͍����z��a�Z���^�[�i�m�b�u�b ���{���c�s�j�́u�H���ɂ��āv�Ƃ����[�փT�C�g����B
�����̏d�ɐ�߂銄���͐��l�ŕ���60���`66���ł��B���̂R���̂Q�͍זE���t�ŁA�c�肪�����A�g�D�ԉt�Ȃǂ̍זE�O�t�ƂȂ��Ă��܂��B�J���Ȋw�������ҁw�J���q���n���h�u�b�N�x�i1988�j�ɂ��ƁA���l�P���̔N���ς̐��ێ�ʂ�2.6���b�g���Ƃ��A���̔r�o�́A�A 1500�C�� 600�C�ċC 400�C�����̑� 100ml �Ƃ��Ă���B
���͒Z���Ԃő̓��ɋz������āA�_�f��z�����ꂽ�h�{�f�����t�Ȃǂɗn�����A���ׂĂ̍זE�ɉ^�т܂��B�܂��V�p����̊O�ɉ^�Ԃ��Ƃ��d�v�Ȗ�ڂł��B���Ȃǂł̑̉��̒��߁A�̉t�̐����̃o�����X��ۂ������S���Ă��܂��B
���l�͂P���ɐH�����̑�����1.3�`1.5���b�g���A���ސ����Ƃ���1.2�`1.5���b�g���̌v2.5�`�R���b�g���̐�����ێ悵�A�قړ��ʂ�r�����܂��B�ʏ�A�r���ʂ̖�R���̂P������f�������玩�R�ɔr������A�c��͔A�Ƃ��Ĕr������Ă��܂��B�̓��̐����͈�����r�A�Ȃǂɂ���Ĉ��ɕۂ���Ă��܂����A�̓��̐�����10����������Ɛg�̋@�\�Ɉُ킪������A20����������Ǝ��Ɏ��邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ɐ����̐ێ�͑�ł����A������i�g���E�����܂ސ��������͈��݂����ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�iNCVC�H���ɂ����j
����2.5���b�g���̐���ێ悵�A�����A�Ƃ��Ĕr������ꍇ���l����B
�A�̒��ɑ���E���ʂ́g�V�p���h���n�������܂�Ĕr�������B���́A�V�p���͂��邱�Ƃɂ���āA�g�̊����ُ̈�����o����A�����͂��Ȃ��݂��B���̏ꍇ�A�d�v�Ȋϓ_�̂P�́A�A�i���������j�͂�������̓��Ɏ�荞�܂ꂽ�����̂����g�p�ς݂̂��́��V�p���𐅗n�t�Ƃ��đ̊O�ɔr�o���Ă���Ƃ������Ƃł���B�l�̂Ƃ��������V�X�e���ɂƂ��Ắu�S�~�̂āv���s���Ă���Ƃ����Ă悢�B
�����ЂƂd�v�Ȋϓ_�́A�A�i���j���p�M���s���Ă���Ƃ������Ƃɒ��ڂ��邱�Ƃł���B���Ƃ��A�P�T���̐�������łR�V���̔A��2.5���b�g���o�����Ƃ���A
�i37-15�j�~2500�~1��55000cal��55kcal�̔M�ʂ�̊O�Ɏ̂Ă����ƂɂȂ�B��b��ӗʁi���Ï�ԂŐS���E�x�E�����Ȃǂ̊����ɕK�v�ȃG�l���M�[�j�� 1500kcal �ȂǂƂ����邩��A����ł́A�p�M�͂܂������s�\���ł���B
���̋C���M���傫���i25����583cal/g�j���Ƃ𗘗p����������p�ɂ���ĕK�v�Ȕp�M�����߂����B���Ƃ��A��b��Ӓ��x�̔M�ʂ̔p�M�ɕK�v�Ȋ��̗ʂ́i���ɂ��ׂď�������Ƃ��āj
1500��0.58��2590����2.6���b�g���ƂȂ�B�������A��b��ӂ����ׂĔM�ʂɂȂ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�������x�̔����ʂ��K�v�ł��邱�Ƃ͗�������悤�B���{�N���[������̃T�C�g���u�Ă̌��N�`�F�b�N�g���̘b�h�v�Ƃ����A�����ɂ����̋Ǝ�炵���L��������A
���ϋC����29�x�̉ĂɁC�̏d65kg�̐l�������Ŋ�������ƁC����̊��̗ʂ�3���b�g�����炢�ɂȂ邻���ł��D�����������̍H���8���ԓ����ƁC12���b�g���ɂ��B���邻���ł��D�Əq�ׂĂ��āA�����⋋�̏d�v���������Ă���B�������X�|�[�c�̏ꍇ�����l�����A���Ԃ�����P���b�g�����x�̔���������A�K�v�Ȕp�M���s���Ă���B
�g�̊����̃G�l���M�[�͊�{�I�ɉ��w�I�G�l���M�[�i���Ƃ��u�h�E���������Ă���G�l���M�[�j�ł����āA����̉���i�u�h�E�����_������ߒ��j�̓G�l���M�[�����o�����i���Ƃ��ؓ������k������j�A���̂������M���B���̔��������M�����ʓI�ɔr�o���Ă��Ȃ��ƁA���̕��ʂ̑̉��̋}�㏸���܂˂��A����Ȑ����������s�\�ɂȂ�B�M�e�ʂ̑傫���������t�Ƃ��ďz���Ă���A���M���ʂ��璼���ɔM���ړ������A�Ö��ő̕\�ʂ֔M��`���E�t�˂����đ̊O�ɓ����������łȂ��i�������g�̂̓����ɐÖ����O���ɋ߂����z���Ă���͍̂����I�ł����j�A���������Ȃ����Đ��̑傫�ȏ����M�𗘗p���Ĕp�M����B����ł����Ƒ̉���ۂ@�\�ł���B�g�̂�M�@�ցi�G���W���j�ƌ����Ƃ��A�p�M������ɓ����Ȃ��Ƃ������Ɂg�Ă����Ă��܂��h���ƂɂȂ�A���Ɋ댯�ł���i�M���ǂ͂���ł���j�B
�ȏ���܂Ƃ߂�ƁA
���͐g�̂̍\���v�f�Ƃ��Ă��d�v�����A�펞�ێ悵�r������Ƃ����z�����s���Ă��邱�Ƃ̔F�����d�v�ł���B�V�p���͎�Ƃ��ĔA�ŁA�p�M�͎�Ɋ��ő̊O�Ɏ̂ĂĂ���B�Ȃ��A��ɍĘ_���邪�A�A�͑̓��̍\���v�f�ł��������̂́g�V�p���h��n�t�Ƃ��ėn�����đ̊O�֔r������̂ł��邪�A��ւ͏����ǂ�ʉ߂��Ă��đ̓��Ɏ�荞�߂Ȃ������s�p����r�����Ă���̂ł����āA���̏d�v�x���܂������قȂ�B�A�̔r���̕��������Əd�v�ł���B�i���̓_�Ɋւ��āA��5.4���g�ѕ֊�̏������̂Ȃ��ŁA�A�ƕ��̕�������̈Ӗ����q�ׂĂ������B�j
�H�ו��ɂ͑��l�Ȃ��̂����邪�A�G�l���M�[���ƂȂ�Y�������E�����ȂǂƁA�g�̂������^���p�N���A���ߋ@�\���͂����r�^�~���E�~�l�����̂R�ɑ傫����������B�������A���̕��ނ͑�G�c�Ȃ��̂ŁA�^���p�N���̓G�l���M�[���Ƃ��Ă��g���邵�A�����͍זE��������̂Ɏg���邵�A���t���ɂ��܂܂�i�������b�Ƃ��R���X�e���[���Ƃ��j�A���n���r�^�~���i�`�A�c�A�d�A�j�j����������������d�v�B
���āA�H�ו������������A�����t�ƍ������킹�A�������Ĉ݂ɒB����B�݂ł͒`���������y�f�i�y�v�V���j��ݎ_�i���_�A�J���V�E����n�������ƁA�ۂ̔ɐB��h���j�����傳���B�H�ו����ǂ�ǂ�̊���̂��̂ɂȂ邱�Ƃ́g�q�f���h�ł��Ȃ��݁B
�P�Q�w���ŁA�X�t�E�_�`�����傳���B�X�t�͓����E�����E�^���p�N������������t�A�_�`�͎��b���z�����₷������B�����܂ł́A�قƂ�Njz���͍s���Ȃ��B
�����Œ��t�����傳���B�Y�������̓u�h�E���i�O���R�[�X�j�ɁA�����͎��b�_�ȂǂɁA�^���p�N���̓A�~�m�_�ɕ��������B���q�ʂ̏����Ȍ`�ɕ��������B�����āA�����O�тȂǂ̔��בg�D�ɂ����čזE����ʂ蔲���āA�̓��Ɏ�荞�܂��B
�咰�ł́A�����ŋz��������Ȃ��������E�~�l�����Ȃǂ��z������A���݂��Ă��鑽���̒����ۂ̓����ɂ���Ă���ɕ����E���y���i�݁A�z�����s����B�c�]���A��ւƂ��Ĕr�������B
�H�ו��̓b�������b���^���p�N�������q�ʂ��傫�����Ă��̂܂܂ł͍זE����ʂ蔲���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߂ɁA���q�ʂ̏����ȁg�����h�i�l�̂��č\�����邽�߂̌����j�ɂ܂ŕ�������ċz�������̂ł���B�z�����ꂽ�u�h�E���E�A�~�m�_�E���b�_�Ȃǂ͌��t����p�ǂɂ���đ̓��̕K�v�Ȍ��A�������։^���B�������ɏ���ꂽ��A�����ߒ����ւăq�g�Ǝ��̃^���p�N�ȂǂƂȂ��Đg�̂��\������i����������Ă��l�����ł���j�B
�����ǁi���|�݁|���|���j�͊O�E�ƒ��ڂȂ����Ă���A��5.1�߂ŏ����ǂ�
�A���ɂƂ��Ă̓y��ɑ���������̂������ǂƂ��đ̓��Ɏ�荞�݁i���t����n�܂��āA�y�뒆�̔������ɑ������鐔�X�̏����y�f���A�����ǂ̒��ł͂��炢�Ă���j�Ə��؈��w�����w�Ɋ�Â����̊�b���_�x����̈��p���������B�u�̓��Ɏ�荞�܂ꂽ�O�E�v��ʉ߂��āA�̓��Ɏ�荞�܂�Ȃ������c�]����ւł���B�܂�A��ւ͔A�ƈ���āg�̓������̔p�����ł͂Ȃ��h�̂ł���B���������āA�r�ւ͎�荞�܂�Ȃ������H���c�]�ɂ����Ȃ��̂ŁA�r�ւ��邱�Ɓi�֔��j�͂���قNjً}�Œv���I�Ȗ��ł͂Ȃ��B���̓_�́A�r�A���邱�Ɓi�A�j�̐[�����Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��B�A�͔A�ŏǂɂȂ���v���I�ɂȂ邱�Ƃ������B
�i5.5.b�j�F�A���E�ہE�Í�
�A����������������_�������Ƒ傢�ɈقȂ��Ă���B�A���͗t�̗t�Α̂ŁA���z�����A�Y�_�K�X�A���ɂ���āA�b������������B
�t�̂̐��@�{�@�Y�_�K�X�@�{�@���ʎq�@�@���@�@�u�h�E���@�{�@�����C�@�{�@�_�f
���̔����͌��ʎq���z�����Ă��锽���i�z�M�����j�ł���B�u�h�E���P���q�ɂ��āA��16�̌��ʎq���z������Ă���v�Z�ɂȂ�Ƃ����B�㎮�͂��̍ŏI���x������킵�Ă���ɉ߂����A�r���ɁA����߂ĕ��G�ȑ����̔�������������Ă���B
���̓r���̔����ߒ���i�s�����邽�߂ɂ́A�㎮�̌��ʎq�Ƃ͕ʂɁA�u�h�E���P���q������32�`44�̌��ʎq���K�v�ɂȂ�Ƃ݂�����B��҂̌��ʎq�́u�������̖��ɂ͗��������A���ǂ͔M�ɂȂ��Ă��܂������ƂɂȂ��v�i���ؑO�f��p103�j�B���́A�������̉��w������i�s������̂Ɏg������ʎq40�قǂ́A���M�������s�������ƂɂȂ邩��A���̔p�M�����ɍs��Ȃ��Ɣ����͂����~�܂��Ă��܂��B����ǂ��납�A�t�Α̂�j��i�Ă��Ă��܂��j���ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B���̔M�ʂ͐����q128�`175������������ۂ̏����M�ɑ�������Ƃ����i��p104�j�B�����܂ł��Ȃ��A���̐��̏��������́A�t�̗����ɑ������z���Ă���C�E�ōs���Ă������U��p�ł���A�������̉��w�����ɔ����Ĕ�������M���A�f�����p�M���邽�߂̕K�R�I�ȍ�p�ł���B�����炠�����Ă��������A�C�E�Ő����C�ƂȂ��đ�C���֏��U���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł������B
�܂�A�u�h�E���́g�����Ƃ��Ă̐��h�����ł͑���Ȃ��̂ł����āA�������̉��w�������i�s���邽�߂ɂ́A�g�����Ƃ��Ă̐��h�̂Q�W�{���x�̐����K�v�Ȃ̂ł������i�g�����Ƃ��Ă̐��h�̓u�h�E���P���q������U���q�K�v�j�B�Ƃ��낪�A���ۂɂ́A�������ŗt�̗t�Α̂��z��������́A����̔g���̂��́i450�C680nm�j�ł����āA����ȊO�̂��͔̂��˂���邩�z�������B�z�����ꂽ���z���͔M�ƂȂ�B�܂葾�z���Ŗ��ʂɒg�߂��邱�Ƃ��A���Ȃ肠��킯�ł���B����ɂ�鉷�x�㏸��p�M���邱�Ƃ��v�Z�ɓ����ƁA�g�����Ƃ��Ă̐��h�̖�P�O�O�{�̐����K�v�Ƃ݂�����i��p108�j�B
�v����ɁA�������Ƃ�����Ղ̂悤�ȃu�h�E�������ߒ���i�s������ɂ́A�����Ƃ��Ďg���ēb���̒��ɌŒ肳��鐅�̂P�O�O�{���x�Ƃ݂����鑽�ʂ̐����A
���@�@���@�@�ۊǑ��@�@���@�@�t�@�@���@�@�C�E
�i�����́A�������Ɋւ���l�@�́A�܂��������؈��w�����w�Ɋ�Â����̊�b���_�x�Ɉˑ����āA������܂ݐH�����Ȃ���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��B�킽���̏��q�ɂ�������������Ƃ���A�킽���͂܂��u�G���g���s�[�v�Ƃ��������x���o���Ă��Ȃ����Ƃł���B
���؈����ˋ������̂͂P�X���I�㔼�Ɋm�������M�͊w�̏��@���A�����G���g���s�[����̖@���ł���A���̖@�����g���ՓI�Ȍ����h�Ƃ��闧�ꂩ��i����ȊO�̗���́A�܂����蓾�Ȃ����j�A���͍l�@��W�J���Ă���B�܂�A�u�G���g���s�[����̖@���v���������̉ߒ��ɓK�����Ă݂��ꍇ�ɁA�ǂ̂悤�ȁA�܂������Ă��Ȃ��������Ƃ������Ă��邩�A�Ƃ������ӎ��ł������i�Ɛ��ʂł���j�B�t�Ɍ����A�ÓT�����w�̌����Ƃ��Ċm�����Ă���͂��́u�G���g���s�[����̖@���v���ꕔ�̕����w�҈ȊO�ɂ͏\���ɗ�������Ă��炸�A�������ߒ��̌����ɐ�������Ă��Ȃ������A�Ƃ�������������ƌ����悤�B�j
�A���̌������ŁA�Y�_�K�X����荞��Ńu�h�E�����ł���i�Y�_�����j���Ƃ́A��Ղ̂悤�Ȃ��Ƃł��邪�A�������A�A���̓u�h�E���i�f���v���j�����Ő����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����i�⑼�̐����j�Ɠ������A���̍זE���\�����邽�߂ɂ̓^���p�N���⎉����K�v�Ƃ���B����炷�ׂẮA���̐����Ɠ��l�ɍזE���ō�������Ă���B���̌����ƂȂ鐅��{���͍�����A���̓��Ɏ�荞�܂�A�u�h�E���̕����ߒ��Ő��܂�鉻�w�I�G�l���M�[�𗘗p���č�������B
���ƒY�_�K�X�E�_�f����Y�f�A�_�f�A���f�͓����邪�A�^���p�N����j�_�Ɏ�v���f�Ƃ��Ċ܂܂�Ă��钂�f���ǂ�����R�����Ă��邩�����ł���B���f�͋�C���W�����߂钂�f�K�X�m2�Ƃ��āA�L�x�ɂ���̂����A�m2�����Ɉ���ŁA�ʏ�̐����͂���ڗ��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�m2���퉷�ŕ����ł���̂́A�}���ȐA���̍��ɋ������Ă��鍪���ۂȂǓ���ȍۂɌ����Ă���B���̓��������f�Œ��Ƃ����B
�܂�A���f�Œ�ۗނɂ���Ă���ꂽ�A�����j�A�Ȃǂ̗L�@���f�����Ƃɂ��āA�A���������H�ׂ铮�����A�K�v�ȃ^���p�N���⎉����j�_�Ȃǂ�����Ă���B�܂�A���f�Œ�ۂ��Œ肵�����f�������̑̂̒����A�H���A���ŏz���Ă����̂ł���B�䂦�ɁA�n����̒��f�����������ɂ���Ăǂ̂悤�����f�z�����s���Ă��邩�A�Ƃ����ϓ_���d�v�ƂȂ�B
�l���A��엿�Ƃ��ėp���邱�Ƃ́A�ߑ�ȑO�̐��E�e�n�̔_�Ƃōs���Ă������A���q�̂悤�ɁA�����|�ߐ��̓��{�قǛ��A��엿�Ƃ��Ďg���Љ�I�V�X�e���𐮂��A�O�ꂵ�Đ������Ă������͂Ȃ��B
�P�X���I���܂ł͒��f�엿�Ƃ��ėp����ꂽ�͓̂��A�����L�@���엿�����ł��������C�P�W�O�Q�N�Ƀy���[�ŃO�A�m�i�C�����̑͐ϕ��j����������Ĕ엿�ɗ��p����͂��߁C�܂��C�R�O�N����ɂ̓`���̃`���ɐ� �ma�m�n3 ���엿�Ƃ��ė��p�����悤�ɂȂ����B�i���}�S�Ȏ��T�u���f�엿�v���ڂ��j�O�A�m�͂����܂ł��Ȃ����A�`���ɐ������̕��E�C���������ɂȂ��Ă���ƍl�����Ă���i�ɐ̗R���ɂ��Ă͖��𖾂ȓ_����B�Ȃ��A�����E�l�Ԃ̕�����ɐ��ł��錻�ۂ́A���̗��R�͕s���Ȃ���A�Â�����m���Ă����B���{�ł��A�Â��_�Ƃ̏����Ɍ������ł��Ă��邱�Ƃ��]�ˊ��̕����ɏo�Ă���B����́A�ɉ��ۂ̓����ł��邱�Ƃ���ɕ��������B�Ζ�̌����Ƃ��Ē��ڂ���Ă����̂ł���B���F�Ζ�͏ɐ�75%�E����10%�E�ؒY15%�������������́i�䗦�͂P��j�B�j
���f�z�������ۂȂǂ̒��f�Œ�ۂ̓����ɂ���Ă��邱�Ƃ��͂����肵�Ă����̂́A�P�X���I���ł����i���f�Œ�ۃ��]�r�E�����������ꂽ�̂��P�W�W�W�N�j�B����ƁA�K�R�I�Ɏ��̂悤�ȏd��Ȏ����ɐl�ނ����ʂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���Ȃ킿�u���̒��f�Œ�ۂ̓����ɂ���Ăł���A�����j�A�Ɏn�܂�L�@���f�ȊO�ɂ́A�n����̐��������p�ł���L�@���f�������͑��݂��Ȃ��v�Ƃ��������ł���B�������A�ߋ��R�T���N�̐����j�̂Ȃ��Œ�������Ă���L�@���f�i�n��E�n���E�C�j�𗘗p����Ƃ��Ă��A�l�ނ̐l���}���́A�`���ɐȂǂ��@��s��������́A���f�Œ�ۂ̍��o���L�@���f�̗ʂɂ���ē��ł��ɂȂ邾�낤�Ƃ����ߊϓI�ȗ\�����������B
�Ȋw�҂��������f�z�̌o�H���q�����킹�n�߂��Q�O���I�����A�ނ�̓p�j�b�N�ɏP��ꂽ�B�͔��̌@���ꂽ�������f�����ł͋}������l�����x���邾���̔엿���\���ɍ��Ȃ��Ƃ����x����������ꂽ�̂��B�P�X�O�O�N�㏉���ɉp���̗L���ȉȊw�҃T�[�E�E�C���A���E�N���[�N�X�������h����������Ɍ����������̒��ōr��������i��`���o���đ�ʋQ����x���������ƂŁA���̌��O�ɂ��Ȃ�̐M�ߐ����^����ꂽ�B�����̉^����[���f]�K�X���痘�p�\�Ȓ��f�����o����킸������ނ̓y��������A���f�Œ�ۂ̊����ɂ������Ă���Ƃ����̂��B�i�w�n�������̋��فxp121�j�Q�O���I�n�߂́A�H�Ɩ�肾���łȂ��s�m�s�Ζ�̌����Ƃ��ẴA�����j�A�����߂鍑�ƓI�v��������ł������i��P�����E���͂P�X�P�S�`�P�X�N�j�B
���̂悤�ȏ�̒��ŁA�A�����j�A�̐l�H�����̌������e���ŕK���ɍs���A�h�C�c�̃t���b�c�E�n�[�o�[���A�����j�A�����i�T�O�O���A�P�T�O�`�Q�O�O�C���A�I�X�~�E���n���G�}�j���s�����̂��P�X�O�W�N�A���̍H�Ɖ��͂P�X�P�R�N����ł���B����ɂ���ď�q�̂悤�ȁu���f��@�v�͍�������A�엿�H�Ƃ����E�I�ɗ����ƂȂ肻��͓����ɉΖ��̕���Y�ƂƂ��Ȃ����Ă����B���̏́A���݂Ɏ���܂Ŗ{���I�ɕς���Ă͂��Ȃ��i�l�ނ͍����E�������ł̒��f�Œ肵���ł��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��܂߂āj�B
�i�w�n�������̋��فx�͂e�D�n�[�o�[���u���f���Œ肵���j�v�Ƃ��ďЉ�Ă��邪�A�����ɔނ͑�P�����E���ɂނ��ēŃK�X�������s�������Ƃ������Ă���B�n�[�o�[���P�X�P�X�N�Ƀm�[�x�����w�܂���܂����Ƃ��A�u�����I�ɂӂ��킵���Ȃ��v�Ƃ��čR�c�̎��ނ������t�����X�l�Ȋw�҂������Ƃ����B
�n�[�o�[�͓ŃK�X�������s�������R�����̂悤�ɐ������Ă���Ƃ����B�u���w����̋��|���푈�̒Z���I���������炵�đS�̓I�ȋꂵ�݂�����������v�Ɓi���Op123�j�B����́A��Q�����ŁA�ČR���L���E����Ɍ����𓊉��������Ƃɂ��āA����𐳓�������̂Ɏg��ꂽ�_���Ɠ���ł��邱�Ƃɋ����B�j
�ۗށE�ۗ��@������A���̎��́E�͑́E�r�����Ȃǂ͍����E�~�~�Y�E�����ȂǂɐH�ׂ�ꂽ��A�y���̐^�ۗށE�ۗނɂ���āA����ɕ������i�ށB�����́A���x���̈قȂ�u�����ҁv�����̐H���A���̋�����Ƃɂ���āA�f���v����^���p�N���̋��啪�q�͂����ɕ��q�ʂ̏����ȕ��q�ɕ�������A�����z�̍Œ�ӂ܂œ��B����B
�A�����������ɂ���ĒY�_�K�X�Ɛ����獇�������f���v���ނ́A���l�Ȑ����́g�ċz�h�ɂ���čŏI�I�ɂ͒Y�_�K�X�Ɛ��ɖ߂�B�ۗށE�ۗނɂ����Ă��́A�ʏ�̎_�f��K�v�Ƃ���ċz�i�D�C�ċz�j�ȊO�ɁA�A���R�[�����y����_���y�Ȃǂ̌��C�ċz������B���Ƃ��A�A���R�[�����y�̓O���R�[�X���G�^�m�[���ɕς��A�Y�_�K�X��������B���^�������ۂɂ�郁�^���K�X�̔���������B��C���ɏo�����^���K�X�͍ŏI�I�ɂ́A�_������ĒY�_�K�X�ɕϊ������B�Y�_�K�X�͋�C���ɏo��ꍇ�����邵�A���ɗn���ΊD��ȂǂɎ�荞�܂�邱�Ƃ�����B���ꂪ�Y�f�z���ł���B
�^���p�N�����\�������v���f�����f�m�ł������B��C���̒��f�K�X�͒��f�Œ�ۂɂ���ăA�����j�A�ɌŒ肳��A�������p������̂ł������B��������_�ɂ��Ă��ׂĂ̐����Ƀ^���p�N����j�_�̌`�Œ��f�͍L�����Ă����B�r�����E���̂̃^���p�N�ނ́A�ۗށE�ۗނ̕������ăA�����j�E�����ɂȂ�B�A�����j�E�����͐A���ɉh�{���Ƃ��ċz�������B�ɉ��ۂɂ���ďɎ_���Ɏ_������Ă���A���ɗ��p�����ꍇ������B�Ɏ_���ڒ��f�K�X�ɂ��Ă��܂��E���f�ۂƂ������̂����݂��Ă���B����́A���f�Œ�ۂƔ��̓����i�Ɏ_�����m2�j�����Ă��邱�ƂɂȂ�B�Ɏ_���͐��ɗn���čŏI�I�ɂ͊C�ɒ~�ς����B���������ĒE���f�ۂ����f�K�X�Ƃ��Ē��f����C���֕��̂͏d�v�����f�z���̈�Ȃ̂ł���B
�H�ƓI�Ȓ��f�Œ肪�s���o���Ă܂��P�O�O�N���o�Ă��Ȃ��B�������A�l�ނ͖��s���ɉ��w�엿����ɂ��邱�ƂɂȂ����̂ł���B���ʂȎ{����A�����������̕s�\�������i�������D����A���f�E��������邱�Ƃ�������Ƃ͑�5.3.b�����������ŏq�ׂ��j�A����������n���̏Ɏ_���ނɂ���āA�Ώ��E���p�̕x�h�{���������炷�B���A�E�䏊�S�~�Ȃǂ́A���ʂ̎{��ɂ���ĉ\�ɂȂ�����ʂ̔_�Y�����`��ς��ĉ����ɓ����Ă������̂ɂق��Ȃ�Ȃ����̂ŁA���ʂȎ{��Ɖ����������̕s�\�����ɂ��������́A�[�����I�Ɋ֘A���Ă���B
�^�ۗނ̓L�m�R�Ȃǂ��܂ސ^�j�����ŁA���j�����ł���ۗނƂ͂܂�ňႤ�����ł���B���A���{�ł͓���̕����u�ہv���g�����߂ɍ����������Ă���B���ɁA���̕���ɑa���f�l�ɂƂ��ẮA�����̎�ł���i�킽���̂��Ƃ����ǁj�B
�Ⴆ�u�y��ۂ̓A���R�[�����y�������Ȃ��A���_�ۂ͓��_���y�������Ȃ��v�Ə����Ă���A�y��ۂ����_�ۂ������悤�Ȓ��ԂȂȁA�ƌ�����Ă��܂��������B�y��ۂ́u�q�X�ۗށv�ŃL�m�R�ނɋ߂��A���_�ۂ͍ۗނł���B�{���́g���_�ہh�ƌ����ׂ��Ƃ��낾�B
�w�n�������̋��فx�́u��҂��Ƃ����v�ŁA����h�����̂悤�ɉ��������ɏq�ׂĂ���̂ɁA�܂������^�������A���̖{�ő������[�����ꂽ�B
���܁A�����ۂłȂ��ɍ����ۂƏ������B�ۂ��u�`�ہv�ƌĂԂ̂́A�ہi���F�ہj���u�����v�ƌĂ�ł����̂Ɠ����ɁA�E�[�Y�ȑO�����ăz�B�b�e�J�[�ȑO�̋C�y���P�זE�y���̃V�X�e���̖��c���B���u���v�Ƃ��������w�I�ȕΌ��͋}���ɐ���������邪�A���j�u�ہv�Ƃ����悤�Ȉ�w�I�Ό��́A���ԂŒ蒅���Ă��邱�Ƃ������āA���܂�C�z���Ȃ��B�i�O�f��p260�j�܂������A�g�����ށh�ƌ�����A�A�����Ǝv����B�w��I�Ɍ����Łg�����h�ȗ���Ǝv����}�g��w�����Ȋw�n�A���n�����ފw�������������̃T�C�g�ł́A���������̂悤�Ɉʒu�Â��Ă���B
�����͗t�Α̂�~�g�R���h���A�C�S���W�̂Ȃǂ̍זE���튯�������Ȃ����j�����̒��ԂŁC�n���I�ɂ̓O�����A���ۂȂǂƂƂ��ɐ^���ہiEubacteria�j�̈���ł���B�������C�������ۂƈقȂ�C�^�j�����������i�A���j�Ɠ��l�Ɏ_�f�����^���������s�����߂ɁC�Â�����A�����邢�͑��ނ̈���Ƃ��Ĉ����Ă����B���݂ł͍ۂ̈ꕔ�Ƃ��ĔF������Ă��邪�C���܂ł����K�̖ʂ���C���邢�͌����Z�p���ގ����Ă��邱�Ƃ��瑔�ނƂ��Ĉ����邱�Ƃ������B
�Í��@���^�����y�Ƃ������̂�����B�b����ǂԐ삩��u�N���A�u�N���Ɓg���C�h�iᏋC�j���킫�オ���Ă��錻�ۂł���B���̃K�X�̓��^�����U���A�Y�_�K�X���R���A���̂ق��ɏ��ʂ̗������f�A�����C�Ȃǂ���Ȃ�B���̒�ɒ��a�����L�@�����A���C�I�����̂��ƂŊ�������ۂɕ�������Đ��f��Y�_�K�X�A�M�_�A�|�_�ȂǂƂȂ�B�����������Ƃ��āA���^������������ۂ����݂���B������u���^�������ہv�Ƃ����B
���̃��^�����y�ɂ���āA���_�f��Ԃł̗L�@���̕������ۏ����B�Ȃ��Ȃ�A���f�����ۂ����C�I�����̉��Ŋ������Ă��A���f�����^�������ۂɂ���ď����Ȃ��Ɗ����͂�����~���Ă��܂�����ł���B
�[�C��i���炍�j�̊C��ɕ��z����M���̂킫�o�����̍����E�������Ő������郁�^�������ۂ���������Ă���B����́A�n���������甭�����鐅�f�𗘗p���Ă���B
�����i���Ƃ��œK���x�W�T���j�E�������̖��_�f��Ԃł悭��������ۂ́A�������������������đ�C���Ɏ_�f�K�X���[������ȑO�̑��Â̒n���ɐ������Ă����\��������B�E�[�Y�iR.C.Woese�j�́A���ׂĂ̐����̍זE�ɑ��݂��Ă��郊�{�\�[���̔�r��������A���^���ۂ��A���̐����Ƃ܂�ňقȂ���������V�����������ފT�O�idomain / kingdom�j�ɑ�����ƍl����ׂ����Ƃ����B�����Ă�����g�Íہh�iarchae-bacteria�j�Ɩ��Â����B�E�[�Y�̌ÍۂɊւ���ŏ��̘_���͂P�X�V�V�N�B
����ɂ���āA�����E�́A���̂R�h���C���ɕ������邱�ƂɂȂ����B
�]���A�ÍۂƐ^���ۂ͂��킹�āu���j�����v�Ƃ����Ă����B�זE�j�������Ȃ��P�זE�����ƕ��ނ���Ă����B�����A���̒P�זE�����̃��x���ŏd��Ȑi�����s���Ă������ƁA����͓����|�A���̔��ȏ�̔��ł��������ƁA����h�̌����u�P�זE�y���v�̓��ł͔����ł��Ȃ����̂ł��������Ƃ����炩�ɂȂ����B
������A����^�ۗނ͐^�j�����ɓ���B�������ގj�����I���������Ƃ́A���̕��ނ��Q���@�ł͂Ȃ��R���@�������Ƃ������Ƃ��i�������A�����^�^�j���������j�������j�B���܂̂Ƃ���ÍۂƐ^���ۂ́g�����h����A�^�j���������܂ꂽ�ƍl�����Ă���B�������A�ÍۂƐ^���ۂ̔����̐��͊ȒP�Ɉʒu�Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�Íۂ���^���ۂ����܂ꂽ�Ƃ����悤�ȊW�ł͂Ȃ��Ƃ��������j�B
���^�������ۂ́A�ŏ��ɔ������ꂽ�Íۂł���B���ɂ́A���c�≖���甭�����ꂽ���x�D���ۂ�A�����̉���Ȃǂ��甭�����ꂽ���x�D�M�ۂȂǂ�����B
�[�C��i���炍�j�̊C��ɕ��z����M���̂킫�o�����̍����E�������Ő������郁�^�������ۂ���������Ă���B����́A�n���������甭�����鐅�f�𗘗p���Ă���B
�����̊����́A�G�l���M�[���ƂȂ镨���i�H���^�h�{�j��������A������i�D�C�I�^���C�I�Ɂj�g�R�₷�h�̂ł��邪�A���w�I�G�l���M�[��������鑽�i�K�̐����ȃT�C�N����p�ӂ��Ă����āA���������w�I�G�l���M�[������E���p���Ă������Ƃɂ���āA�s���Ă���B���������p����H���^�h�{�́A�݂��Ɋ�d�ɂ����܂肠�����H���A���̒��ŁA�Ȃ��肠���āA�z���Ă���B���鐶����̐g�́^�r�����͕ʂ̐�����̐H���^�h�{�ɂȂ�B���̘A���͂P�{�̍��ł͂Ȃ��A�����̑��݊W����Ȃ�Ԃ̖ڂ̂悤�ɂȂ��Ă���B�u�H���ԁv�Ƃ����n�������B���̐H���A���i�H���ԁj��ʂ��āA�����z�����s���Ă���B
�����̗��j�R�T���N�́A���̕����z���������Ă������j�ł���B����́A�S�����ɋ��ʂ̂c�m�`�l���ň�`��`�����Ă��Ă��邱�Ƃ��������Y�قɎ����Ă���B�������ێ����Ă��������z�́A�c�m�`���ێ�������̂ł������B�������A����͓r���Łg�i���h�i�V�X�e���Ƃ��Ă̐i���j���Ȃ���R�T���N�������Ă����̂ł���B
�����̕ϓ]����܂�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ɑ��āA�V�n���R�̗I�v�s�ł��q�ׂ郍�}����`���w�Ȃǂ��������B�����A�R�x����n�����ȍ�p�ŏo�����Ƃ��������łȂ��A�嗤�������̂ł���B����ɑ��āA�����̈�`�V�X�e���͂R�T���N�̌Â����ւ��Ă���B
�����̕ϓ]�������Ȃ�A����Ɠ����x�ɓV�n���R���F���V�R���ϓ]��Ȃ��̂ł���B�V�n���R�̗I�v�E�s�ς������Ȃ�A�������I�v�E�s�ςł��邱�Ƃ������ׂ��ł���B�킽���́A�����̕s�v�c���v�����Ƃ����ł��邪�A�����̂��̎��ӎ����̂��̂��R�T���N�̐����j�̏�ɂ��邱�Ƃ������v���B�����āA���ꂪ�u�J�Q���E�̂��Ƃ��A�͂��Ȃ����v�ł͂Ȃ��A�R�x�E�嗤�Ɣ�ׂĂ������͂��Ȃ����łȐ����V�X�e���̏�ɂ���Ǝv���Ă���B�u�J�Q���E�̖��v���R�x�E�嗤�Ɣ�ׂĕ����͂��Ȃ��̂ł���B
�����炭�����V�X�e���́A�g���R�ɂł�������Ȃ����݁h�ł͂Ȃ��A�F���ɕՍ݂��鋭�łȕ����W�c�̂�����i�����n�̑��ݗl���j�̂ЂƂł���Ƃ����l�����A�܂�A��������������̂ɂ͕K�R��������A����͕Ս݂��Ă��邾�낤�Ƃ����l�������Ƃ肽���B�����łȂ���A�R�T���N�Ƃ����悤�Ȓ��N����������������\���͏��Ȃ��A�ƍl����B�܂�킽���́A�u�����͔��Ɉ��肵�������n�̂�����̂ЂƂ��v�Ǝv���B
�i5.5.c�j�F���������ƃG���g���s�[
�킽�������́A�����E�A���E�^�ۗށE�ۗށE�ÍۂƁA������G�c�ɐ��������̃G�l���M�[�I�Ȏ��x����ѕ����z�����Ă����B
�C��M���t�߂ł̒n����������̐��f�𗘗p���Ă���Íۂ�ʂɂ���A���z�����𗘗p��������������́A�V�̂���̃G�l���M�[�ڗ��p���ĒY�f�Œ���ʂ����_�ŁA���M���ׂ��ł���B����ȊO�̂��ׂĂ̐����́A���̐����ƐH���A���i�H���ԁj�Ō��т��ĕ����z��������Ƃ��Đ������Ă���B
���������p����H���^�h�{�́A�݂��Ɋ�d�ɂ����܂肠�����H���A���̒��ŁA�Ȃ��肠���āA�z���Ă���B���鐶����̐g�́^�r�����͕ʂ̐�����̐H���^�h�{�ɂȂ�B���̘A���͂P�{�̍��ł͂Ȃ��A�����̑��݊W����Ȃ�Ԃ̖ڂ̂悤�ɂȂ��Ă���B�u�H���ԁv�Ƃ����n�������B���̐H���A���i�H���ԁj��ʂ��āA�����z�����s���Ă���B
�����̗��j�R�T���N�́A���̕����z���������Ă������j�ł���B����́A�S�����ɋ��ʂ̂c�m�`�l���ň�`��`�����Ă��Ă��邱�Ƃɂ���āA�������Y�قɎ�����Ă���B�c�m�`�Ƃ����j�_�̑��݂��R�T���N�̊Ԏ�������悤�ȕ����z�łȂ���Ȃ�Ȃ������A�Ƃ������Ƃ͊m���ł���B
�����̊����́A�G�l���M�[���ƂȂ镨���i�H���^�h�{�j��������A������i�D�C�I�^���C�I�Ɂj�g�R�₷�h�̂ł���B�����A���́g�R�₷�h�ߒ��͂����Ĉ�C�ɐi�ނ̂ł͂Ȃ��A���w�I�G�l���M�[��������鑽�i�K�̐����ȃT�C�N�����Ȃ����Ă��āA���������w�I�G�l���M�[������E���p���Ă������Ƃɂ���āA�s���Ă���B
�����́A�H���^���^��C��������A������^�������A�g�̂����^�r������B�����ɂ����邱�̃G�l���M�[�ƕ����̗���́A��d�̗����ɂȂ��Ă���B�ЂƂ́u�����v�̗���ł���A�����ЂƂ́u�����v�̗���ł���B
�����|�����q�ʂ���啪�q�ʂց|���w�I�G�l���M�[���g�p�|�i�������̌����j
���̓�d�̗���́A���ݍ����Ă��āA�ʁX�ɕ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�����v�ɂ���ē����G�l���M�[��p���āu�����v����̂����A�u�����v���ꂽ�y�f�Ȃ��ɂ́A�u�����v��������i�s�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�����v�Ɓu�����v�̓�d�̗�����ł��Ȃ��ЂƂ̐����^���ƂƂ炦�āA���̂��݂������݂��̌����ł��茋�ʂɂȂ��Ă���K�R����F�����邱�Ƃ��厖�ł���B
�����āA���i�t�̂̐��A�����C�j�̑��݂��d�v�ł������B�����̒i�K�Ŕ�������M�͑��₩�ɔr�����邱�Ƃ��K�v�ł���A�p�M�͐��̐��M�E�����M���g���āA���ցi�����E��C���j�֔r�����Ă����B
���̐��������Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤�B�d�v�����Ȏ����������Ă݂�B
���������́A�g�̂Ƃ����u�V�������������̌`���v�ł���A�g�̂̍s���i���o���ہE�ؓ��s���j�́u���I�����̌`���v�ł���ƍl�������B�q���`���͑��̂Ƃ����A��荂���́u�`���v�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
- �@�h�{�����A�ċz�����A�r������i�G�l���M�[�����j
- �@�����̑̂���肾���Ă��邱�Ɓi���������j
- �@���o�A�s���A�ӎ������i����́A�����̍������j
- �@�ɐB�����邱�Ɓi���̂���肾���j
�����ŁA�킽���͐��������̓��������̂悤�Ɉ���ł܂Ƃ߂Ă����B
���������Ƃ́A���I�E���I�ȐV���������̌`���ł���B
���Ƃ��A�킽���������H���������ǂ�ʂ��Ē��ő̓��Ɏ�荞�ނƂ��ɂ́A�����y�f�ɂ���ď����q�ʂ̕����ɕ������āi�^���p�N���Ȃ�A�~�m�_�ɂ��āj��荞�ށB��荞��ŁA�q�g�̃^���p�N������������̂����A���̍����ߒ��̓G�l���M�[��K�v�Ƃ���i�����ŁA�H�����瓾����G�l���M�[���g����j�B�������A���̍����ɂ���āA����^���p�N�����q���`�������B�܂�A����̓~�N���ȃ��x���ŋN�����Ă���u�V���������̌`���v�Ȃ̂ł���B
�����̃A�~�m�_�@�@���@�@�^���p�N�����q
�����Ő����Ă��锽���́A���R�E�ŋւ����Ă���i�s�\�ȁj�����ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�ւ����Ă��锽���łȂ���A���R�E�ł́A���܂��܋��R�ɁA���̔������N���邱�Ƃ́i�Ⴂ�m����������Ȃ����j���蓾��B�������A�����̏�ł́A���̔����������I�ɋN���邱�Ƃ��m�ۂ���Ă���̂ł���B
�����̃A�~�m�_���A���������ЂƂ̖ړI�̂��߂��W�܂��Ă���悤�ɂ��ă^���p�N�����q����������B���́u�V���������̌`���v�̉ߒ��́A�܂�ŁA���ړI�I�ȍs���ł��邩�̂悤�Ɍ�����B�Ӗ��̂���s���̂悤�Ɍ�����B�^���p�N�����q�̐v�}���c�m�`���Ƃ��ĕۑ�������A�����ǂ݂Ƃ�A�����̍y�f�ɂ�鐸���Ȕ����̕��G�ȘA���̉ߒ����A�זE���Ŏ��s�����B
�킽���́A�������G���g���s�[�T�O�������������Ǝv���B
�㎮�̍��ӂ́u�����̃A�~�m�_�v�́A�Ă�ŁA�o���o���ɕ���A�������������ł������肵�Ă��邾�낤�B�����ƂȂ鉽�킩�̑����̃A�~�m�_�́A���̓��ŕʁX�̏ꏊ�ɒ�������Ă��āA�K�v�ȏꏊ�։^��Ă��Ȃ�������Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA���ӂ́u�����̃A�~�m�_�v�͖������̓x�����͑傫���킯�ł���B����ɑ��āA�E�ӂ̃^���p�N�����q�́A�A�~�m�_�����̔z��łȂ����Ă��āA�S�̂łЂƂ̗��̍\���������A���܂�����������`�������Ă���B������A�������̓x�����͏��Ȃ��Ȃ��Ă���A�ƍl������B
�����������̓x�������G���g���s�[�Ƃ����̂ł���B�㎮�ł́A�����̃A�~�m�_����������ĂЂƂ̃^���p�N�����q���ł��邱�ƂŁA�G���g���s�[�͌��������̂ł���B
�G���g���s�[�@���@�n�́A�������̓x����
�i�G���g���s�[�͂�����Ƃ��������I�T�O�ŁA���l�I�ɒ�`����Ă���B�P�ʂ́y�G�l���M�[����Ή��x�z�ŁA�Ⴆ�� �W���[���^�j�ł���B��Ή��x�s�K�j�̔M������p�W���[���̔M���n�ɗ��ꍞ��A���̌n�̃G���g���s�[�� �r���p�^�s ������������B�������A���_�ł� �p�^�s �Ƃ��������Ȃ��o�Ă��邩�A�Ƃ������Ƃɂ͓��݂��܂Ȃ��B�j
�P�X���I�㔼�Ɋm�������M�͊w�̑�Q�@���Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȍn�i�l�@�Ώہj�ł����Ă��A���̌n�ɑ��āu�G���g���s�[ �r�v�Ƃ����ʂ��`���邱�Ƃ��ł��āA
�Ǘ������n�Ŏ��ۂɋN����ω��ł́A�n�̃G���g���s�[�͑�������
�����w�̑����̖@���̂Ȃ��ŁA���̔M�͊w��Q�@���́A���Ɉٕ���悵�Ă���B���ꂪ�A�ǂ��������Ƃ��A�v�����܂܂ɏ����Ă����B
- ��P�@���́A�u���ʁ^�G�l���M�[�ۑ��̖@���v�ł���B�i�]���}�[�t�F���g�w�M�͊w����ѓ��v�͊w�x�i�u�k��1969�j�̕\���������Ă����B�M�͊w�I�Ȍn�͂��ׂĂ���ɌŗL�̏�ԗʁA�G�l���M�[�����B�G�l���M�[�͑̌n���M�ʂ��p���z��������ꂾ���ӂ��A�n���O�������Ďd�����v���s�����ꂾ��������B�ip13�j�j
- ��Q�@���̕\���@�͂���������̂����A�قƂ�ǂ́g���́h�Ő�������`�ɂȂ��Ă���B�Ȗ��ȕ������ɂȂ��Ă��Ȃ��_�������@���Ƃ��Ă͍ۗ����Ă���B�i�ނ��A���r���O �Ə����Ă��������A���̗R�����q�ׂ镶�������Ƃ����ʂ��B���Ƃ��A�N���E�W���E�X�̕\���́u�M�͂ЂƂ�łɒቷ���獂���Ɉڂ邱�Ƃ͂Ȃ��v�ł���A�P���r���̕\���́u������̕��̂̉��x�����̂܂��̍ł��₽�������̉��x���������邱�Ƃɂ���āA�d����A���I�ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ł���B�]���}�[�t�F���g�O�f���ip27�j�j
- �G���g���s�[�r�Ȃ���̂́A�u�����琶����v�Ƃ����_�ŁA���̑��̕����ʂƕ��͋C���Ⴄ�B�����́A����n�̒��Ő��܂�āA�ǂ�ǂ��邪�A�����ď��ł��Ȃ��̂ł���B��x���܂��ƁA�ړ��͂��邪���ł͂��Ȃ��B�������A�ǂ�ǂ܂�Ă���B���̖@���́A�����������Ƃ��咣���Ă���B
- �����n�ł́A�G���g���s�[�r����������悤�ȕω������N����Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A���Ԃ̐i�s���������߂Ă���A�Ƃ�������B�g���̐��E�ł́A����������������悤�ɂ����A�����͋N����Ȃ��h�Ƃ����������ŁA���Ԍo�߂̕��������߂Ă���B
- �㎮�̕\���i�]���}�[�t�F���g�O�f���ɂ��j�ł́u���ۂɋN����ω��v�Ƃ�������������ł���B�����ǂނƁA�����w�҂Ɂu���ۂɂ͋N����Ȃ��ω��v�Ƃ������̂�����̂��A�Ǝ��₵�����Ȃ�B����͂������A�G���g���s�[�𐔗ʓI�Ɍv�Z����Ƃ��K�v�ȁu���ÓI�ߒ��v�ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ŁA���܂�[���l���Ă����ʂł���B
�i���ÓI�ߒ��Ƃ́A���O�I�ɑz�肷�闝�z�I�ߒ��ŁA�ނ荇����ۂ��Ȃ��疳���Ɏ��Ԃ��������������ω���������ߒ��ł���B���ÓI�ߒ��͉t�ߒ��ł���B
��̗���������̒�[�W���[���̎��R�c���̎����̃G���g���s�[]�ŁA�v�Z���@�������Đ������Ă݂�B�G���g���s�[�̒�`��������ƒm�邽�߂ɂ́A�J���m�[�E�T�C�N���Ȃǂ���G���g���s�[�̒�`���ʂ���Ԃ�����A�܂��A���̂悤�Ȍv�Z�������ł���Ă݂�̂��������Ǝv���B�j
�y�W���[���̎��R�c���̎����̃G���g���s�[�z
����C�̂���̐ςu1 �̗e��`�ɕ����߂Ă����āA�R�b�N�b���q�l���āA�^��̗e��a�A�̐ςu2 �ɕ��o������B����ƁA�C�̂͗e��`�Ƃa�̗����ցA�̐ςu1 �{�u2 �ɍL����B���̎��A�O�E�ƔM�̏o����̂Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃ���B���̎������f�M�I�Ȏ��R�c���Ƃ����i�P�ɁA�f�M�c���Ƃ����Ƃ��ɂ́A�O�C���Ɍ������Ėc������j�B
���̎������ʂ́A �n�S�̂��f�M�I�ŁA�������A�C�̂��O���Ɍ������Ďd�������Ȃ��Ƃ��ɂ́A�C�̂������G�l���M�[�͑̐ςɖ��W�ł���B
���Ƃ��Ӗ�����B����́A�C�̂̕��q���m����������������A�Ԃ��荇�����肷��e�����قƂ�ǖ�����ԁA�܂�A�[�������K�X�Ȃ�A�G�l���M�[���g�����h�i�C�̂̕��q���m�̊ԁj�ɒ������邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl���Ă悢�A�Ƃ����ӂ��ɗ��������B
���̐����������ɐ��藧�Ƃ������̂����z�C���Ƃ����A���̂P�����ɂ��āA���͂��A�̐ςu�A���x�s�A�C�̒萔�q�i��8.31 J/mol K�j�̊ԂɁA
���āA���̎��R�c���̎����́A��t�I�ł��邱�Ƃ́A������₷�����낤�B�`�ɕ����߂Ă������C�̂��A�^�����a�Ɍ������āA�ЂƂ�łɍL����A�����`�{�a�Ɉ�l�ɍL�����Ĉ��肷��B���̏�Ԃ����ɖ߂��ɂ́A�R�b�N�b����߂Ă���A�^��|���v�Ȃǂ�p���āA�a���̋C�̂��z���o���Ă`�ɓ���邱�Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ��A�ЂƂ�łɁA�ŏ��̏�Ԃɂ��ǂ邱�Ƃ͂��肻�����Ȃ��B
���̂悤�ȁA��t�I�ȕω��ɂƂ��Ȃ��ĕK���G���g���s�[�̑������N�����Ă����A�Ƃ����̂��M�͊w��Q�@���ł����āA�ȉ��A��̓I�ɂ��̏ꍇ�̃G���g���s�[�̕ω����v�Z���Ă݂�B
���x�����ʂł��邱�Ƃɒ��ӁB�܂��A��ԕ�����������̂ŁA��1 �� �q�s�^�u1 �C��2 �� �q�s�^�u2 �ƂȂ�A���͂͏����ł���B
- �n ����F�̐ςu1 �C���͂�1 �C���x�s
- �I ����F�̐ςu2 �C���͂�2 �C���x�s
�G���g���s�[�̌v�Z�́A�n��Ԃ���n�߂āA�I��Ԃ܂œ��B����悤�ɁA�n�ɂ����������ÓI�ɕω��������Ȃ���i�ށB���̕ω��̘H�����ǂ�Ȃ���A�n�ɐڂ��Ă���g�M���̉��x�s�h�i�n�̉��x�ł���K�v�͂Ȃ��j�ƌn�ɗ^������M���p�Ƃ����Ƃ��ɁA���̐ϕ����s���悢�i���_�ł́A���̎��̓��o�͂��Ă��Ȃ��j�B
�w���ɂƂ��āA���̘b�ł����Ƃ��������ɂ����Ƃ���́A���ÓI�Ƃ��A��̉�H�ϕ��Ȃǂł͂Ȃ��āA�n��Ԃ���I��Ԃ܂ŒB����H���A�����̌n�����ǂ����H�i���̏ꍇ�u���R�c���v�j�ł���K�v���Ȃ��A�K���ɑI�i�����ɂ���j���ÓI�ȘH�̂����̂ǂꂩ�P�ōs���悢�A�Ƃ����_�ł���B�����Ă��̏ꍇ�́A�v�Z���₷���悤�ȘH��I�Ԃ��ƂɂȂ�B�ǂ̂悤�ȏ��ÓI�H��I��ł��A�G���g���s�[�̌v�Z���ʂ͑S������̒l�ɂȂ�̂ł���i���̂��Ƃ��A�G���g���s�[���u�M�͊w����ԗ��v�ł���A�Ƃ����j�B�i���́A��ŔM�͊w�̑�P�@�����]���}�[�t�F���g�̕\���ŏЉ���Ƃ���ŁA�u�G�l���M�[�͏�ԗʂł���v�Ƃ��Ă����B�j
�����ł́A�Q��ނ̈قȂ鏀�ÓI�H���l���āA����ɉ����Ă̐ϕ��v�Z�����ꂼ�����Ă݂�B
�y�v�Z�@���̂P�F�����Ȑ��ɉ����āz
���ÓI�ŁA�����I�ɕω��������邱�Ƃɂ��悤�B
�Ƃ����āA�㎮���v�Z���Ă����悢�B���Ȃ킿�A���x�s�̔M���ɐڂ��Ă���K�X�����ÓI�Ɂi�e�u�Ԃɒނ荇�킹�A�����̎��Ԃ������āj�ω�������B���u�̊O�ɂ��Ə����Ă���̂́A�K�X�̈��͂ɒނ荇�킹�邽�߂Ƀs�X�g���ɉ����Ă��鈳�͂ł���B
- �n ����F�̐ςu1 �C���͂�1 �C���x�s
- �r���� �F�̐ςu �@�C���͂� �@�C���x�s
- �I ����F�̐ςu2 �C���͂�2 �C���x�s
�i���z�j�C�͓̂����̏����ł́A�����G�l���M�[�̕ω��͂Ȃ��B���������āA��������M���p�́A���̂܂܊O���ւ̎d�������u�i����́A�d�����́~�������璼�ڂɓ������j�ɂȂ�B
�r�@���@�����p�^�s�y�v�Z�@���̂Q�F�f�M�Ȑ��ɉ����āz
�@�@���@�������u�^�s
�@�@���@���i�q�s�^�u�j���u�^�s�@�@�@�i��ԕ��������g���ĕό`�����j
�@�@���@�q�����u�^�u
�@�@���@�qlog�i�u2 �^�u1 �j�@�@�������@�@���_
���x�́A�f�M�I�ɂu1 �� �u2 �Ɩc�������i�ނ��A���ÓI�ɍs���j�A���̂��Ƃɂ���āA���x���������Ă��邾�낤����i���̉��x���s3 �Ƃ���j�A�M���s3 �ɐڂ������Ēg�߂āA�{���̉��x�s�ɂ���B
�܂��A�f�M�I�Ȗc�������ÓI�ɍs���Ƃ��́A���R�A�M�̏o���肪�Ȃ��A���Ȃ킿�A
�ł��邩��A�G���g���s�[�̕ω��͂Ȃ��B�������A���x�ω��s���s3 �͂���B�s3 �����߂�ɂ́A���̂悤�ɂ���B
�f�M�ω����闝�z�C�̂ɂ��āA�|�A�b�\���̎��Ƃ������̂�����B
�� ����M���Ƃ����ʂŁA��ϔ�M�bv �ɑ���舳��M�bp �̔�A���Ȃ킿
�ł���B�bp �̕����˂ɂbv ���傫���̂Łi�Ō�Ɏg�����A���z�C�̂ł� �q �����傫���j�A�����P�ł���B
���āA��̃|�A�b�\���̎��ɂ��A
��ԕ����� ���u���q�s ��p���āA
�䂦�ɁA
����ŁA�s3 �����܂����B
�����ŁA�̐ψ��̂܂܁A���x���s3 �� �s �֏グ��B����́A��ϔ�M�b�����g�����ƂɂȂ�B�bv �͒萔������A
�r�@���@�����p�^�s�Ō�̍s�́A���z�C�̂ɂ��Đ��藧�� �bp �� �bv �{�q ��p�����B
�@�@���@���bv ���s�^�s
�@�@���@�bv �����s�^�s
�@�@���@�bv log�i�s�^�s3 �j
�@�@���@�bv log�i�u2 �^�u1 �j�i���|�P�j
�@�@���@�bv �i���|�P�jlog�i�u2 �^�u1 �j�@�@�i������ �����bp �^�bv ��p���āj
�@�@���@�i�bp�|�bv �jlog�i�u2 �^�u1 �j
�@�@���@�qlog�i�u2 �^�u1 �j�������@�@���_
����ɂ���āA��̈قȂ鏀�ÓI�o�H�ɂ��v�Z���ʂ���v���邱�Ƃ������ꂽ�B
�Ȃ��A���̕����͌˓c���a�w�M�E���v�͊w�x�i��g���X1983�j�ip30�`63�j���Q�l�ɂ����B���̖{�́A���Ă��Ȃ����J�ɏ����Ă���D�ꂽ�M�͊w�̋��ȏ����Ǝv���B
�M�͊w��Q�@�����ēx�f���Ă݂�B
�ǂ̂悤�Ȍn�i�l�@�Ώہj�ł����Ă��A���̌n�ɑ��āu�G���g���s�[ �r�v�Ƃ����i��ԁj�ʂ��`���邱�Ƃ��ł��āA
�Ǘ������n�Ŏ��ۂɋN����ω��ł́A�n�̃G���g���s�[�͑�������
�O�ɁA������������������A��������^���p�N�������Ȃǂ̐����̓��ōs���鑽���̔����́A��_���Y�f��A�~�m�_�Ȃǂ̏����q���������āA�����������\���������啪�q�����グ�锽���ł������B���̔������i�߂ΐi�ނقǒ�������������B����́A���������̌����ɑ��Ȃ�Ȃ��B�܂�A�����̍�������������ƁA�������������̓��ŋN�����Ă��錻�ۂ́A�G���g���s�[�̌������Ӗ����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���Ȃ킿�A�M�͊w��Q�@���ɔ����锽���̂悤�Ɍ�����B
�M�͊w��Q�@���͊m�ł���o���Ɋ�Â��Ă���@���ł��邩��A�����̊֗^���錻�ۂɂ��Ă��A������Ɛ��藧���Ă���̂��A�ƍl����̂������ł���i�����I�ł���j�B�Ƃ���ƁA�������������̓��ŋN�����Ă��錻�ۂ��A�M�͊w��Q�@���ɔ����锽���̂悤�Ɍ�����̂́A���̂Q�́A�����ꂩ���Ӗ�����B
�悭�l���Ă݂�ƁA���̂Q�͎��́A�������Ƃ������\���Ă���ꍇ�������B�����Ƃ��Ă��锽�����A���ڂ��Ă���n���O���̌n�ƂȂ��ł���A�Ƃ����悤�ɁB
- ���ڂ��Ă���n���A���́A�u�Ǘ������n�v�ł͂Ȃ��B
- ���ڂ��Ă���n�̂Ȃ��ɁA�����Ƃ��Ă��锽��������B
�g�����̑����h�̂悤�Ɍ����锽���̉A�ɁA�g�������̑����h�ł��锽�����i�s���Ă��āA���̗��҂��l����ƁA�G���g���s�[�̑����̂ق����A�����������Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��锤�ł���A�����A�M�͊w��Q�@�������ՓI�ɐ��藧�Ƃ���B
�g�������ۂ͕����w�̋y�Ȃ��_��Ȍ��ۂ��h�Ƃ�������ɗ����Ȃ�����A�������ۂɂ����Ă����ՓI�ɔM�͊w��Q�@�������藧���Ă���͂����A�ƍl����ׂ��ł���B�������A����́A�P�Ȃ鋳����`�i����ځj�ł͂Ȃ��A�������ۂ�T������w�j�����Ă���_�ŗL�Ӌ`�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�������ۂ����������M�͊w��Q�@���ɔ�����悤�Ɍ�����̂Ȃ�A�u�G���g���s�[�̑����������炷���ۂ��B��Ă���ɂ������Ȃ��v���Ƃ��咣���Ă���̂�����B
�Ⴆ�A���I�̌��ۂ�����B�u���I�v�ł��������u��̂ӂ��̐��H�v�ł������B�Ƃ������A�ɍL�����Ă����i�g�U���Ă����j�����C���W�܂��Ă��āA�t�̂̐��̂������A���Ȃ킿�I�ɂȂ錻�ۂł���B���̌��ۂ����ɒ��ڂ���A���炩�ɁA�G���g���s�[�̌����ł���B
��Q�@���ɂ��ƁA�G���g���s�[�����̌��ۂ������ɐi�s���Ă���͂��ł���B����́A�u�����̊g�U�v�܂��́u�G�l���M�[�̔��U�i���M�j�v�̂悤�Ȍ��ۂł���͂����B���I�̏ꍇ�́A�����C�����C���M�ɑ�������M��D���K�v������B�����C���炷��A�C���M�ɑ�������M�����͊��֕��o���āA����͉t�����Đ��ƂȂ�B���Ȃ킿���I�̌��ۂɂƂ��Ȃ��āA�����C������͊��ւ̔M�̈ړ����������A�Ƃ������Ƃ�������B
�����A���ۂɂ́u�����C���v�̖�肪����B��̂ӂ��̏ꍇ�́A��̒����O�a�����C���ɂȂ��Ă����Ԃłӂ����O�C�Ɛڂ��Ă��āA�����Ő����C���C���M��D��ꌋ�I����A�ƍl���Ă������낤�B���̔M�͓�̒��M���Ă���R�������痈�Ă���B
���I�̏ꍇ�́A�����ɑ�n�̕��˗�p�ŋC�����ǂ�ǂ����Ă����Ԃ��l���悤�B��C���Ɋ܂܂�Ă��鐅���C�̗ʂ͂��炩���ߌ��܂��Ă���ƍl���Ă悢���낤�B��������Ƃ�����������Ƃ��B�C�����������āA�����C�������̉��x�̖O�a���C���Ɉ�v������A���I���͂��܂�B�����C�͑�n�ɋC���M��D����ƁA���̕��������I����B���Ȃ킿�A�����C �� ��n �� ���˗�p �̗���ŔM���ړ����A���M�����B �����ɂ����A���̊ԁA�C���̒ቺ�͎~�܂�A���˗�p�͌��I�Ɏg���Ă���B���I���i��ŁA�����C����������A���x�͋C���̒ቺ���ĊJ���邱�ƂɂȂ�B
������ɂ����Q�@���ɂ���āA���I�Ɠ����i�s�ŕK�R�I�ɕ��M���ۂ��N�����Ă���͂����Ƃ�������߂��ł���̂ł���B
�����P��A��C�������z�����l�@���Ă݂悤�B
�n�\�ɂ��鐅�i�t�̂̐��j���������A�����C�ɂȂ��ď㏸���A���ʼnt���i������ɕX�j���ĉ_�ƂȂ�A�J�H�ƂȂ��ė������Ă���ߒ��ł���B
�茳�́w���ȔN�\�x�i�����V����ҁ@�ۑP�j���݂�ƁA���̋C���M�͂Q�T���łT�W�Rcal/g�A�P�O�O���łT�S�Ocal/g �Ǝ�����Ă���B����𗘗p���邽�߂ɁA�n�\�̋C�����Q�T���������Ƃ��悤�B�Q�T���łP���̐����������āA�����C�ɂȂ����Ƃ���B���̂Ƃ��A���̐��͎��͂���T�R�Wcal�̔M��������ċC�����A�����C�ɂȂ����̂ł���B���̂P���� ���@���@�����C �̕ω��ɂ�������������G���g���s�[��
�r1 �@���@�p�^�s�@���@�T�R�W�^�i�Q�T�{�Q�V�R�j�@���@�P�D�W�O�T cal/g K�ł���B����ɓo�ꂵ�Ă���Q�V�R�́A�ێ������Ή��x�j�ɕϊ����邽�߂̂��̂ł���B���̏������ۂł��ꂾ���̃G���g���s�[���������A�����C�͂���������ď����������A�ƌ����Ă��ǂ����A���͂̊�����M���z�����������C�������������A�Ƃ����Ă������B�����A�u�M���z�����v�ƌ������������ƁA���̌��ۂ��A�M�͊w��Q�@���ɂ��K�R�I�ȃG���g���r�[�����̔�t�Ȍ��ۂł���Ƃ����F�����Ƃ��Ȃ�Ȃ��\��������B���������āA�����ł͒P�Ɂu�M�v�Ƃ����A�u�G���g���s�[�����������v�Ȃ����u�G���g���s�[�̑����v�Ƃ͂����茾���������悢�B
���āA���̐����C���㏸���Ă����B�Ⴆ�A���w���̏�̂ق��P�����ӂ�ŁA���H�^�X�ɂȂ����Ƃ��悤�B�w���ȔN�\�x�ł͂P�������͉��x�Q�Q�R�j�i�|�T�O���j�A�C���Q�U�ThPa�Ƃ��Ă���B���̏����ł̋C���M�͕s���ł��邪�A���ɂQ�T���̂Ƃ��Ɠ������Ƃ���A
�r2 �@���@�p�^�s�@���@�T�R�W�^�Q�Q�R�@���@�Q�D�S�P�R cal/g K�܂�A���x���Ⴂ�̂ŁA���ꂾ���G���g���s�[���傫���Ȃ��Ă��āA���ōs������M�ɂ���āA�r2 �����̃G���g���s�[�𐅏��C�́u���ɒu������ɂ��āv�J�H�Ƃ��ė������Ă���B��̌v�Z�ł͐��P���ɂ��ā@�r2 �|�r1 �� �O�D�U�O�W cal/g K �̃G���g���s�[�����֎����グ���̂��B�u������ɂ��ꂽ�G���g���s�[���������M�́A�ŏI�I�ɂ͉F���֕��˂����B�i�n�����F���֍s���M���˂̌��ς�v�Z�́A�����ł͏ȗ�����B���Ƃ��Ώ��؈��O�f���̑�R�́u���Ƃ��Ă̒n���v���Q�Ƃ��ꂽ���B�j
�܂�A�n������̔p�M�i��C���̐��z��ʂ����p�M�j�́A���̂悤�ɂ��āA�G���g���s�[���F���֎̂ĂĂ����̂ł���B
���̐��z�ɃG���g���s�[�̊ϓ_���璍�ڂ��A���̖{���I�d�v�����ŏ��Ɏw�E�����̂́A�G���g���s�[�w��The Society for Studies on Entropy�i�ݗ�1983 http://www.entropy.ac/entropy/nyuwkai.html �j�ł���B�킽���͂��̉���ł͂Ȃ����A�ݗ��������炱�̊w��֘A�̏������瑽�����w��ł���B�����܂łɖ��O�����������؈��A�Ɠc�ւ̂ق��ɁA�ĒJ�čO�A���c���A�ʖ��F�Y�������Ă����B�Ȃ��A�u���R�ی���߂����āv�Ƃ������ٍe�i1984�j���T�C�g�u���V�̐��݂��v�Ō��J���Ă���B�G���g���s�[�w��ł������A�킽�����S�������Ă������Ƃ������Ă���B�����A�G���g���s�[�Ɋւ��Ă͂قƂ�ǐG��Ă��Ȃ��B
�y�V�����f�B���K�[�̃l�Q���g���s�[�ɂ��āz
�ʎq�͊w�̑n�n�҂̂ЂƂ�ł���d�D�V�����f�B���K�[�́A�Q�O���I�O���̕����w�̗L���̃��[�_�[�ł������i�I�[�X�g���A���܂�A1887-1961�j�B�P�X�S�R�N�̍u�������ƂɁw�����Ƃ͉����x�Ƃ����L���Ȗ{���o�ł���A���̒��Ɂu�����́g���̃G���g���s�[�h��H�ׂĐ����Ă���v�Ƃ������t�������āA�悭�L�����ꂽ�B�킽���͉����V�E���ڋ��v��̊�g�V���i����1951�j���茳�Ɏ����Ă��邪�A�P�X�W�R�N�E��R�X���ł���A�悭�ǂ܂ꂽ�{�ł��邱�Ƃ�������B
�V�����f�B���K�[���u���̃G���g���s�[�v�i�l�Q���g���s�[�j�Ƃ�������ǂ̂悤�Ɏg���Ă��邩�A���Ă����B
���������������Đ����Ă��鐶���̂͐₦�����̃G���g���s�[�債�Ă��܂��\�\���邢�͐��̗ʂ̃G���g���s�[������o���Ă���Ƃ������܂��\�\�����Ă��̂悤�ɂ��āA���̏�Ԃ��Ӗ�����G���g���s�[�ő�Ƃ����댯�ȏ�Ԃɋ߂Â��Ă䂭�X��������܂��B���������̂悤�ȏ�ԂɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���A���Ȃ킿�����Ă��邽�߂̗B��̕��@�́A���͂̊����畉�G���g���s�[��₦���Ƃ����邱�Ƃł��B�\�\��ł���������悤�ɂ��̕��G���g���s�[�Ƃ������̂͐�����ۓI�Ȃ��̂ł��B�����̂������邽�߂ɐH�ׂ�͕̂��G���g���s�[�Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ����������t���炵���Ȃ������Ȃ�A������ӂ̖{���́A�����̂������Ă���Ƃ��ɂ͂ǂ����Ă����o����������Ȃ��G���g���s�[��S�����܂���ɊO�֊��Ă�Ƃ������Ƃɂ���܂��B�i�O�f��p125�j�G���g���s�[�̍�������ŁA�����̂́u���v������悤�ɂ��Ă���A���ꂪ������ӂ̖{�����Ƃ��������ł͑��肸�A�u���G���g���s�[�v��H�ׂĂ���ƌ������̂ł���B���̌���ŁA�܂��������\���ł͂Ȃ��B
�������A���́u���G���g���s�[�v����l�������Ă��܂����̂ŁA�G���g���s�[�̍�������́u������ۓI�ȁv�ߒ��ɓ��݂���ʼn𖾂��邱�Ƃ��a���ɂȂ肪���ɂȂ��Ă��܂����B���������ɂ́A�G���g���s�[�傷��ߒ��ɂƂ��Ȃ��āA���̃G���g���s�[�����Ă�ߒ����K�����݂��Ă���̂ł���A���̕ʁX�̉ߒ��̂��ꂼ��̓������A���ꂼ��𖾂���K�v������B
���Ƃ��A�l�ԁi�����j�̏ꍇ�A�r�A�E�����Ȃǂɂ���Ĕp�M����єr�������s�����Ƃɂ���āi���ɂ��ċC���t�˕��M�Ȃǂ���j�A�����̂Ƃ��Ắu�G���g���s�[���������Ă���v�悤�ȍ�������ɂȂ��Ă���̂ł���B�H�����̂�A�������݁A�ċz�����Ă��邱�Ɓi�ێ��j�ƁA�p�M�E�r���������Ă��邱�Ɓi���̑S�̂��u�r�G���g���s�[�v�ƌ����Ă������낤�j�A�̍��������Ō�҂̕��������Ă���Ƃ����̂ł���B�����͂��̏����Ă��镪�����A�g�̌`�������ړI�ӎ��I�s���������_���������Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A��G���g���s�[��n�o���Ă���̂ł���B���̍��������̑O��ƂȂ�u�ێ�v�Ɓu�r�G���g���s�[�v�̂Q�̉ߒ��̎��ԋ������l�O���āu���̃G���g���s�[��H�ׂĂ���v�ƌ����Ă��܂��ƁA���������H���E���E�_�f�������Ƃ��āu���̃G���g���s�[�v�������Ă���ƌ�����Ă��܂������ł���B�{���́u�r�G���g���s�[�v�ߒ��������Ă��邱�Ƃɂ���āA�g�H���E���E�_�f���u���̃G���g���s�[�v�������Ă���h�Ƃ������߂������Ă���Ƃ����̂ɉ߂��Ȃ��̂ɁB
�i5.5.d�j�F�n����
�n���́A���������݂��Ă���V�̂ł���B
�i���܂̂Ƃ���A�n���ȊO�̐����̑��݂���V�̂͒m���Ă��Ȃ��̂ŁA�u��L�ȓV�́v�ł���Ƃ����ׂ������m��Ȃ��B���؈��́u�F���L���Ƃ����ǂ��A�����̑��݂���V�̂͂��̒n�������ł��낤�A�Ƃ̎v�������͕����v�O�f��p146 �ƌ����Ă���B
 �킽���́A�ނ���g�[�}�X�E�S�[���h�w���m�Ȃ�n�ꍂ�M�������x�i�匎���X2000�j�ɂ��������āA�����̕Ս݂���F�����̕��ɐe�ߊ����o����B�����A���؈��͋������Z�i�Z���j����ɒG[�����͂������Ђ�]����u�l�ޔ����ɂ���ĉF���͑����I�ian sich�j�Ȓi�K��������I�ifur sich�j�Ȓi�K�ɓ������v�Ƃ����l�ޔ����̉F���j�I�Ӌ`���u�`�ŕ����i��p151�j�[�����������Ƃ����B
�킽���́A�ނ���g�[�}�X�E�S�[���h�w���m�Ȃ�n�ꍂ�M�������x�i�匎���X2000�j�ɂ��������āA�����̕Ս݂���F�����̕��ɐe�ߊ����o����B�����A���؈��͋������Z�i�Z���j����ɒG[�����͂������Ђ�]����u�l�ޔ����ɂ���ĉF���͑����I�ian sich�j�Ȓi�K��������I�ifur sich�j�Ȓi�K�ɓ������v�Ƃ����l�ޔ����̉F���j�I�Ӌ`���u�`�ŕ����i��p151�j�[�����������Ƃ����B�킽���́A�G�̖��O�ɉ��������v���������B�S�O�N���O�ɁA�G�w�����̓N�w�I�T�O�x�Ȃǂő����I�|�����I�i�K�Ƃ����T�O���w���Ƃ�����������ł���B���̂���킽���͍��c����Ƌg�{�������܂������ɓǂ݂Ȃ���G[�J�P�n�V���C�V���E�Ƃ����Ă���]�������������肵�Ă����̂ł���B�j
�Ȃ��A�n���ɐ����������������A���܂R�T���N�O�ƌ����Ă��邪�A�悭�������Ă��Ȃ��B���������A�u�����v�Ƃ͉������A�悭�������Ă��Ȃ��B�����A�����̑��ݗl���͕������Ă���B
�����́A���^�O����ʂł��鋫�E�������A�����^�G�l���M�[���������铮�I����̂Ȃ��ŁA�G���g���s�[�������Ӗ�����A�������^�g�D���������I�Ɍ`�����Ă������ݗl���̌n�ł���B���������āA���̐����n�Ƀ́A�K�R�I�����������u�G���g���s�[����v�����������n�����݂��Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ���āA�͂��߂āu�G���g���s�[����v�͐����n���œ��I�Ɉ����Z����ăg�[�^������Ɓu���̃G���g���s�[�v��ԂɂȂ��Ă���̂ł���B���̎傽��S��������ł���B
���̐��̓����̃|�C���g�́A���̂R�_�ł���B
- �i�t�̂Ƃ��Ắj�����p�������悭�n�����āA�����Ƃ��Ĕr�o����邱��
- �C���M�̑傫���𗘗p���āA�����i���U�j�ɂ���āA��C�������悭�p�M���邱��
- �����C����C�����㏸���A���ʼn_�����J�H�i�X���j�ƂȂ�ۂɁA�F���֔p�M���邱��
��C���ɔp�����ꂽ�G���g���s�[�i�p�M�j�́A�ŏI�I�ɂ͑�C���̐��z�ɂ���ĉF���֊��Ă���B���̐��z�̉i�����A�n�������̐����̉i���̕K�{�̏����ł���B
�i�G���g���s�[�r���̊ϓ_���璭�߂�ƁA�u���v�A�u���́u���v�v�A�u���́u���́u���v�v�v�A�������Ƃ����`�����͂��Ȃ炸�K�w�\�����Ȃ��Ă����A�Ƃ������؈��w���̊�b���_�xp140�`144 �ُ͌̕����ł���B�j
��C���ł̐��z�K���Ă������B�n��ɂ͉t�̂̐��i�C�A�Ώ��A�͐�j������A�����C�ƂȂ��ď������ď��ւ�����_���ł��i�Η����E�ʂ���P�Pkm���j�A�ቷ�̂��߉t���i���^�X�j���A�~�J�i��j�ƂȂ��čĂђn��ɖ߂�B
�n��ŏ����M��D���������C�́A���ŋC���M�Ƃ��ĕ��o����B�n��Ə��̉��x���i�n��Q�O�����x�A�Η����㕔�Ł|�T�O���j�����݂��A���̒��Ő����z���A�t�́^�C�̂Ƒ���ω������Ă��邱�Ƃɂ���āA�n��̃G���g���s�[�������グ�A�F���֊��ĂĂ���B���̐▭�ȍ\���ɂ���ăG���g���s�[�r�����s���Ă���A���̍\���̂ǂꂩ�ЂƃR�}�������Ă��A���̏z�͂��܂����Ȃ��B
- ���̕����Ƃ��Ă̓��قȐ����i�C���M�E��M���傫���A�X�����ɕ����A���̂��悭�n�����j
- �n���\�ʂɂ́i�t�̂́j������ʂɑ��݂���i�n���̑傫���Ǝ��ʁj
- �n��Ə��̉��x�Ɖ��x���i���z�����̕��ˁA��z�Ƃ̋����A��C�̉������ʁj
- �����C����C���y���i���̕��q�ʂ��������A�����P�U�A��C���Q�W.�W�j
��K�͂ȋC��ϓ��ł��Ȃ�����A�ɒ[�Ɋ����������������I�ɐ����̐��߂���ɕω�����v���͂Ȃ��B�ɒ[�Ɋ�������������́A�����C�̏������̂��̂����Ȃ��A�_���ł��Ȃ�����ł���B�ُ�C�ۂŁA�ˑR�~�J�������Ă��A�A�����Ȃ����߂ɐ��������킦�邱�Ƃ��o�����A�y���ƂƂ��Ɉ�C�ɐ�������Ă��܂��B
�X����ی삷��Ӗ��́A���낢�날�邾�낤���A���z�̊ϓ_���������߂ďd�v�ł��邱�Ƃ͘_��҂��Ȃ��B���ɑ���X�т̓������ې������̂Q���傽����̂ł���B
�~�J�̉J���́A��C���𗎉����Ă��āA�ŏ��ɐX�т̗t�ɂԂ���B����ɁA���}��`���A���������Ēn��ɍ~��Ă���B�n��̉�����G�炵�A���t�̑͐ς̊Ԃɗ��܂�R�P�ɐ���^���A�y��ɐ��݂��ށB�X�тɐ������鐶���͐������݁A�̓��ɂƂ肱�ށB���͒n���ɒ���߂��点�������琅���z���グ��B�n���̏��������^�ۗށE�ۂ��K�v�Ȑ����Ƃ肱�ށB
�~�J�������A�R�P�̊Ԃɑ����������������܂��B�y��ɐ��݂����́A�y�������Ԃ������ē`����āA�Ō�͒n�����H�ɒB����B�R�̒[����n�\�ɂ�����H�邱�Ƃ�����B���������A�₪�ĒJ��ƂȂ�A���ꂪ�������ĉ͐�ƂȂ�B
�����́A���l�ŕ��G�Ȋ��i�����j�����邽�߂ɁA�~�J���͐�ƂȂ�܂łɁA�������Ԃ�v����B���S�ɔ��B�����X�тł���A�~�J����x�ɎR���𗬂ꉺ�邱�Ƃ��Ȃ��A�X�т��\�����ې��@�\�����B������莞�Ԃ������Ĉړ����鐅�́A�X�тɐ������邠���鐶���ɗ��p�����B�������A�X�т��\������A�����̂ɂ����p����āA��蔭�B�������G�ȐX�т����グ��B
�A���̏��U��p�ŋɏo����̂�����A�����̓���ʂ��ĔA�Ƃ��ĘV�p����̊O�ɉ^�яo������������B�y��̐��n��������n�������݁A�͐�ɗ������B
�����̐����ɗ��p�����̂��A�n���ɂ��݂���Œn�����ƂȂ�̂��A�X�т̓����Ő����������ƈړ����邱�ƂɊ�Â��Ă���B
���R�E�ɑ��݂���W���S�ʂɂ��ď����ꂽ���̂ŁA�d�D�b�D�s���[�w���̎��R���x�i�Ñ��G�q�� �͏o���[�V��2001�j�قǑz���͂��������Ă��A�Ȋw�I�Ɍ����ŁA�������A������������Ă�����̂͒m��Ȃ��B���e�͒n�����̑��`�Ԃ���͐�A�Ώ��A���n�A�v�����N�g���Ƒ���ɂ킽���Ă��āA�������}���G�̐}�\��������Ă���B�����ŁA���̖��͓I�Ȗ{�̏Љ�����˂āA��Ɠ|�������Ă���ӏ������p���Ă������B

�܂��A�����B�X�ї���ł́A�͐�͔S�y�⍻���I����łȂ��A�����t��̎}�Ȃǂ̗L�@�����^��ł���A�����͐��ʂɕ�����ł�����̂�����A���ɐZ�����Ă�����̂��̂���B����ɁA�����̏�Q���Ƃ����A�ۑ��͋��I��������ӂ�Ă���B�X�ђn��̉͐�ł́A�������K�i�����Ă���̂́A�g�ݍ��킳�������I�ł͂Ȃ��|�ł���B�ǂ����낤�B���������A�J�������|������u�_���v�ɂ��Ď��グ�Ă���悤�Ȓ���ɁA�킽���͎n�߂ďo������B
���������I�̃_���͍\�����Ă�������������g�ݍ��킳���Ă���Ή����I�ł����̂ɑ��āA�|�̃_���͗L�@���ł��邽�߂ɁA��r�I���݂₩�ɕ�������B�|�͔������ɂ���Ď�߂�ꕅ�s���A���������Ɋ��݂�������ĉa�ɂ����B(�w���̎��R���xp173)
���ꂪ���܂葬���Ȃ���A��ʂ̗����t��̎}�Ȃǂ��ςݏd�Ȃ��ă_��������B���������_���́A�h�ߊ�̓��������āA�㗬����^��Ă����؋��△�@�͐ϕ�(�S�y�⍻)����������B�_���͂������ɑ傫���Ȃ�A�^�����N����Η������B�؋��̃_���́A�͓����̐��{�̊Ԋu�ł��Ȃ�K���I�Ɍ`������邱�Ƃ������B���̂��ƁA�R���ɂ悭��������J�̗����̌�́u���t�̃_���v�̐Ղł���u�t���ςݏd�Ȃ��Ăł����Ⴂ�K�i�v�ɂ��Ă̏ڍׂȕ��͂�����B�Ȃ��A���̖{�̌����wFresh Water�x�͂P�X�X�W�N�̏o�łŁA���҂̓J�i�_�ݏZ�B��P�P�́u�������ł��������Ȃ������v�̓v�����N�g����ۂ������Ă��邪�A�Íۂ�u�ΐF�ہv(�����̂���)�ɂ��Ă�����Ƃ����L�q�ɂȂ��Ă���B�i��5.5.b���A���E�ہE�Í��Œ���h�̉������Љ�����A�����Ȃ��ǂނ��Ƃ��ł���B�j
�����ɂ͑����E���l�Ȑ��������ނ��Ƃ��ł���B�����ɂ����l�Ȑ��������L�����Ă���B�Ƃ������A���݂̒n��̐����́A�����i���̉ߒ��Ő�������オ���Ă������̂ł���B�n��̍����ł����|�c������𐅒��ʼn߂������̂͑����B����������������̏���D�ɑ�������ł���B���̂ʂ߂�E���ۂ̔����w�́A�������̏W�܂�ł���B�傫�Ȋ���I�⍻�A���ӂ̈��␅���B����炪���o�����G�ő��l�Ȕ����ɁA���ꂼ��K���������������ݕ�����B����������_�f�L�x�ȏꏊ�B������ǂݒ�_�f�̓D�̑w�B
�����̑��l�Ȑ��Ӂ|�����̐��������́A�������^��ł���͗t�͂�}�E�������́E�V�p���Ȃǂ̗L�@�����g�H�ׂ�h�B���l�Ȕ����̒��ɑ��푽�l�Ȕ����������݁A���ꂼ�ꂪ�Ɠ��́g�H�ו��h������̂ł���B���̂��Ƃɂ���āA�L�@���̕������~�܂邱�ƂȂ��A�O��I�ɂȂ����B���̎��R�̕����ߒ��ł́u�]�艘�D�v�͂��蓾�Ȃ��̂ł���B
�H���A���̍��́A�P�ɂȂ������ł��邾���łȂ��A���l�Ȏ�@����g����鍽�ł���B���̍��̘A���̒��ŁA�L�@���͂���ƕ��q�ʂ̏����ȕ����ɕ�������Ă����B���̕����̉ߒ����A���𐴏���ߒ��ł�����B�������R�̏�p�Ƃ����̂́A���̂��Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
���̎��R����p�̈ꕔ���Ƃ肠�����A�H�ƋZ�p�I�ɑ�K�́E�����������̂��A���݂̉��������@�́u�������D�@�v�ł��邱�Ƃ́A���łɏq�ׂ��B
�����ɋ�C�𐁂�����ōD�C���ۂɁg�����h��H�ׂ�����B��C�𐁂����ނ̂ɑ��ʂ̓d�͂��g�����A���̕��A���������͂����̂ŁA����̓s�s�����̏����@�Ƃ��čD�܂�Ă���̂ł���B�G�l���M�[������^�̎�@�Ƃ��āA����s�s�ɓK�����Ă���Ƃ��������̂��Ƃł����āA�����āA�]�܂��������@���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B
���������Z�p�́A���R�̏�p�̈ꕔ�������グ�ăV�~�����[�g���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ŁA�������̉��������S�ɕ������I��邱�Ƃ͕s�\�ł���B�u�]�艘�D�v���o�邱�Ƃ��������Ȃ��B��5.3.b�����������ł́A�S�����x���]�艘�D�ƂȂ�Ƃ����L�q���Љ�Ă������B
���̗]�艘�D���A�u�����v�̂��������̔������ł���_�n�E�q��Ȃǂ֖߂��̂����z�I�����A����͓���B���D�̒��ɗL�Q�������������Ă��邱�ƁA�R���|�X�g�i�͔�j�����Ă��K�������_�Ƃ���������߂�Ƃ͌���Ȃ��B�i���{�����ɂ́A�L�@�_�@�������Ȃ��_�Ǝ҂�n��z�^�_�@�����݂Ă���n�悪���邪�A���������Ƃ���̎��v��傫������܂���ʂ̗]�艘�D���������Ă���͂��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���{�͑�ʂ̔_�앨�A�����ł��邩��B���̓_����5.3.b�߂Ŋ��q�B�j
���ʂ̉��w�엿���_�n�Ɏ{����Ă���̂�����ł���A���ꂪ�A���̂ƂȂ��ĐH�ƂƂȂ�B�ƒ{�����ƂȂ��ē��E�����i�ƂȂ�B�Ƃ���ƁA�����H�ׂĕ��A��r�����A������������Ăł���̂��]�艘�D�ł���B���ɗ]�艘�D�̑S�ʂ�_�n�Ȃǂ֖߂����Ƃ��ł����Ƃ���ƁA���ʂ̉��w�엿���s�p�ɂȂ��Ă��܂��B
����̍H�ƎЉ�ł́A��ʂ̉��w�엿�Y������������������K�v������B�]�艘�D�͏z������K�v�͂Ȃ��̂ł���B�z���Ă͍���̂ł���B�]�艘�D�̑����͏ċp�������A���̏ċp�D�݂��邩�A���z�f�ށE���H�ܑ��f�ނȂǂƂ��Ďg���B�܂�A�z�����Ȃ��̂ł���B�����āA�z�����Ȃ����Ƃ�����̍H�ƎЉ�������邽�߂̗v���ł�����̂ł���B
���肩�����ɂȂ邪�A�C�Â����_����Ă������B
- �u�������D�@�v�̋���ȏ�����̉������̂Ȃ��ł́A�������������܂���C�C�A�ɂ��܂�Ȃ���D�C�����������L�@����H�ׂ�B���������āA���̉������ł͒蒅�������肵�������D�ޔ������͔ɐB���ɂ����A���R�̐����E���ӂɂ�����悤�ȑ��l�Ȋ����p�ӂ���Ă��Ȃ��B�܂�A���R�̏�p�̂���߂ċǕ��I�Ȉ�ʂ����剻�������������̂��A����̉��������ł���B���̂��߁A�����̕����肪�傫���B
- ���������ł́A���C�����Łu���C�����v���Ђ��Â��s����i���Ƃ�����j�B�����Ŕ������郁�^����R���Ƃ��Ďg�p�ł��邵�A���f����̏������v���̂ŏ��������͖]�܂����̂����A����̓s�s�����̃V�X�e���̂Ȃ��ł͐�������Ă��Ȃ��B�Ƃ����̂́A���̌��C�����������`�P���̎��Ԃ�v���邩��ł���B
�����A�l�������ł́A���������Ō��C�^�D�C�ߒ����g�ݍ��킳��Ă���̂����ʂł���B�u�������v�����߂Ȃ���A���ꂪ�\�Ȃ̂ł���B - �H�ꉺ���Ȃǂ�����鉺���i���������j�ŁA�������ɗL�Q�ȕ����������ꂽ��A�������̐H���ɂȂ肦�Ȃ����@�^�L�@�����������ꂽ�肷��B�J���������i�������j���Ƃɂ���Ă��A�L�Q���o�Ȃǂ̗����͔������Ȃ��B�ƒ�r���ɂ���܂ȂǂŔ����������ł��Ȃ����̂�����B
- ���������̍ŏI�Y�����]�艘�D�̏������e�Ղł͂Ȃ��B�ܐ������傫���A�ċp�����͕s�o�ςł��邪�A��ʂł��邱�ƂƏ������x���l����ƁA����ɗ��炴������Ȃ��B�����ł��Ζ�������^�̋Z�p������ł���B
- ���������̍ŏI�Y�����]�艘�D�́A���ǁg�p���h�����B����́A���݂̉��������̒v���I�ȂƂ��낾�B���R�̏z�n�̂Ȃ��ɑg�ݓ���邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��̂ł���B
�l�Ԃ̐H�ו��݂͂Ȏ��R���i�����j�ł���B�����H�ׂĂ����āA���A�����R�֖߂����Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B����́A���R��������D�V�X�e���ł���B - ����ȉ��w�엿���Y��Ƃ́A���̎��D�V�X�e�����������߂Ă���B�y�n�i�A�����J�Ȃǁj�ɓ�������鑽�ʂ̉��w�엿�Ő��Y�����_�Y���́A���u�n�E�O���i���{�Ȃǁj�֗A���i�A�o�j����Ă����ŏ�����B���̌��ʐ�����]�艘�D�͏ċp��������A���݂����B���̂��ׂĂ̋ǖʂŁA�i�Ζ��j�G�l���M�[������^�̕������Ƃ��Ă���B
�������y�ł��A���w�엿��^���邱�Ƃő������x�A�앨����邱�Ƃ��ł���͎̂����ł���B�������A����𑱂��Ă���ƕa�Q���ɔ��Ɏキ�A��Q�ɂ��キ�Ȃ��Ă����B�܂��A�A�����J�Ȃǂł́A�J�ɂ���ĕ\�y�����o���r�p���Ă��܂����ۂ��L�������Ă���B�_�n�̍������ł���B�����́A�y�����������������邱�Ƃɂ����̂炵���B
��5.1�߁u���[�S�[�v�Łu�ۍ��ہv���Љ���B����͐A���̍��̂܂��ɐ��ސ^�ۗށi�J�r�j�̈��ł��邪�A�u�����ۍ��ۂ̓����́A���w�엿����������ƕs�v�ɂȂ邽�߂��}�����āv�i�����ׁw��������T��x�V���V��1998 p192�j���܂��Ƃ����B
�ۍ��ۂƂ͕ʂɁA�A���̍��̂܂��ɂ͌������~���̍����Ƃ���ۂ�J�r�̂Ƃ��ׂ̂��ݏꏊ������܂��B�����̒��ł͊O���Ƃ͂��������ہA�J�r���������Ă���A�ۑS�̖̂��x�͊O���̐��{�ȏ�ł��邱�Ƃ���ʓI�ł��B�܂����N�ȍ��̕\�ʂɂ��ۂ��W���������ĕ��z���Ă��܂����A�������������[�ɂ͔����������Ȃ����ە���������܂��B���w�엿�����ň�Ă�앨���a�Q���Ɏキ�Ȃ郁�J�j�Y���̐����͂��̂悤�Ȃ��̂ł���̂��낤�B�L�@�_�@�������Ȃ��Ă��鐅�c����Q�ɋ������R�̂ЂƂ́A���w�엿�Ɣ_��ɂ���鐅�c�Ƃ́A��Ă̍ۂɓy�����x���Ⴄ���Ƃ��������Ă���i�R���Ⴄ�Ⴊ����Ƃ����j�B�y���������̊����ɂ����̂ł��낤�B
���S�ȐA���̍����⍪�ʂ̔������́A�����番�傳��铜�Ȃǂ��h�{�Ƃ��ė��p�������A�A�����j�A�A�Ɏ_�A�����Ȃǂ̖��@�h�{����A���ɋ������Ă��܂��B�܂����ɐN�����悤�Ƃ���a���ۂ�j�~����͂��炫�����܂��B�i�����בO�f��p192�j
�i���I�Ȕ_�Ƃ̂��߂ɂ́A�L�@�_�Ɓi���w�엿�E�_��̎g�p���ł��邾���}����j���K�v�ł���B�����A�P�Ɂu�L�@�엿�v�Ƃ��������ł͕s�\���ŁA����_�n�łƂꂽ�앨�͂ł��邾�����̒n��ŏ���A�A���́i�m��A�}�t�Ȃǁj�╳�A�E�c�тȂǂ����̔_�n�ɕԂ��ďz�����邱�Ƃ�ڎw���ׂ��ł���B���ꂪ�\�ł��邽�߂ɂ́A�_�Ƃō앨����邱�Ƃ��u���i������v�ƍl���Ȃ����Ƃ������ɂȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B���i���s�ꌴ���Ŕ�������邱�ƂɂȂ�A���ۓI�H�Ɗ�ƁE�엿�Y�ƁE�_�@��Y�ƂɌ������킴����A���i�Ƃ��Ĕs�k����\�����傫���i����҂ƒ����Ƃ������������邪�A����͖{���I�����ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�A�Ƃ킽���͍l���Ă���j�B
�u�n��z�^�_�Ɓv�Ƃ������O���f���Ă���R�`������s�����C���{�[�E�v�����Ȃǂ́A�L�]���Ǝv�����A�c�O�Ȃ��琶�S�~����ɂ����ڂ������Ă��炸�A���A�엿�̖�肪���ʐ��Ęb��ɂ���Ă��Ȃ��悤���B
�����s�̏ꍇ�A�����Ƃ��ď�����ɗ������Ă���ŏI�I�ȏċp�D���ǂꂮ�炢�o�Ă���̂��A�\�ɂ��Ă��ڂɊ|����B
| �� | 17��3898����3 |
| �����r�o�� | 11��4367����3 |
| ���D������ | 6068����3 |
| �Z�k���D�� | 977����3 |
| �������D�� | 137����3 |
| �E�����D�� | 109�� ���@ |
| �E�����D�ċp�� | 103�� ���@ |
| �ċp�D������ | 4��7266 ���@ |
���ʂ����āA�Ƃ炦�ɂ������A���ʂɂ���ƒE�����D�ċp�ʂ� �Q�W�R�P���^���A�ċp�D�����ʂ� �P�Q�X���^���B�����S�� �g���b�N�V�O�O��]�̉��D���ċp�F�ɓ���A�R�Q��]�̏ċp�D���ł���Ƃ������ƂɂȂ�i���ۂɂ͉���������|�ċp��̊Ԃ͑��D�ǂňڑ����Ă���j�B�i�ʁ������{�J���B�֑��Ȃ���A���Ȃ�P��3�̏d�ʁ��P�� �Ȃ̂ŁA��\�̒P�ʂ́A���̂ɂ������Ă͂��悻����P�ʂƂ݂Ȃ��Ă����B�ʼn��i�̏ċp�D�͐������ł�̂ŕʁB�j
�i5.5.e�j�F�������ӂ��ތ���
�킽�������́A�H�ׁA�r������B����́A�����Ƃ��Ă̐l�Ԃ̊�{�I�^���ł���B�����������r���s���́A�l�ԂɂƂ��ĕ��ՓI�ł���A�����Ƃ��ς��Ȃ��B�ς�肦�Ȃ��B
�l�����͒������Ȃ����A���̂Ȃ��l�Ԃ͌��̂Ȃ��l�ԂƂقړ��`�ł����āA���肦�Ȃ��B�̓�����̘V�p���𐅗n�����Ĕr������A�́A����ɂ����̐��������ɓ��I�ɒ������Ă���̂ł����āA�l�H�t���i���́j�͂����Ă��A�r�A�Ƃ����r���s�ׂ����̂��̂���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�킽�������̔r���s�ׂ́A�����Ƃ��Ă̂���ꂪ�n���̐������̈���Ƃ��Ă��̕����z�̈�[�ɉ�����Ă��邱�Ƃ́A����I�Ȏ��H�Ȃ̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�H�ׂ�̂́i����~�l�����Ȃǂ������j���ׂĐ������̂�H�ׂ�̂ł���B������J�����Ă��哤���������॥�����A���ׂĂ��������̂Ȃ̂ł���B������A�����́A�r���������̐H���A���̍��Ɏn���������̏������@��m��Ȃ��̂ł���B���܁A�����������������Ȃ��Ă��銈�����D�@�Ȃǂ����ׂāA���R�E�̕����z�̕s�H�ȃV�~�����[�V�����ɂ����Ȃ��B�u���̐H���A���̍��ɓn���v�ȊO�̏����@��l�Ԃ͂�������Ƃ��Ȃ��̂��B
�����A����ɂ�������炸�A�����̕��A�́u���̐H���A���̍��ɓn���v���Ƃ��ł����ɁA�Ă���ĊD�ɂȂ�����A�L�ŋ����ƍ������Ēn���Ɂg�p�����h�Ƃ��Ċ��Ă�ꂽ�肵�Ă���B���������āA�����ɂ������̕����͏��������Ă��Ȃ��̂��B�B���Ċ��ĂĂ���ɂ����Ȃ��B���f����͂Ƃ肫��Ȃ��̂ŁA���Ȃ�̊����Ŋ����n�ւ��ꗬ���Ă��܂��Ă���B
���u�n�^�O���̔_��łƂꂽ�앨���s��ɏW�����A���A����������^�������ꂸ�A�p���E���݂���^���֏o�Ă��܂��B
���̕����̗���͏z�����A�ΐ��Ȉ����ʂ��Ӗ�����B�����āA�_�n�̍r�p�ƁA���̕x�h�{�������ʂ���B����̐��n�����Y�ƎЉ���o�����̖c��ȕ����̗���́A�Ƃǂ܂邱�ƂȂ��A�����Ă���B
�r���s��
���邭�����Ȑ���g�C���Ŕr���s�ׂ��ς܂��A�����֊�ŐK�����Ă��炢�A
�K�x�ɏ_�炩���z�����̂���g�C���b�g�y�[�p�[�ł�����Ɛ��C���z����点�āA
�R�b�N��P���ĉ����֗�������B
�S�{�A�S�{�A�S�{�B
���ꂪ�A�����̖����s���\�ԍs�ׂ��B
�Ȃ��Ȃ�A���̔r���s�ׂ͊������Ă��Ȃ�����B
�u�����A�T�b�p�������v
�{���́A���������T�b�p�����Ă��Ȃ��̂��B
�S�{�A�S�{�A�S�{�@�̏I�[�ł́A
�Ζ�������ŏĂ����A�ǂ����֔r�����Ă���B
�����Ȃ��悤�ɂ��Ă��邾���̋\�ԁB
�������������A�킪�̓���ʉ߂��āA
���A�����܂��B
�����܂ł́A�R�T���N�O����n�������̉������B
�����A�킪���A�́A
�����������̏z���E�֖߂邱�Ƃ��ւ����Ă���B
�����̕��A��Ζ�������ŏċp�������悤���A�L�ŕ����ƍ�������Ēn���ɔr������悤�ƁA���܂�Ȃ��B�����������K�Ȃ炻��ŗǂ��A�Ƃ����ԓx�͂��肤�邵�A���㕶���̑ԓx�������������̂��Ƃ�������B�Y�Ǝ��{��`�̍��x�Ȕ��W�i�K�ɂ��錻�㕶���́A���ԓI�ɂ͙��ߎ�`�ł����B������ɒ[�Ȍ`�ŕ\���Ă���̂��g�G�b�W�E�t�@���h�h�Ȃǂ̋��Z����Ƃł���B
�����A���̌��㕶���̑ԓx�����Ȃ̂́A�u���̑ԓx�͉i���ł��Ȃ��v�Ƃ����_�Ȃ̂��B �Ζ���������u���ΔR���v�ŗL���̖����ʂ����Ȃ���A�Ζ����g�����Ă��܂��Ƃ����������邱�Ƃ͖��炩�B�����A�����̏����́A�����Ζ��̟����̖������A�Y�_�K�X��^���K�X�̑����ɂ���n�����g���̂ق����������������ƂȂ��Ă���B
�Y�Ǝ��{��`�̍��x�Ȓi�K�ł��錻�㕶�������Ԑ����������Ƃ����߂��Ă���A�Ƃ킽���͍l���Ă���B���v�|�����A�~�]�̎����Ƃ����悤�Ȏ��{��`�o�ϗ��O�̍���ɁA���Ԑ������邱�Ƃ��A�킽���̍����I�ȃ��`�[�t�ł���B�������������n���̕����z�n���Ւf���Ȃ��l�Ԋ�������b�ɂ���A�Ƃ����̂͂ЂƂ̎��Ԑ��̓�����ł���B
�ł́A�Ȃ��u���㕶���̑ԓx���i���ł��Ȃ��v���Ƃ����Ȃ̂��B����ɂ́A�킽���͂ЂƂ����͂Ȃ��Ǝv���Ă���B����́u�����͖�����K�v�Ƃ��Ă���v����ł���B������O��ɂ��Ȃ��ƁA�����͂��蓾�Ȃ��B
�����ɂƂ��Ė����Ƃ��q���ł���B�����̎��ɐ��܂�ė���u�Ⴂ����v��O��Ƃ��Ȃ��Ő��������͂��蓾�Ȃ��B����́A�قƂ�ǐ����̒�`�ł���B
�l�Ԃ͊ϔO���E�i�u���������́u�����v�v�j�������Ă��邪�A���̂��Ǝ��̂����łɎ��Ԑ����Ӗ����Ă���Ƃ����ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A�u���������v��U��Ԃ��Č���Ƃ����u�u�����v�v���������Ԑ��̍����ł���Ǝv�����炾�B�i�G�Ɍh�ӂ�\���āA�u�����I�����v�Ƃ����Ă������B�j
�u�Ζ��͉��ΔR���ł͂Ȃ��v�Ƃ����g�[�}�X�E�S�[���h�̐����A�i�X�L�͎�����Ă��Ă���B�S�[���h�̖�{�Q���w�n���[�w�K�X�x�i���o�T�C�G���X1988�j�E�w���m�Ȃ�n�ꍂ�M�������x�i�匎���X2000�j�́A����������ɖʔ����B���^���E�n�C�h���[�g�̔��@����̉�������A���{���ӂɓ��{�l�̏����R���S�N���͂���Ƃ������Ă���B�������A�Ζ��ɑR�ł���قLj����ɍ̌@�o����悤�ɂȂ邩�ǂ����͂܂����m���B�o�ώY�ƏȂ̑��̂��������l�g�Q�P�́A�o�ϓI�Ɍ@��E�������Z�p�J���̃v���W�F�N�g�B
�ނ��냁�^���E�n�C�h���[�g�́A�f�������_���ӂ܂��Ēn���[������オ���Ă���Y�����f�̗��ꂪ����Ƃ����S�[���h�����A�x������L�͂ȏ؋��Ƃ��ĈӋ`������Ƃ킽���͎v���Ă���B
����ɂ��Ă��A���̖c��Ȗ����Y�����f�̋N�������ׂĉ��ΐA���ɋ��߂�͖̂���������̂ł͂Ȃ����B�Ζ����u���ΔR���v�ƌ��������Ă��܂��āA�܂������^���悵�Ă��Ȃ��_������ƁA�m�I�Ӗ�����Ȃ����Ƃ����v���B
�n�����g���ɂ���k���ɒn�т̕X�Z���^�C�ʏ㏸�^�ُ�C�ۂȂǂ́A���łɋߖ������l����̂ɖ����ł��Ȃ��t�@�N�^�ɂȂ��Ă���B���E�_�Ƃ̓����E�H�Ɛ��Y�̖�肪�A�l���}���ɂƂ��Ȃ��Đ[���Ȗ��ɂȂ����B���̎��m�̖��͘_�҂��������ƂȂ̂ŁA�����ł͐G��Ȃ��B
�킽�������̖��i�����z��f���錻��Y�ƎЉ�̖��j�ɖڂ��J���ꂽ�̂́A�Ɠc�ցw�G�l���M�[ �����ւ̓����}�x�i���{����1980�j��ǂƂ��ŁA�Q�O�N�قǑO�ł���B
�_������A�āA���֎����Ă����B���ł́A���͂⏈���\�͂��������牘���ɂȂ�킯�ł��B�v����ɁA�X�V�������̎g�����Ƃ����̂́A�o�����ꏊ�Ŏg���āA�o�����ꏊ�ɗ��Ƃ��A�Ƃ����̂���ԗǂ��̂ł��B���ꂵ���������т���@�͖����̂ł��B�ip62�j���_���������߂ɍēǂ��Ă݂����A���̖{�͌Âڂ��Ă���Ƃ���͂قƂ�ǖ��������B���{�̐H�Ǝ������͌��݂قڂS�O���i�M�ʃx�[�X�j�ŁA�P�X�U�O�N�ɂW�Q���������̂��A�Ƃǂ܂邱�ƂȂ�����Â��S�O�N�Ŕ����ɂȂ����i�Ȃ��A�����������������ƌ��݂Q�W���Ƃ������낵���قǂ̐����j�B�A����̓A�����J�A�����A�I�[�X�g�����A�Ȃǁi�P�X�X�W�N�ŃA�����J���R�W���i���z�x�[�X�j�ŁA�f�R�����j�B
�Ζ������̓����͓��R�@�ւɂ���A�܂�����ɂ�鉓�����̑�ʗA���ɂ���B���݃A�����J�����ʂ̐H�Ƃ����{�ɉ^��Ă��邪�A�����炭�A�߂������A�A�����J�̔_�n�͎��D�̌��ʔ敾���č앨���o���Ȃ��Ȃ邾�낤���A���{�̔_�n�͌����ȂǂŊ��S�j��āA����܂����Y���Ȃ��Ȃ邾�낤�B���A�Ζ���������w�����錈�S������Ƃ���A���̉������A���̔ے肩��n�߂�ׂ��ł��낤�B�܂�A�H�ƂƂ����̂́A�����z�̈ꕔ���ł��邩��A�l�Ԃ̂Ƃ���ł��̏z��邱�Ƃ́A�����̕ۏ����邱�ƂȂ̂ł���B�l�Ԃ��H�Ƃ𗘗p�������Ƃɂ��p���́A�H�Ƃ��y�֕Ԃ����Ƃ��K�v�ɂȂ�B�����āA�l�ԎЉ���܂߂������z�����������X�̌`�������G���g���s�[�𐅏z�ɓn���A�ŏI�I�ɂ͉F���֊��Ă�Ƃ����G���g���s�[�̗�������߂��K�v������B�ip107�j
�A�����J�ł͉��w�엿���ʂɗ^���A��`�q����앨��p���āA�_�앨�̑�ʐ��Y���s���Ă���B�u�������W���[�v�ƌĂ�鑽���Њ�ƂȂǂ����鍑�ێs�����ē��{�͐H����A�����Ă���B�Ɠc�̎w�E���Ă���悤�ɁA���́u�p���́A�H�Ƃ��y�֕Ԃ����Ƃ��K�v�ɂȂ�v�͂������A�������A�u�������W���[�v�͂���Ȃ��Ƃ��l���Ă����Ȃ��B�������y�n�͕������āA�ׂ̓y�n�ő���_�Ƃ��s���܂łȂ̂ł���B�y��̗i�������j�͐��E�Ŗ��N�T�O�O�`�U�O�O���w�N�^�[���i���{�̔_�n�ʐϒ��x�j�ƌ��ς����Ă���B����A�������̟������d��ł���B�[��˂ɂ��g���̉ߏ�ɂ���āA�n�����ʂ������荑�y�S���[���Ȑ��s�����P���Ă���Ƃ��낪�A���E���ł������w�E����Ă���B
���Ƃ����X�^�[�E�q�E�u���E���̃l�b�g��̘_�����s���͐H�ƕs���ɒ��������i2002�j����̓I�ɏ�������Ȃ���w�E�����̂́A�C�G�����E�C�����E�G�W�v�g�E�G�`�I�s�A�E�X�[�_���E���L�V�R�E�����ؖk�n���Ȃǂł���B�A�t�K�j�X�^���̐��s���̓y�V�����[����̒����N��t�̊����Œm���Ă���B�C���h�E�p�L�X�^�����A�����ăA�����J�����s�����疳���ł͂Ȃ��B
�܂�A�Ζ�������^�̕����ɂǂ��Ղ�Z�����Ă�������́A�y��̍������Ɛ��s�����\���I�ɏ����Ă����̂ł���B���{�l�͐��E������H�Ƃ��ʂɗA�����āA�ӂ�ɐH�ׂ�B���ꂪ�ǂ̂悤�ȍ��ۋ����Ƃ̎v�f�ɉ��������ƂȂ̂��C�����Ă��Ȃ��B����Ȃ��Ƃɂ͊S���Ȃ��B����ǂ��A���E�e�n�̔_�n�Ŏ��n�����H�Ƃ��͂��A�����Ă��āA���̕��A�͍ĂѐΖ��ŏċp���Ă���̂ł���B
���Y�n�̓y�낪���������ł���̂́A���R�ł���B�����Z���肵�Ă���̂�����A����̓G�R���W�J�������D�ł���B�������y�납��앨�邽�߂ɁA���w�엿�̑���Ŕ_�k���s���B���̕��������������Ȃ��B�y��̔������������Ă����Ȃ�����ł���B
�������A���܂��ɓ��{�ł́u�Ă̌�������v���s���Ă���B�P�X�V�O�N��Ɏn�܂������̋��s�͂����������ł������̂��B�ĉ��i�Ɛŋ��������ł���肾�����̂ł͂Ȃ����B�u�������W���[�v�Ƃǂ̂悤�Ȏ��������������̂��B��Q�����E���̎����ɂ����Ƃ��������������ƎЉ��`�I�ȓ������A�������X�ƂЂ�����A�����I�ȏ�o�����݂Ɏ����Ă���̂ł���B
���c�́A�ې����u�Ƃ��Ă����ɗD��Ă���A�����̕ۑS�̈Ӗ��ł��u��������v�͋��s�ł������Ǝv���B�Љ�S�̂��Y�Ǝ��{��`���悤�Ƃ��錻�݁A�_�Ƃ��̂��̂����������ׂ��ł���B���{�̂悤�ȍ��x���{���Љ�ł́A�_�Ƃ͐H�����Y�̈Ӌ`�����łȂ��A���ۑS�̈Ӗ��������Ă�����̂Ƃ��āA���c�ێ������サ�ėǂ��̂ł͂Ȃ����B�g���N�^�[�ȂǑ�^�@�B�̎g�p���������A�ł��邾�������̗������@�B�Ɛl�͂ɂ�鏬�K�͔_�Ƃ��߂������ƁB�������A�H�����Y����{�I�ɂ͎��Ɨp�̐H�����Y�Ɍ��肵�A���i�Ƃ��Ă̔_�앨�̈琬�����サ�Ȃ��悤�ɂ���̂ł���B��Ɣ_�ƂƂ������z�͎~�߂āA�H�Ǝ��������u�O�����_�Ɓv�̓`����������Ƃ����g�ƒ�؉��h�̔��z�ł悢�̂ł͂Ȃ����B�_�Ƃ��Y�Ǝ��{��`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�R���͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�_�Ƃ݂͂�����̌��ɓ����H�ו���������ʂȎd���ł����āA��ʁE���I�ȋ���Y�Ƃł���K�v�͂Ȃ��B����̋���_�Ƃ́A�P�W�C�P�X���I�̐A���n��`�̐����c��Ȃ̂ł͂Ȃ����B �v�����e�[�V�����o�c���c��Ȑ��̌��n������I�ȕn���J���҂ɒǂ����A�O���玝�������i�Ƃ��Ă̐H�Ƃ��ĐH�ׂ鐶�������������B
�i�u�O�����_�Ɓv�Ƃ�������A����ɂȂ��Ă���B�u�Q�O���I�̗��s��v�T�C�g�ׂ���P�X�U�R�N�̗��s�ꂾ�Ƃ����B���x�������ɂ������āA��������̒j�͋߂ɏo�ĉƂɂ��炸�A���������E�������E���������́u�O�����v�ł��낤���Ĕ_�Ƃ��s���𝈝��������t�B�j
���l�ɁA�ыƁE���Y�ƂȂǂ̂P���Y�Ƃ��u�O�����Y�Ɓv�Ƃ��Č��������ƁA���邢�́A���̎Y�ƂɈӋ`�����������҂́u���������Y�Ɓv�Ƃ��Čp�������邱�ƁA�Ȃǂ̔��z�̓]�������߂��Ă���A�ƍl����B
�ł��邾���H�ו������i�ɂ����A�����։^�������A�n��ŏ���ďz�����߂邱�Ƃ��A���l���镨���z�n�ł���ƍl���邱�ƁB���̉��l�ϓ]���Ȃ��ɂ́A����Y�ƕ������z���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�����Ă��邩�������������Ȃ��B
���ꂪ�����̂�������B
�˂ɐ����������̂Ȃ��Ɏ��݂��Ă���B
�ߋ��▢�����ǂ����ɂ���̂ł͂Ȃ��B
�����̂Ȃ��ɉߋ����������܂܂�Ă���B
���ꂪ�����̂�������B
���炭���̂܂ܐ����Ă���ƁA������A���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
���̂Ƃ�����͂����������Ȃ��B
������������
���̂킽�������̐�������
�����̐l�тƁA�܂�
�킽�������̎q���̕��S����肾���Ă���̂ɋC�Â����Ƃقǂ̗J�T�͂Ȃ��B
���̎q�������ƒ��Ɋ����킹�邱�Ƃ͂Ȃ����炩�܂�Ȃ��Ƃ͌����܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�ނ�͖����̂킽������������B
�����͖������܂�ł���B
�����͂����ȊO�̂ǂ��ɂ����݂��Ȃ��B
�u�H�ׂďo���v���̂��Ƃ�
�킽�����̎q���̕��S����肾���Ă���̂͗J�T�ł���B
���ɁA�J�T�ł���B
�����A�J�T�ł���B
���Ƃ���
�u���̗������ցv�A�u�j�̍��菬�ցv�ɂ��Ă��ꂼ��A�l�I�ȑ̌��������āA���_�������Ă݂�C�ɂȂ����B
�Ƃ����Ă��A�[���Ȍl�I�̌����������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�u���̗������ցv�́A�킽���̗c���N���Ɏ��͂Ō��������Ă������ʂ̂��Ƃ������Ƃ������ƁB�u�j�̍��菬�ցv�̓`�x�b�g���ʂ���{�R�̒T��Ƃ��Đ��s�����ؑ��썲���E�����O�Ƃ�����l�̊�L�Ȓj������m���Ē��ׂ��Ƃ��ɁA�������K���Ƃ��Ēm�����B�����̂��Ƃ́A���_�̎n�߂̍��ɏ����Ă������B
�u���ցv�̔r���s�ׂɂ��ď����i�߂邤���ɁA�킽�����v���������Ȃ���������Ɋ֘A�����Ă����B���̂��тɂ킽���͉����Ȃ��V��������ɓ��݂���ł������B�Ȃ��ł��������̂͏��������̖�肾�����B�����≼�ʂ̖����A�킽���́u���C�a�v�ɂ��Ē��ׂ��Ƃ��ɔ��������̂����A���ꂪ�A���������S���Ă����̂ł���B�u�������v�Ƃ��u�畆���o�v�Ƃ������Ƃ��l�ԂɂƂ��Ė{���I�ɏd�v���Ƃ������ƁA�������A���̖��͌`����I�ȕ���ɂ������т��g�����I�ȁh���삾�Ƃ������ƂȂǂł���B
�אڂ��镪��Ƃ��Ắu���ʁv��u�����v������B�X�J�g���M�[�ɂ��ẮA�i�E�f�E�{�[�N �w�X�J�g���W�[��S�x���3.3���u�A���v�ŁA�ق�̐\���킯���x�ɏЉ���B�����Ƃ����ƁA�L���[�����E�����邱�Ƃ������Ă��邪�A�����̗͗ʕs���ŁA���ݍ��߂Ȃ������B
�����������߂����āA�Q�O�N�قǑO�ɍl���Ă����n���K�͂̐H�Ɩ�������ɂȂ��������Ƃ��A���͈ӊO�������B��������d��œ�����ł����āA��T�߂͂ق�̑f�`���x�ɂ����Ȃ��B�֘A�����X�̕���ɁA������ƁA����������Ă݂��Ƃ����ʂ��B����ǂ��A�킽�������̕��ւ̖�肪���ځA���E�̕����z��Y�ƎЉ�̂�����Ɍ��т��Ă��邱�Ƃ��������Ƃ����A�Ƃ��������ňӋ`�͂���Ǝv���Ă���B
���������݂Ɋ֘A���ẮA���{�̊������̂��ƁE���x�Ƃ��ẲȊw�̂��ƂȂǂ��ꂼ��ʁX�̕����ŊS�������Ă������Ƃ��A��x�Ɋ֘A�Â��ďo�Ă��Ă��܂����B���̂��߂ɁA��T�߂͂��낢��Ȃ��̂��l�ߍ���ŁA���ꂵ������̂Ƃ�Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂����B�������A�킽���̌����\���Ă���̂ŁA���̂܂܂ɂ��Ă������ƌ��S�����B
�܂��A���̂��߂ɁA�ӂ����ł��܂�����T�߂������t�@�C���Ƃ��Đ蕪���ĕʗ��Ăɂ����B
�����̂킽���̗��V�ŁA�V�������Ƃ������Ɋw��ł������Ƃ��ʔ����āA�I�_�ɓ�������̂Ɏv������������Ԏ���Ă��܂����B�����o���Ă���قڂX�����ł���B�命���̕����͂킽���̋��Z�n���ӂ̌����}���ق𗘗p�����B�����}���ق̑������C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����悤�ɂȂ����̂ŁA����Ō��e�������i�߂Ȃ���A�K�v�Ȗ{��T�����肻�̖{�̉{����\����ł���B�����������@�ŕ����@����ʔ������A�킽���͏\���Ɋy���B
�V�����m���邱�Ǝ��̖̂ʔ����ƁA�����}���ق̗��p�Ƃ������Ɂg�����I�h�Ȏ�@�̖ʔ������킽���͋������Ă��������B
���e�I�Ȏ�@�i���@�_�j�Ƃ��ẮA�킽�����O����p�����Ă��������������ł����P�����B�܂�A
���������ۂɑ̌������������j�Ƃ��Ĉʒu�Â����B�������āA���̊j�ɏo���_��u���āA��������T���̎��L���āA����ɘA���I��@�œ��B�ł���͈͂̂��̂��L�q���Ă����B�������������o���Ă��邩����A�ǂ�ǂ�T���̎��L���Ă������ƁA�킽�����g���ʔ����v���Ă���̂Ȃ�ǎ҂ɂ��ʔ����͂����Ƃ����O��ŁA�i�߂�B���_�ɂ����Ă��A���̕��@�_���L���ł��������Ƃ��������Ă���B�������A�u���̗������ցv����o�����āA�s�s�_��n�����܂Řb���L���邱�Ƃ͗\�z���Ă��Ȃ������̂ŁA�����Ƃ��Ắg�ǂ̕ӂŔ[�߂邩�h�Ƃ������Ƃŋ�J�����B
���p�ɂ��āA���f������Ă����B
���_�Ɉ��p�������́E�}�ɂ��āA��A���쌠�҂ɋ��������߂Ă��Ȃ��B�����̂��̂́A�w�p�ړI�ł̈��p�Ƃ������Ƃŋ������͈͓��ł��낤�ƍl���Ă��邪�A�킽���ɗ��x������ꍇ�����낤���Ǝv���B���C�Â��̂��Ƃ�����A���L���[���ւ��w�E������������肪�����B�����ɁA�K�v�ȏ��u���Ƃ�܂��B
���C�Â��̂悤�ɁA�킽���͈��p�̍ۂɂ͂��邳���قǏo�T�L��������ł���B�S�����ǎ҂̕ւ�}�邽�߂ł��邪�A����҂ւ̌h�ӂƊ��ӂ̋C�����̈�[��\�����Ƃ��Ă�����B
���������̓ǎ҂ł����Ă��A�ǂ�ł��������������Ƃ����̂́A�٘_�̂悤�Ȃ��̂������ۂɂƂĂ��d�v�ł���B���ۂɂ͓ǂސl���[���ł����Ă��\�ԂƂ��Ă̓ǎ҂����݂��Ă���Ƃ��������ŁA��Ⴂ�ł���B�킽���̂悤�ɏ����ȃT�C�g���J���āA���̏�ł��̂������Ă����Ƃ�����@�́A�C���^�[�l�b�g����̂ЂƂ̂����ł���ƍl���Ă���B
���z�₲�ᔻ�����L���[���֊Ă���������A���肪�����B
�@kib_oe@hotmail.com
�Q�O�O�S�N�R��
����
�����Ɍf�����̂́A�������_�̂Ȃ��ň��p�����茾�y���������Ɍ����Ă��܂��B�����ł͂���܂��A�����}���قʼn{������ۂ̏��Ƃ��ď\�����Ǝv���܂��B
�i�����͂قڏo�����ł����A���m�ł͂���܂���j
| nb. | ��ҁE�Ҏ� | ��i�� | �o�ŎЁA�o�ŔN�i������Ώ��ŔN�j |
| 1. | �@ | ��A�G�� | �� ���{�G���听�S �������_��1985 |
| 2. | �a��h�O �Ғ� | ���{�햯�����G���i��P�`�T���j | �p�쏑�X1965 |
| 3. | �n�ӐM��Y | �]�˂̏������̃g�C�� | �s�n�s�n1993 |
| 4. | �����O | �鋫���攪�N�̐��s�@�㊪ | ���u���[1978�V���� |
| 5. | ���͈� | �p���c�������� | �����V����2002 |
| 6. | �i�Z�� | �������Ǝq | �p�앶��1975 |
| 7. | �{������ | �ʐ^�Ō�����{�����}���S�@���܂� | �O����1988 |
| 8. | �Ȓ��n�� | 㲗����^ | ���{���M�听 ��P���P �g��O����1975 |
| 9. | ���R�c�^�� | �����M�L | �������s��1908 |
| 10. | �쑽���ϒ�E�M�� | ��V�Η� | ���{���M�听 �ʊ�7-10 �g��O����1979 |
| 11. | ���B�ρE�a�c�v���� | �^�c���y�L | ���m����507 ���}�� |
| 12. | �Ŗ��� | ���V�A�ɂ�����j�^���m�t�̕֍��ɂ��� | �V������1990 |
| 13. | �\�����h�� | �V���G�L���� | ���m����499,504 ���}�� |
| 14. | �R�H�Α� | �g�C�������� | �����Ѝ�������o�ŕ�2001 |
| 15. | �����P | �c�s�ߐ� | �V�Q���ޏ]�P ��ꏑ�[1976 |
| 16. | ����F�� | ����F��S�W�T | ���}��1972 |
| 17. | ���c�����Y | �l�Ԃ̗��j�P�`�U | ������1951-57 |
| 18. | �I��S���Ғ� | ���A�̖����w | ��]��1996 |
| 19. | �䓛�r�F�� | �R�[���� | ��g����1957 |
| 20. | �W�����E�f�E�{�[�N �X�C�X�E�o�E�J�v������ | �X�J�g���W�[��S | ��c�^�I�� �|��1995 |
| 21. | ��쐷�Y,�������Ғ� | �A�W�A�̍l | �������[1994 |
| 22. | �����G�Y | �g�C���b�g�y�[�p�[�̕������|�l���n���w����| | �_�n��1987 |
| 23. | ��ؗ��i | �����m�g�C������� | �s�n�s�n�o��1992 |
| 24. | �w���h�g�X | ���j | ������H�� �}�����E�ÓT���w�S�W10 |
| 25. | �}���^���E���l�X�e�B�G | �r���S�� | �g�c�t���E�ԗ֏Ǝq�� �����[1999 |
| 26. | �a��h�O�� | ���������j�P�Q�@������ | �m�X��1955 |
| 27. | ���������� | �X�J���x�̌������� | �s�n�s�n�o��1991 |
| 28. | ���Ɛ��� | ���A�Ɛ������� | �ח���1987 |
| 29. | ��i�d�q | ���������j | ���q���X1991 |
| 30. | �����r�q | �킽����醔n�ɏ���ĉ���������ɂ䂫���� | ����1973�@�����Е���1982 |
| 31. | ����ߎq | �X�J�[�g�̉��̌��� | �͏o���[�V��1989 |
| 32. | �t���[�h���b�q�E�r�E�N���E�X | ���{�l�̐��ƏK�� | ���c��Y�� ������1965 |
| 33. | ���]�^�� | ���]�^���V���L�P | ���c���u�E�{�{��ꌻ���� ���m����54 ���}��1965 |
| 34. | ���c�n�`�� | ���]�^�� �����}�G | �����p��1989 |
| 35. | �����N�Y | ����M�̌n�� | �O�ꏑ�[1995 |
| 36. | ��t������ | ���{�������y�_ | �O����1980 |
| 37. | ��t���� | ���[�ƎR�̐_ | �䉮�}��1983 |
| 38. | �ԕ��юq | �l�Êw���猩�������̎d���ƕ��� | ���{�̌Ñ�P�Q�w�����̗́x�������_��1987 |
| 39. | �ː��� | ��ƂȂ��P�N�����̃g�C�� | �s�n�s�n�o��1992 |
| 40. | �@ | �M�M�R���N�G�� | ���{�G���听�S �������_��1977 |
| 41. | ������ | �����҂̊y�� | �V����2000 |
| 42. | ������ | �܂牮�̗Ǒ� �S�R | �o�t��1987 |
| 43. | �ɒO�\�O | ���{���Ԕ��̌n | ���t����1987 |
| 44. | �������� | �V�c�̉e�@�t | �V������1983 |
| 45. | �@ | �V�瑐�� | �����{�G���听�P�X �������_��1984 |
| 46. | �ܗ��d | �G�����Ɩ��� | �p��I��1981 |
| 47. | �ܗ��d | �@�������W���S �����M�̏��� | �p�쏑�X1995 |
| 48. | �W�����E�t�F�N�T�X | ����S | �����O���� ��i��1998 |
| 49. | �͌��d�C | �`�x�b�g���s�L �P�`�T | �u�k�Њw�p����1978�@ |
| 50. | �a�c���� | ���̐l�ފw�@�������猩���������� | ��������1994 |
| 51. | �{�{��� | �G�����Ɍ�����{���������� | �����V��1981 |
| 52. | �ؑ��ɕ��q | �ؑ��ɕ��q�ʐ^�S�W�@���a�����P�� | �}�����[1984 |
| 53. | ����ߎq | �Θb�� �����_ | �͏o���[�V��1991 |
| 54. | ���Ɛ��� | �̂܂� | ����V���Ł@��؎�1988 ����1961 |
| 55. | ���q�e�� | �~�\�N�\���̑� | �P����1996 |
| 56. | ���J�쒬�q | ������������ �S | �o����1969 |
| 57. | �L���T�����E���C���[ �ߓ����v��E�G�b�Z�C | �R�ŃE���R��������@ ���R�Ə��ɂ��������߂� | ���{�e���r������1995 |
| 58. | �����G�Y | �G�������E�̖ʔ��g�C������ | ���n�o��1998 |
| 59. | �ē�����E���V�{�q���� | �������֘^ | ���w��1998 |
| 60. | ��c�旧���y�����ٕ� | �g�C���̍l�Êw | �������p1997 |
| 61. | ��ؗ��i | �g�C���w���� | ���_��1988 |
| 62. | �^�R���_ | ���Ǎ^�� | �������s��1912 |
| 63. | �G���Q���x���g�E�P���y�� | �]�ˎQ�{���s���L | �ē��M��@���m����303 ���}�� |
| 64. | ��c�䂤 | ��������� �ʂ����܂� | �ѓ�1971 |
| 65. | �я�� | �^�^�E������Ɛ̂̐����G�� | ������1998 |
| 66. | �@ | ��S�����@�a���� | ���{�G���听�V �������_��1977 |
| 67. | �@ | �F���E�╨�� | ���{�ÓT���w��n�Q�V ��g���X1960 |
| 68. | �s�ۏ\��� | �ʐ^�łÂ��B�̖��� | ������1999 |
| 69. | �X�쏹�a | ���l�L�ːl�̎l�G | ���{�̌Ñ�S �w�ꕶ�E�퐶�̐����x�������_1986 |
| 70. | ��㖞�Y | �Ñ�s�s�̐��� | ���{�̌Ñ�X �w�s��̐��ԁx�������_1987 |
| 71. | �G���@�E�b�E�N���[�Y | �t�@���X�̉��� | ��g���X1989 |
| 72. | �킩������ | ���݂����̂��݂��� | �o�t����1997 |
| 73. | ���B�N�g���E���S�[ | ���E�~�[���u�� | ��㋆��Y��@�͏o���[�V��1989�@�͏o���E���w�S�W10 |
| 74. | ������ | �ܑ��Ɖ������̕��� | �_�n��1985 |
| 75. | �f���B�b�h�E�v�E�E�H���t | �n�������̋��� | �y��2003 |
| 76. | ������ | ��n�̔��������E | ��g�V��1987 |
| 77. | ������ | ��������T�� | �V���V��1998 |
| 78. | ���؈� | �����w�Ɋ�Â����̊�b���_ | �C��1999 |
| 79. | ���s��r | �R�����̐��E�j | ������1994 |
| 80. | ���W�F���A�����E�Q���� | �g�C���̕����j | ���^�J���X��@�}�����[1987 |
| 81. | ��Y�o | �������猩���s�s | �m�g�j�u�b�N�X1982 |
| 82. | �A���X�g�p�l�X | ���a | �w���E�ÓT���w�S�W�P�Q�x���Ït�ɕ� �}�����[1982 |
| 83. | �G���Q���X | �C�M���X�ɂ�����J���ҊK���̏�� | ��g���� �i�㉺�j 1990 |
| 84. | ���쏺�� | �a�C�̎Љ�j | �m�g�j�u�b�N�X1971 |
| 85. | ����G�v | �]�ˁE�����̉������̂͂Ȃ� | �Z�o��1995 |
| 86. | �n�Ӌ��� | ���������̖ʉe | �����[1998 |
| 87. | �����s�������ǎ{�݊Ǘ����^�� | �����s���������v�� | ���ő吳�R�N �����s�������ǍĔ��s1978 |
| 88. | ���і� | ���{���A��茹���l | ���Ώ��[1983 |
| 89. | ���X�ƐM | �����̓����v�� | ��g�����ド�C�u�����[1990 |
| 90. | ����܂��悵 | �o�L���[���J�[�͂��炩�����I | ���|�t�H1996 |
| 91. | ������ | ���{�̔p���� | ������ |
| 92. | �F�䏃 | ���{ ���Q���_ | ���I���[1988 |
| 93. | �����S�N�j�ҏW�ψ��� | �����S�N�j �S�U���ʊ��R | �����s1972�`78 |
| 94. | ����N�Y | �]�` �Z�t�E�R�m�̐��U | �u�k��1994 |
| 95. | �R�m�ʐ^�W�ҏW�ψ���� | �ʐ^�W �R�m�^�㐢�ւ̈�Y | �R�C��1994 |
| 96. | �Έ�M�E�R�c���A | ���v�� | �����o��1994 |
| 97. | �������q | ���̂��̐� | �ǔ��V����1990 |
| 98. | �������q | �s�s�̍Đ��Ɖ����� | ���{�]�_��1979 |
| 99. | �������q | �������F���Đ��̓N�w | �����V��1983 |
| 100. | �������q | ���̊��헪 | ��g�V��1994 |
| 101. | �{���~�T | ���o�C�I�w���� | �Z�o��2001 |
| 102. | �����s�������� | �����������P�O�O�N�j | �����s1989 |
| 103. | ���R�]�_�Е� | �����s���������Ƒ�ρf�W�O�N�x | ���R�]�_��1980 |
| 104. | �É�m�� | �Í� | UP BIOLOGY ����o�ʼn�1988 |
| 106. | �]���}�[�t�F���g | �M�͊w����ѓ��v�͊w | ���ӎq�� �u�k��1969 |
| 107. | �˓c���a | �M�E���v�͊w | ��������R�[�X�V ��g���X1983 |
| 108. | �V�����f�B���K�[ | �����Ƃ͉��� | �����V�E���ڋ��v��@��g�V��1951 |
| 109. | �g�[�}�X�E�S�[���h | �n���[�w�K�X | ���o�T�C�G���X1988 |
| 110. | �g�[�}�X�E�S�[���h | ���m�Ȃ�n�ꍂ�M������ | �ە��u�� �匎���X2000 |
| 111. | �d�D�b�D�s���[ | ���̎��R�� | �͏o���[�V��2001 |
| 112. | �Ɠc�� | �G�l���M�[ �����ւ̓����} | ���{����1980 |
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
